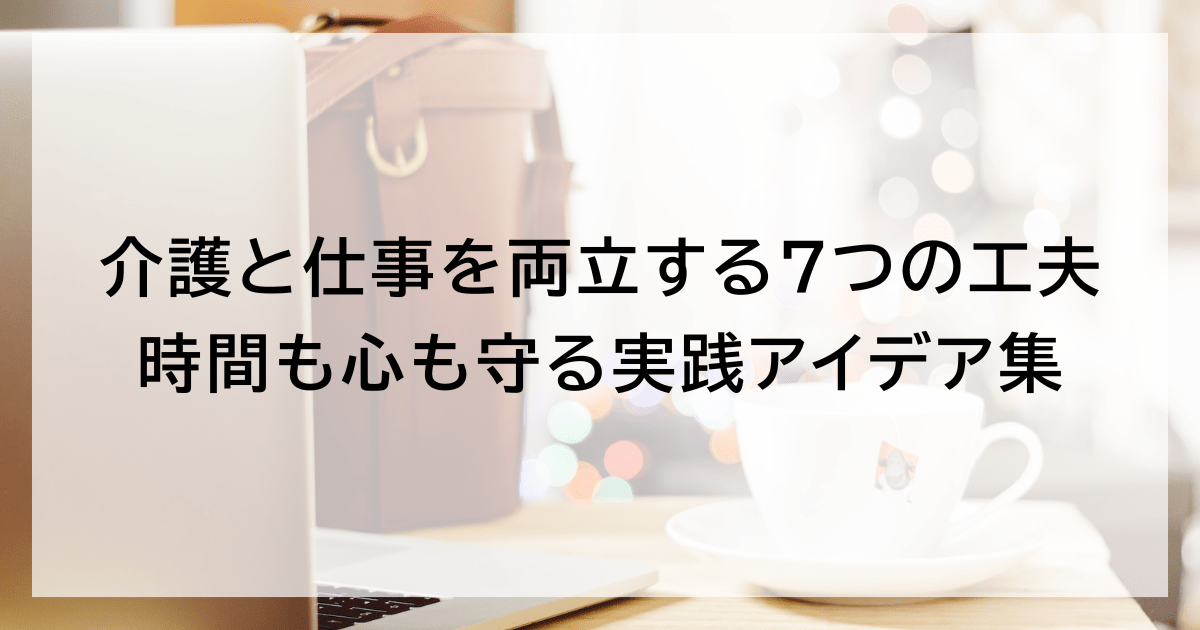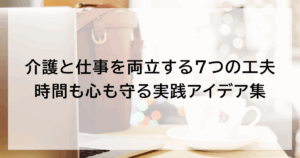仕事をしながら親や家族の介護を担う――
頭では「両立しなきゃ」とわかっていても、現実はそんなに簡単じゃありませんよね。
朝は出社前にデイサービスの送り出し、夜は帰宅してから食事やお風呂の介助。
気がつけば、自分の時間はほとんどゼロ。
気力も体力も削られて、仕事のパフォーマンスまで落ちてしまう…そんな不安や焦りを抱えていませんか?
実は、介護と仕事を両立している人は年々増えています。
特に40代〜50代の女性に多く、「周囲に相談できない」「無理して頑張るしかない」と一人で抱え込みがちです。
でも大丈夫。
少し視点を変えて工夫すれば、仕事を諦めなくても、介護を投げ出さなくても、両立は可能です。
この記事では「頑張る」のではなく「仕組みをつくる」ための7つの実践アイデアをご紹介します。
無理なく、そして長く続けるためのヒントを、一緒に見つけていきましょう。
- 親の介護が始まりつつある方
- 仕事に迷惑をかけたくないが、介護も手を抜けないと思っている方
まずは「両立できる環境」をつくる準備
介護が始まったときって、まるで大きな波に突然さらわれたような気持ちになりませんか?
「何から手をつければいいの?」と頭が真っ白になり、ただ毎日を回すだけで精一杯…。
私自身も母の介護が必要になったとき、最初の数週間は仕事も家事も乱れてしまい、夜は布団の中で涙が出ることもありました。
でも今振り返ると、最初に「環境を整える準備」をしていたら、もっと心に余裕を持てたはずだと思います。
介護と仕事を長く続けていくには、まず
- 介護サービスの情報を集める
- 職場に早めに相談する
- 家族で役割を分担する
この3つが大切な土台です。
介護サービスの使い方を知る
「介護は自分が全部やらなきゃ」と思い込んでしまう方は多いのですが、実は公的なサービスを使うことで負担を大きく減らせます。
ここは、介護に関する「なんでも窓口」で、介護認定の申請やケアマネジャーの紹介をしてくれます。
利用できるサービスには、訪問介護(ヘルパーさんが来てくれる)、デイサービス(日中に施設で過ごせる)、ショートステイ(短期間の宿泊)などがあります。
名前だけ聞くと難しそうですが、最初は「お風呂に入れるのが大変で…」「日中だけ見てほしいんです」と正直に話すだけで大丈夫です。
私も、母を週に2回デイサービスにお願いするようになったことで、数時間まとまった仕事時間が確保できました。
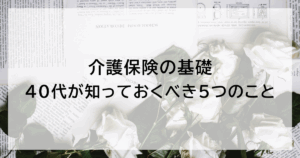
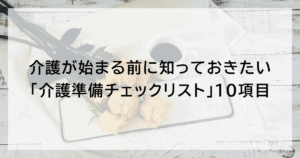
職場との調整のコツ
次に欠かせないのが、職場への相談です。
正直、私も最初は「迷惑をかけたくない」と口をつぐんでいました。
でも、介護は数か月で終わるものではありません。
早い段階で伝えておいた方が、周囲も理解して動いてくれます。
介護休暇や時短勤務、在宅勤務など、法律で認められた制度は意外と多いんです。
上司に伝えるときは、「家庭の事情でご相談があって…」と前置きをし、「水曜の午前はデイサービスの送りがあるので午後から出社したい」など具体的に話すとスムーズです。
上司に話すときは、「困っていること」だけでなく「こうすれば業務への影響を減らせそう」という提案をセットに。
たとえば、
- 午前中だけ在宅勤務にして午後は出社
- チームでスケジュールを共有して、急な早退時の引き継ぎを明確に
こうした言い方なら、相手も「一緒に工夫しよう」と前向きに受け止めてくれます。
私も思い切って話したら、「もっと早く言ってよ、みんなでサポートするから」と言われて拍子抜けしました。
家族の協力体制を整える
そして忘れてはいけないのが、家族との役割分担です。
介護が始まると「自分がやらなきゃ」と思い込んでしまいがちですが、それでは体も心も持ちません。
最初の段階で「誰が何をするか」を話し合っておくことが大切です。
たとえば「病院の付き添いは兄」「食事の準備は私」「金銭管理は父」といった具合に。
これを曖昧にしたまま始めると、後で「なんで私ばっかり…」という不満につながります。
もし家族だけで話すのが難しいときは、ケアマネジャーに同席してもらうのもおすすめです。
次のステップへ
こうしてサービスを把握し、職場と調整し、家族で協力体制をつくることができれば、ようやく「両立できる環境」の土台が整います。
最初にここをしっかり固めておくだけで、その後の日常の負担が驚くほど軽くなるんです。
次のステップでは、この環境を実際の暮らしの中でどう回していくか。
買い物や家事をラクにする工夫や、自分の心身を守る小さなケアについてお伝えします。
きっと「これならできそう」と思えるヒントが見つかりますよ。
7つの工夫の一覧表
| 工夫の領域 | 具体的な方法の例 |
|---|---|
| 家事負担を減らす | 宅配・冷凍食品・家事代行 |
| 介護記録の管理 | 介護アプリで家族共有 |
| セルフケア | 短時間運動・マインドフルネス |
| 生産性の確保 | 朝型勤務・タスク優先度見直し |
| 職場コミュニケーション | 言葉選び・業務分担相談 |
| 制度・支援の活用 | 介護休暇・在宅勤務制度 |
| 心の整え方 | 完璧を求めない・仲間づくり |
日々の負担を軽くする実践テクニック
介護と仕事、それに家事まで一緒に背負っていると、「一日が48時間あっても足りない!」と叫びたくなる瞬間、ありませんか?
私自身、母の介護をしていた頃、夜ベッドに入ると「今日もできなかったことばかり…」と頭の中で反省会が始まり、心がじわじわすり減っていくのを感じていました。
少し工夫を取り入れるだけで、肩の荷がふっと軽くなったんです。
結論から言えば、毎日の負担は「大きな改革」ではなく「小さな工夫」でちゃんと軽くできます。
まずは家事の時短、情報整理、そしてセルフケアという3つの切り口をお伝えします。
どれも「これならやれそう」と思えるものばかりなので、まずは1つから試してみてくださいね。
家事負担を減らす時短アイデア
まず真っ先に取り入れたいのが、家事の時短です。
介護でヘトヘトになっているときに、毎日のご飯や掃除を「完璧」にこなすなんて無理。
私も以前は「夕食は必ず一汁三菜で」と自分に課していましたが、それは理想であって現実ではありませんでした。
たとえば「Oisix(オイシックス)」のミールキット。
野菜はすでにカットされ、調味料も揃っているので20分ほどで食卓に並びます。
平日はこれで済ませ、週末だけゆっくり手作りする…そんなメリハリが、むしろ暮らしを豊かにしてくれました。
掃除や洗濯も同じです。
我が家にロボット掃除機が来てからは、夜「床掃除しなきゃ」と焦ることがなくなり、その分、好きな読書の時間を楽しめるようになりました。
「CaSy(カジー)」なら1時間3,000円前後から利用でき、スポット的にお願いするだけでも気持ちがぐっと楽になりますよ。
介護記録アプリやツールの活用
次に大事なのが「情報の整理」です。
介護をしていると病院の予定、薬の管理、ケアマネさんとの連絡…とにかく情報の洪水に追われますよね。
そこで救いになったのが、介護記録アプリ。
「おやろぐ」や「まごチャンネル」なら、服薬や通院スケジュールを家族みんなで簡単に共有できます。
Googleカレンダーを使うだけでも「次の通院は誰が付き添うか」が一目で分かり、余計なやり取りが減りました。
情報を一元化するだけで、「あ、伝え忘れた!」というヒヤリが減り、家族の空気もずいぶん穏やかになります。
介護は一人の力で回すものではなく、チームプレー。
だからこそ、ツールを味方につけることが、続けていくコツなんです。
自分の体と心を守るセルフケア
そして最後に忘れてほしくないのが、自分自身のケアです。
介護中はつい「親が優先、自分は後回し」となりがち。
でも、疲れ果てて倒れてしまったら、結局介護そのものが立ち行かなくなってしまいます。
セルフケアといっても難しいことは不要です。
朝5分だけストレッチをする、夜はスマホを置いて深呼吸をしてから眠る。
それだけで翌朝の気分が驚くほど違います。
最近はYouTubeで「寝る前ヨガ」や「ながらストレッチ」の動画がたくさん公開されているので、無料で気軽に試せるのもありがたいですよね。
私は半信半疑で始めたのですが、数分間呼吸に集中するだけで、介護中に心がザワザワしたときでも気持ちをリセットしやすくなりました。
大切なのは「自分を犠牲にしない」と決めること。
介護と仕事を両立する生活は、短距離走ではなくマラソン。
だからこそ、自分の体と心を大切に守ることが、結局は介護を続ける力になるのです。
介護と家事、仕事を同時に抱える毎日は、本当にエネルギーを消耗します。
でも「時短家事」「情報整理」「セルフケア」の3つを取り入れるだけで、負担は目に見えて軽くなります。
次のステップでは、そうして生まれた余裕をどう活かすか、そして周囲との信頼関係をどう守るかに目を向けていきましょう。
そこからさらに、前向きな毎日が開けてくるはずです。
仕事のパフォーマンスを落とさないために
仕事の生産性を守る工夫
介護と仕事を両立していると、どうしても
「今日は集中できないな」
「またミスしたらどうしよう」
と不安になる日がありますよね。
私も母が入院したとき、スマホが鳴るたびに心臓がドキッとして、パソコンの画面に集中できなくなったことがあります。
そんなときに一番大切なのは、自分を責めることではなく、「工夫でカバーする仕組み」を持つことだと痛感しました。
可能なら朝型勤務にシフトしてみるのもひとつの手。
介護の連絡が少なく比較的落ち着いている午前中に仕事を一気に進めると、午後に予定外の用事が入っても対応しやすいんです。
最近は「時差出勤制度」を導入する会社も増えていて、朝7時から働いて午後3時には退勤、という働き方をしている人もいます。
おすすめなのが 「優先順位の3段階ルール」。
- 今日必ずやること
- できればやりたいこと
- 明日以降でもいいこと
に分けるだけ。
私は「Todoist」というアプリを使っていますが、紙の手帳でも十分です。
頭の中でぐるぐるしていた不安が整理され、「今日はここまでできれば合格」と安心できるようになります。
「同僚に迷惑をかけたくない」
「評価が落ちるのでは」
と思う気持ちはよく分かります。
けれども、無理に抱え込んで空回りするよりも、効率よくやる仕組みを作ったほうが結果的に信頼を得られることが多いんです。
次に大事なのは、その信頼を守るためのコミュニケーションです。
信頼関係を壊さないコミュニケーション術
「介護のことを職場でどう話せばいいの?」と迷う人は多いと思います。
私も最初は上司にどこまで伝えるべきか悩みました。
たとえば、「親の介護で病院から急に連絡が来ることがあります。その際は早退の可能性があります」と事実だけ伝える。
詳しい家庭事情を細かく話す必要はありません。
必要な情報だけを相手に渡すと、上司も状況を理解しやすくなりますし、余計な心配をかけずに済みます。
それでも口頭で言い出しにくいときは、メールやチャットで
「〇〇の理由で勤務時間の調整が必要になる可能性があります。業務に支障が出ないように進行表をまとめておきました」
と送る方法もおすすめです。
私も資料を添えてお願いしたことがあるのですが、そのときは「ここまで準備してくれてありがとう」と言ってもらえ、むしろ信頼が深まりました。
同僚への配慮も大切です。
たとえば
「午後は介護の関係で電話に出られないかもしれません。そのときはチャットに残していただけると助かります」
とひとこと添えるだけで、周囲も協力しやすくなります。
言葉ひとつで関係性は大きく変わるものです。
そして、信頼関係を守りながら仕事を続けるためには、会社の制度や外部の支援を知っておくことが欠かせません。
社内制度・支援の使い方
「制度を使うと周りにどう思われるかな…」と心配で、なかなか利用できない方も多いのではないでしょうか。
たとえば「介護休暇」や「フレックスタイム制」「在宅勤務」。
コロナ禍をきっかけにテレワークが一般的になり、介護と仕事の両立がしやすくなったという声をよく聞きます。
私の知人は、午前中は病院に付き添い、午後から在宅勤務に切り替えるという働き方をしています。
「移動が減っただけで、気持ちも体もずっと楽になった」と話していました。
大企業だけでなく、中小企業でも工夫しているケースは増えているので、まずは人事や上司に制度の有無を確認してみましょう。
さらに、公的なサービスも頼れる味方です。
「地域包括支援センター」では介護の相談を無料で受け付けてくれますし、仕事との両立についての具体的なアドバイスももらえます。
「制度を使ったら評価が下がるのでは?」という不安は誰しも感じるもの。
だからこそ、制度を上手に活用することこそが、自分の健康と周囲との信頼を守る一番の方法なんです。
介護と仕事の両立は、想像以上にエネルギーが必要です。
でも「仕組みを整える」「信頼関係を築く」「制度を活用する」という3つの工夫を組み合わせれば、「介護だから仕方ない」と諦めずに、自分らしい働き方を守れます。
両立を長く続けるための「心の整え方」
介護と仕事を両立していると、
「私ばかりが頑張っている」
「親にもっと優しくできたのに」
と罪悪感で胸がいっぱいになること、きっとありますよね。
私自身、母の介護に関わっていた時期、イライラしてきつい言葉を投げてしまい、夜になってから「どうしてあんな言い方をしたんだろう」と泣きながら眠れなかったことがありました。
あのときの胸の痛みは、今でも忘れられません。
でも、ある先輩介護者に「完璧を目指すと続けられないよ」と言われて、すっと肩の力が抜けたのを覚えています。
私たちはロボットではなく、人間です。
感情もあるし、体力にも限界があります。
だからこそ、「できる範囲で最善を尽くす」という視点を持つことが、両立を長く続ける大きな鍵になるのです。
罪悪感や孤独感と向き合うヒント
罪悪感は、介護をしている人の多くが抱える共通の感情です。
大事なのは、「できなかったこと」ではなく「できたこと」に光を当てること。
たとえば「今日は病院に付き添えなかった」ではなく、「でも薬の管理は忘れずにできた」と考えてみる。
ほんの小さな達成でも「私、ちゃんとやれている」と自分を認められるようになります。
孤独感もまた、多くの人が直面する壁です。
だから、「私だけがこんな気持ちを抱えている」と思う必要はありません。
それはあなただけではなく、誰もが通る道。
同じ立場の人と話す価値
「誰かに話す」ことは、それだけで不思議なほど力になります。
私も地域の家族会に参加したとき、「こんなに同じ思いを抱えている人がいるんだ」と涙が出るほど安心した経験があります。
人は、共感されるだけで前を向く力が湧いてくるんですよね。
地域の社会福祉協議会が主催する「介護者のつどい」や「家族会」では、似た境遇の人と気持ちを分かち合うことができます。
対面が難しい場合は、オンラインの場も強い味方です。
たとえば「みんなの介護コミュニティ」では、匿名で弱音を吐けるので気楽に参加できます。
「人に迷惑をかけるんじゃないか」と遠慮する方もいますが、意外なことに、相手も「話してくれてよかった」と感じている場合が多いんです。
お互いの体験談からヒントを得たり、「自分だけじゃない」と思えたり。
孤独をやわらげる最短ルートは、同じ立場の人とのつながりなのかもしれません。
将来を見据えた相談先
介護は短距離走ではなく、長距離マラソンに近いものです。
数か月で終わる場合もあれば、数年続くことも珍しくありません。
だからこそ、早めに「頼れる相談先」を持つことが安心につながります。
身近な存在はケアマネジャー。
介護サービスを調整するだけでなく、「数年後を見据えた生活の組み立て方」まで一緒に考えてくれます。
ある知人は、ケアマネから「今から訪問介護を少しずつ取り入れていきましょう」と提案され、気持ちがふっと軽くなったそうです。
さらに、地域包括支援センターには社会福祉士が常駐していて、制度やお金の相談にも応じてくれます。
民間でも、「NPO法人となりのかいご」が開催する勉強会や座談会のように、経験者の生の声を聞ける場があります。
専門知識だけでなく、実際に介護を乗り越えた人の言葉には、未来を考えるためのヒントが詰まっています。
介護の出口が見えないと、心が真っ暗になることもあります。
大切なのは、完璧を求めすぎないこと。
弱音を吐ける仲間とつながること。
そして、未来を一緒に考えてくれる相談先を持つこと。
全部を明日からやる必要はありません。まずは「今日は自分を責めない」と心に決めるだけで十分です。
その小さな一歩が、長く介護と仕事を続けていくための大きな力になるのだと思います。
まとめ
介護と仕事の両立は「気合い」や「根性」で乗り切れるものではありません。
続けていくためには、「がんばり方」を工夫することが大切です。
今回ご紹介した7つの工夫――
- 家事負担を減らす時短アイデア
- 介護記録のデジタル管理
- 自分の体と心を守るセルフケア
- 仕事の生産性を落とさない働き方
- 信頼関係を崩さない職場コミュニケーション
- 社内制度や社外サービスの活用
- 長く続けるためのマインドセット
どれも特別なスキルやお金が必要なものではありません。
たとえば、料理は宅配サービスや冷凍食品を賢く使えば、1日1時間以上の時短が可能です。
介護記録をアプリで共有すれば、家族間の連絡トラブルが激減します。
フレックスタイムや在宅勤務制度を活用すれば、通勤の負担が減り、急な呼び出しにも対応しやすくなります。
一番大切なのは、「全部自分でやらなきゃ」という思い込みを手放すこと。
「完璧を目指すのではなく、続けられる仕組みをつくる」
その発想に変えるだけで、気持ちは驚くほど軽くなります。
また、同じ立場の人とつながることも忘れないでください。
地域の家族会やオンラインコミュニティでは、「自分だけじゃない」と思えるだけで心が救われます。
専門家との定期相談を習慣にすれば、先を見据えた安心感も得られます。
だからこそ、無理せず続けられる形を選んでください。
この7つの工夫が、あなたの毎日に少しでも余裕をもたらすきっかけになれば嬉しいです。
- 完璧を目指さず、続けられる仕組みを優先することが両立の鍵
- デジタルツールや社内制度・社外サービスを活用して負担を分散
- 同じ立場の人や専門家とのつながりが、心の余裕をつくる
7つの工夫の一覧表(再掲)
| 工夫の領域 | 具体的な方法の例 |
|---|---|
| 家事負担を減らす | 宅配・冷凍食品・家事代行 |
| 介護記録の管理 | 介護アプリで家族共有 |
| セルフケア | 短時間運動・マインドフルネス |
| 生産性の確保 | 朝型勤務・タスク優先度見直し |
| 職場コミュニケーション | 言葉選び・業務分担相談 |
| 制度・支援の活用 | 介護休暇・在宅勤務制度 |
| 心の整え方 | 完璧を求めない・仲間づくり |