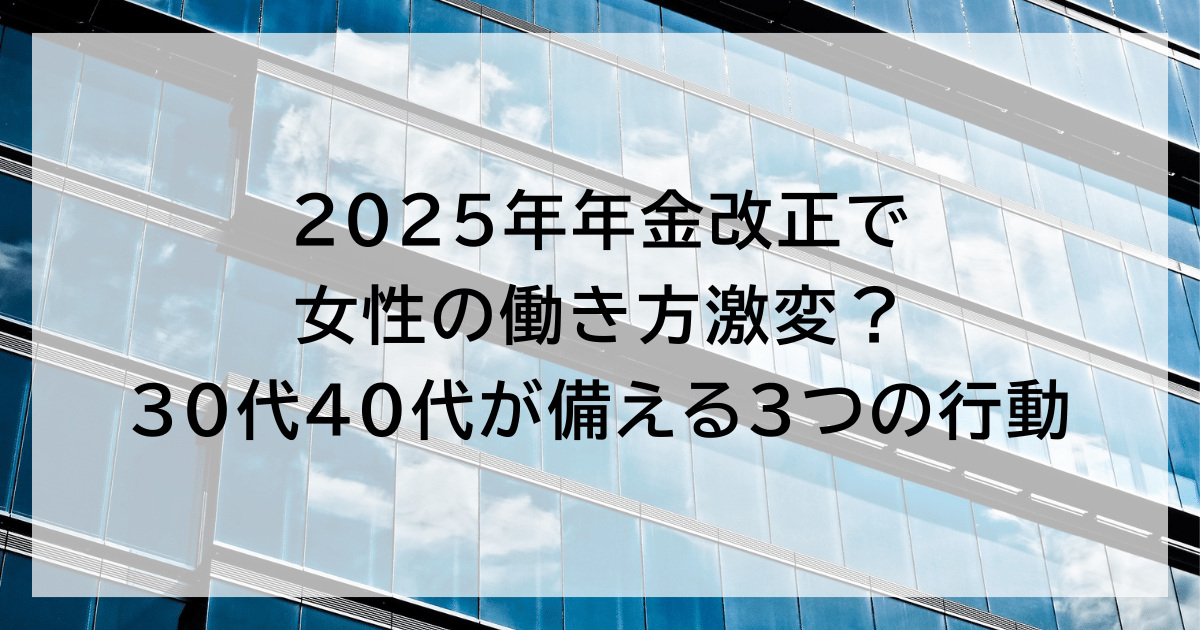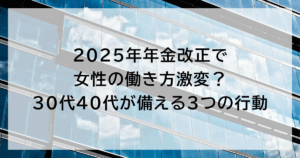2025年6月、年金制度改正法が成立しました。
2025年は大きな税制改正もあり、これまで働く女性がよく耳にしてきた「103万円の壁」は「160万円の壁」へと引き上げられました。
そして年金制度もまた、大きな転換を迎えています。
「106万円の壁」の実質撤廃や、遺族厚生年金が期間限定になる「有期化」など、暮らしや働き方に直結する変更が次々と進むのです。
これまで「収入を抑えれば大丈夫」という考えが、多くの家庭で常識とされてきましたが、その前提が大きく揺らいでいます。
正直に言えば、私自身も子育てと仕事をどう両立させるか、そして「扶養の範囲で働くか、それともキャリアを優先するか」で何度も悩んできました。
同じように、友人との会話でも「壁を気にしてシフトを減らすか、それとも思い切って働くか」という話題が尽きないのをよく覚えています。
けれども今回の改正は、その悩み方そのものを変えてしまう出来事です。
つまり、「制度の壁に働き方を合わせる」のではなく、「自分や家族のライフプランに合わせて選ぶ」ことが、これまで以上に大事になるのです。
たとえば、短期的には手取りが減っても社会保険に加入すれば、将来受け取る年金額が増えるだけでなく、出産手当金や傷病手当金といった制度も利用できます。
一方で、「今は子どもとの時間を優先したい」という時期には、扶養内にとどまる選択肢も現実的です。
ただし、遺族厚生年金が有期化される今後は、「夫に何かあっても年金で支えられるから安心」という従来の前提は通用しません。
だからこそ、自分名義での資産形成を始めることが、これからの安心に直結していきます。
この記事では、2025年の年金制度改正法のポイントを整理しながら、30代40代の女性が「今からどんな行動を取ればいいのか」を、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
- パートやアルバイトで働きながら「扶養内でいるべきか、社保に入るべきか」迷っている方
- 子育てや介護と両立しつつ、自分のキャリアや収入の伸ばし方を考えたい30代40代女性
- 「103万円の壁」や「106万円の壁」など年収の壁の仕組みをわかりやすく整理したい方
- 遺族厚生年金の有期化や制度改正に備えて、家計のリスク対策を考えている方
- iDeCoやつみたてNISAなどで、将来に向けて資産形成を始めたいけれど最初の一歩が踏み出せない方
2025年年金改正の全体像と30代40代女性への影響
正直に言うと、2025年の年金制度改正は「ちょっと難しい話」に聞こえるかもしれません。
でも実際は、私たち30代40代女性の「働き方」「家庭のあり方」「将来の安心」にダイレクトにつながる大きな出来事です。
これまでの制度は「夫が正社員、妻は専業主婦やパート」という古いモデルに寄りかかっていました。
今回の改正は、そんな時代の流れに合わせて大きく舵を切った、といえるでしょう。
私自身もフルタイム勤務と家庭の両立に悩んだことがあります。
だからこそ、この改正は「制度が遠い話」ではなく「私の生活そのものに関わるテーマ」だと感じています。
改正の背景にあるのは「社会の変化」
厚生労働省が公表した「法律の概要」を見てみると、今回の改正は「少子高齢化の中で年金を持続可能にすること」と「多様な働き方に対応すること」が目的とされています。
支える人が減り、受け取る人が増える現実を前に、従来の制度を維持するのは難しい。
だからこそ、より多くの人に社会保険に参加してもらい、できるだけ長く安心して働けるように制度を整える必要が出てきたのです。
具体的な改正の5つの柱
改正の中身をもう少し具体的に見ていきましょう。
大きなポイントは次の5つです。
- 社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象拡大(2027年以降段階的に施行)
-
いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上働けば社会保険加入の対象になります。
さらに、これまで「従業員51人以上」だった企業規模要件も段階的に縮小され、将来的には「10人以下」の会社まで広がる予定です。
- 在職老齢年金の見直し(2026年4月施行)
-
60代以降も働きながら年金を受け取れる仕組みが広がり、支給停止額の基準が引き上げられます。
これにより「働きたいけれど年金が減るからセーブする」という選択をせずに済む人が増えます。
- 賃金上限(標準報酬月額)の引き上げ(2027年9月から段階的に施行)
-
高収入層は保険料負担が増える反面、将来の年金額も増えます。
- 遺族年金の男女差解消(2028年4月施行)
-
妻と夫で条件が異なっていた遺族厚生年金は、2028年から「原則5年間の有期支給」に統一されます。
「もし夫を亡くしたら…」と不安を抱える女性にとって、制度の前提が変わる大きな改正です。
- 私的年金制度(iDeCoや企業型DC)の拡充(2028年6月までに施行予定)
-
iDeCoの加入年齢は70歳未満までに引き上げられ、拠出額の上限も増えます。
企業型DCとの併用もしやすくなり、自分で積み立てていく力がより重視されます。
女性にとっての意味
これらをまとめると、国が目指している方向性は「長く働き、社会保険に入り、自分でも資産を準備する人を増やす」こと。
とくに30代40代女性は、子育てや介護の真っ只中で「扶養内に収めるか」「キャリアを広げて社保に入るか」を選ばざるを得ないタイミングにいます。
だからこそ、この改正は「私たち世代に一番響くテーマ」といえるのです。
もちろん、不安はつきものです。
「手取りが減ったら生活は大丈夫?」
「遺族厚生年金が短くなったら老後はどうなる?」
そんな心配を抱くのは自然なこと。
でも長期的にみれば、社会保険加入は将来の年金額や医療保障につながりますし、遺族厚生年金の見直しも「女性が経済的に自立して生きられる社会」への制度調整だと考えることもできます。
つまり、この改正を「負担増」とだけ捉える必要はありません。
むしろ「これからの働き方や家計設計を考える絶好のチャンス」と前向きに活用することができます。
次の章では、その中でも特に注目される「106万円の壁撤廃」が私たちの働き方にどんな選択肢を広げるのか、具体的に見ていきましょう。
「106万円の壁」撤廃がもたらす働き方の選択
「106万円の壁」の撤廃は、一見すると「もっと働けるようになるチャンス」に見えますが、実際には「働き方の分かれ道」を私たちに突きつけています。
これまでは「年収を106万円以内に抑えれば安心」という発想でよかったかもしれません。
けれども最低賃金の上昇によって、週20時間以上働けば自然とこの壁を超えてしまう時代になりました。
つまり、これからは「収入を抑えるかどうか」ではなく「勤務時間をどう調整するか」が現実的なテーマになるのです。
では、具体的にどんな選択肢があるのかを整理してみましょう。
勤務時間を抑えて扶養を維持する場合
正直なところ、かつて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」が全く別物だとはじめて知ったとき、私は少し混乱してしまいました。
似たような言葉なのにルールが違うなんて、まるで同じ名前の料理なのに味が全然違うような感覚です。
だからこそ、働き方を考えるときには必ずこの2つを分けて理解することが欠かせません。
まず「税法上の扶養」。
こちらは2025年の税制改正で大きく変わりました。
これまで「103万円の壁」と言われていた所得税の非課税ラインが、「160万円」へと一気に引き上げられたのです。
たとえば年収150万円で働いても、自分の所得税はかからず、夫の配偶者控除・配偶者特別控除も維持されるケースが多くなります。
これは、多くの働く女性にとって「少し安心して働ける」朗報といえます。
一方で「社会保険上の扶養」は別の仕組みです。
ここで登場するのが「106万円の壁」と「130万円の壁」。
改正後は、賃金額の基準ではなく「週20時間以上働けば加入」というルールが基本となります。
つまり、収入を調整するよりも「週20時間未満で働くかどうか」が分かれ道になるのです。
さらに「130万円の壁」は残ります。
年収130万円を超えれば、働く時間に関わらず社会保険上の扶養から外れるため、自分で社会保険(または国民健康保険)に入らなければなりません。
扶養を維持するメリットはわかりやすいです。
社会保険料を払わなくていいので手取りが多くなり、税法上も配偶者控除が使えます。
特に「今は子どもに手がかかるから、少しでも時間とお金に余裕を持ちたい」という時期には、この働き方が安心を与えてくれます。
でも同時に、デメリットもあります。
勤務時間を週20時間未満に抑えるということは、シフトを増やしたいときでも我慢しなければならない。
最低賃金が上がり続ける中で収入を伸ばせず、物価上昇に追いつけない可能性もあります。
さらに、将来の年金は国民年金だけにとどまり、老後資金に不安が残る…。
これは私自身も強く感じる部分です。
「今は安心だけど、この先どうだろう?」と夜寝る前に考えてしまうのです。
要するに、扶養を維持するのは「今の生活を守る」ための選択肢。
でも将来を考えると、必ずしもベストではないかもしれません。
そこで次に、「社会保険に加入して働く」という道を見ていきましょう。
社会保険に加入して働く場合
結論から言えば、社会保険に入ることは「今は少し手取りが減るけれど、将来の安心と働く自由を得られる」選択です。
厚生年金に加入すれば、将来の年金額が確実に増えます。
国民年金だけだと満額でも月6万円ほど。
でも厚生年金が上乗せされれば、老後の暮らし方が全く変わります。
加えて健康保険に入れば、出産手当金や傷病手当金などが利用できます。
私も出産で休んだとき、手当金に助けられた経験があり、「あの時入っていてよかった」と心から思いました。
もちろんデメリットもあります。
毎月の社会保険料がかかるため、手取りが減ります。
税法上の配偶者控除・配偶者特別控除もなくなる場合がある。
ただ、2025年の改正で「160万円までは税金がかからない」ようになったため、従来よりは扶養から外れるハードルが下がりました。
何より大きいのは、「働き方を制限しなくてよくなる」ことです。
これまで「壁を超えないように調整」していた人も、気兼ねなくシフトを増やせる。
キャリアアップのチャンスもつかめる。
つまり、社会保険に加入するのは「今の損」ではなく「将来の安定」への投資だと考えるのが自然でしょう。
では実際に、どれくらい手取りが変わるのか?
具体的なシミュレーションを見てみましょう。
家計への影響シミュレーション
2025年改正で税法上の扶養は緩やかになった一方、社会保険のルールは残っています。
代表的なケースを整理しました。
| 年収 | 税法上の扱い | 社会保険上の扱い | 手取りイメージ | 将来年金増加 |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 配偶者控除内。所得税なし(地域により住民税発生あり) | 週20時間未満なら扶養内。週20時間以上なら加入義務の可能性 | 扶養内なら約110万円、加入すれば約95〜100万円 | 厚生年金加入なら+数千円〜 |
| 130万円 | 配偶者控除内(税金なし) | 「130万円の壁」を超えるため勤務時間に関係なく加入義務 | 手取り約115万円前後 | 国民年金+約1万円 |
| 150万円 | 配偶者特別控除の満額対象 | 自分で加入 | 手取り約130万円前後 | 国民年金+約2万円 |
| 180万円 | 配偶者特別控除は減額開始 | 自分で加入 | 手取り約155万円前後 | 国民年金+約3万円 |
こうして見ると「110万円で抑える」か「130万円を超えてしっかり働く」かが大きな分岐点です。
中途半端に120〜129万円で働くよりも、思い切って130万円を超えて社会保険に加入した方が、保障や年金の点で有利になるケースが多いのです。
遺族年金・私的年金改正と女性が押さえておくべきポイント
正直に言うと、2025年の年金制度改正は「ただの制度変更」ではありません。
女性のライフプランそのものに直結する、大きな転換点です。
柱となるのは「遺族厚生年金の有期化」と「私的年金制度の拡充」。
これまで「夫にもしものことがあっても遺族厚生年金で暮らせる」と考えていた方にとって、その前提が崩れつつある一方で、「自分で備える手段」が広がった、とも言えるのです。
まるで、これまで敷かれていた一本のレールが分岐して、「自分で進む道を選ばなくてはいけない」時代がやってきた感覚に近いかもしれません。
遺族年金の有期化:5年で終わる「支え」
まず大きな改正点は、遺族厚生年金です。
これまでは、30歳以上で夫を亡くした妻は、基本的に生涯にわたって遺族厚生年金を受け取れました。
けれども2028年以降は、男女差の解消を目的に「原則5年間のみ」に変わります。
障害がある方や収入が著しく少ない方など例外はありますが、多くの人にとって「5年経ったら自分の収入で暮らしていく」ことが当たり前になります。
私自身、知人が突然夫を亡くし、遺族厚生年金に助けられたケースを間近で見たことがあります。
その時の安心感は計り知れません。
でももし支給が5年で打ち切られていたら…と考えると、背筋が冷たくなる思いがします。
今後は「夫の年金があるから何とかなる」という考えでは立ち行かなくなるのです。
iDeCo・企業型DC:自分で積み立てる選択肢が拡大
では、どう備えればいいのでしょうか。
そこで鍵になるのが「私的年金制度の拡充」です。
今回の改正で、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢は、65歳未満から70歳未満へと広がりました。
さらに、拠出限度額も引き上げられました。
「もっと積み立てたいのに上限が低すぎる」と感じていた人にとっては朗報です。
たとえば、パートで年収150万円の方が月1万円をiDeCoで積み立てるだけでも、節税効果を得ながら老後資金を増やせます。
企業に勤めている人なら、企業型DCと合わせることでさらに大きな準備が可能になります。
最近は、スマホアプリで残高や運用状況が「見える化」されていて、資産運用がぐっと身近になっているのも心強いところです。
「働き方」と「資産形成」を切り離さない
ここで大切なのは、働き方とお金の備えを別々に考えないことです。
遺族厚生年金が有期化されるということは、「もし夫に何かがあっても、年金で一生支えてもらえる」時代は終わるということ。
逆に言えば、自分で働く力と、自分で資産を積み立てる力を両輪で育てていくことが、これからの30代40代女性にとっての「生き抜く知恵」になるのです。
私自身、子どもがまだ小さく「今は目の前の生活で精一杯」と思う瞬間がたくさんあります。
でも同時に、「10年後、20年後の私が安心して暮らしている姿」を想像すると、今から少しずつでも備えておきたいと強く感じます。
今からできる小さな一歩
「じゃあ、何から始めればいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
最初の一歩は、身近な制度を確認すること。
その上で、自分のペースで始められるiDeCoやつみたてNISAを少額から利用するのがおすすめです。
月5,000円でも、10年後には大きな安心に変わります。
結局のところ、今回の改正は「遺族厚生年金に依存する時代から、自分で準備する時代へ」というメッセージです。
最初は不安かもしれません。
でも、これは「自分らしい働き方と暮らし方をデザインできるチャンス」でもあります。
次の章では、具体的に30代40代女性がどうライフプランを組み立てればいいのか、その行動ステップをご紹介していきます。
30代40代女性が今から備える3つのアクション
勤務時間とキャリアの選択肢を整理:扶養内か、加入してキャリアを積むかをライフプランと照らして決める
ここ数年、「年収の壁」という言葉を耳にするたびに、私もドキッとしてきました。
けれど、2025年の制度改正でその「壁」の風景は大きく変わっています。
これからは「壁に合わせて働き方を調整する」よりも、「自分や家族のライフプランに合わせて勤務時間やキャリアを選ぶ」ことが大切になってきたのです。
たとえば、これまで多くの女性が意識してきた「103万円の壁」。
これは「160万円の壁」へと引き上げられました。
そのため、「103万円を超えたら損になるから」と仕事をセーブする必要はなくなったのです。
けれど一方で、社会保険のルール――週20時間以上働けば加入義務が出てくる「20時間の壁」、そして年収130万円を超えると自動的に加入となる「130万円の壁」は残っています。
改正前後の「年収の壁」比較
| 年収ライン | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 100万円の壁 | 住民税が発生 | 110万円に引き上げ |
| 103万円の壁 | 所得税が発生 | 160万円に引き上げ |
| 106万円の壁 | 社会保険加入要件 | 実質「週20時間の壁」に |
| 130万円の壁 | 社保加入義務 | 継続 |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除減額開始 | 160万円に引き上げ |
つまり、女性が直面するのは、
- 「短期的な手取りを優先して扶養内で働き続けるか」
- 「社会保険に加入してキャリアや働き方の自由度を広げるか」
という選択です。
扶養内であれば安心感がありますが、勤務時間を20時間未満に抑える必要があり、昇進やスキルアップの機会は限られてしまいます。
逆に社会保険に加入すれば手取りは一時的に減りますが、厚生年金や健康保険で将来の備えが手厚くなり、勤務時間や収入を思い切って伸ばせます。
子育て真っ最中で今は家庭を優先したい方なら扶養内が現実的かもしれません。
でも、将来の老後資金やキャリア形成を考えるなら、社会保険に入って働き続けた方が安心につながることも多いのです。
扶養内 vs 社会保険加入の比較
| 働き方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 扶養内(週20時間未満) | 社会保険料不要、短期的な手取り最大化 | キャリア制限、将来年金は国民年金のみ |
| 社会保険に加入 | 厚生年金で将来年金増加、出産手当金・傷病手当金あり | 短期的な手取り減少、扶養控除外れる場合あり |
大事なのは、「今」と「将来」を天秤にかけながら自分に合った選択をすること。
そのために、家族のライフプランを紙に書き出して、どの時期にどんな働き方を選ぶか見通しておくことが、最初の一歩になるでしょう。
では次に、その働き方を支える「自分名義の資産形成」について考えてみましょう。
資産形成の早期スタート:iDeCo・NISAなどを活用し、自分名義の資産を積み立てる
今の30代40代女性にとって、「自分名義で資産を持つこと」はこれまで以上に重要になっています。
遺族厚生年金が将来的に有期化される中で、配偶者の収入や年金に頼るだけでは不安が残るからです。
注目すべきは、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入年齢が70歳未満に引き上げられたこと。
これなら、育児や介護で仕事を一時中断しても、その後に再スタートが可能になります。
拠出限度額も拡大される予定で、「もっと積み立てたいのに上限が低い」と感じていた人にも朗報です。
また、つみたてNISAも欠かせません。
非課税で投資できる期間が大きく延び、20年以上の長期にわたって積み立てられます。
毎月1万円をコツコツ積み立てるだけで、10年、20年後には頼もしい金額になっているかもしれません。
「少額でも意味があるの?」という質問をよくいただきます。
答えは「もちろん意味がある」です。
たとえ月5,000円でも20年積み立てれば100万円を超えますし、投資なら複利の力でさらに増える可能性があります。
資産形成で大事なのは金額の大きさではなく、「早く始めること」と「無理なく続けること」。
そして、その資産が自分名義で守られるという点も大きな安心材料です。
資産形成のスタート比較
| 制度 | 加入年齢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 70歳未満まで拡大 | 掛金が所得控除対象、老後資金を作れる | 原則60歳まで引き出せない |
| つみたてNISA | 制限なし | 運用益が非課税、20年以上の長期運用 | 元本割れのリスクあり |
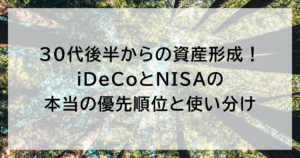
次は、この「積み立て」だけではカバーできないリスクへの備えを考えてみましょう。
リスクへの備えを強化:遺族年金の見直しに備え、保険や働き方でセーフティネットを確保
2028年以降、遺族厚生年金は原則5年間の有期支給に統一される予定です。
つまり、「夫にもしものことがあったとしても、その後も年金で一生暮らせる」という前提が大きく揺らぎます。
具体的には、生命保険や収入保障保険の活用が一案です。
これがあれば、遺族厚生年金の空白期間を補うことができるのです。
また、働き方自体をリスク対策に変えることもできます。
扶養にとどまらず、自ら社会保険に加入することで、厚生年金や健康保険の保障を得る。
これは「保険に加入するのと同じくらいの安心感」をもたらします。
出産手当金や傷病手当金といった制度は、特に働く女性のライフイベントを強力に支えてくれます。
もちろん、保険料や社会保険料が家計の負担になるのでは?という不安は自然です。
けれど、それを「目先の支出」ではなく「将来の安心への投資」と考えられるかがポイントです。
短期的な負担はあっても、病気や事故といったリスクを大幅に減らせるのですから。
最後に
まとめると、30代40代女性が今からできるアクションは3つ。
- ライフプランを整理して、扶養内か社会保険加入かを選ぶ
- iDeCoやNISAで資産形成を早めにスタートする
- 保険や働き方を通じてリスクに備える
この3つを押さえておけば、制度改正による変化を「不安」ではなく「チャンス」として活かせるはずです。
未来を少しでも安心に変えるために、今日から小さな一歩を踏み出してみませんか。
まとめ
正直に言うと、2025年の年金制度改正は、これまで当たり前に語られてきた「106万円の壁」の意味をガラリと変えてしまいました。
以前は「年収を106万円以内に抑えれば大丈夫」と言われてきましたよね。
でも、最低賃金が上がり続ける今、週に20時間働けば自然と106万円を超えてしまう状況になっています。
つまり、これからは「収入をどう抑えるか」ではなく、「働く時間をどう調整するか」が現実的な課題になってきたのです。
では、私たちはどんな選択をすればいいのでしょうか。
大事なのは「目の前の手取り」と「将来の安心」をどうバランスさせるかです。
確かに社会保険に加入すれば、短期的には手取りが減ります。
これは、長い人生を見据えた時に「安心を先取りする」ようなものです。
「じゃあ、もう扶養内で働くのは損なの?」と不安に感じる方もいると思います。
答えは「そんなことはない」です。
子育てや家庭を優先したい時期には、週20時間未満で扶養内にとどまる働き方も十分に合理的です。
ただ、その場合は「いつから社会保険に加入するのか」「どのタイミングでキャリアを広げるのか」といった「次の一歩」をあらかじめ考えておくことが大切です。
逆に「子どもも成長したし、そろそろ収入を増やしたい」「老後に備えて厚生年金を上乗せしたい」と思う時期が来たら、思い切って壁を超える選択がメリットにつながります。
そしてもうひとつ忘れてはいけないのが、資産形成です。
遺族厚生年金が将来的に有期化されることを考えると、公的年金だけに頼るのは心許ない時代がやってきます。
だからこそ、iDeCoやつみたてNISAを使って「自分名義の資産」を少しずつ積み立てておくことが安心につながります。
月5,000円からでも始められますし、複利の力を味方にすれば10年後、20年後に大きな差となって返ってきます。
まとめると、今回の改正は「不安の種」ではなく「働き方とお金の備えを見直すチャンス」です。
短期的に見れば手取りは減るかもしれません。
でも長い目で見れば、保障や年金、そして自分の資産という形で、安心が積み重なっていきます。
未来の安心は、誰かが用意してくれるものではありません。
自分でつくり上げるものです。
今日からできる小さな一歩――勤務時間、収入、資産形成、この3つを自分のライフプランに照らして整理すること。
それが、この制度改正を「味方」に変える、何よりの準備になるはずです。
- 「年収の壁」から「勤務時間の壁」へ。短期的な手取りと長期的な保障をどう選ぶかが鍵
- iDeCoやつみたてNISAで「自分名義」の資産形成を早めにスタートすることが安心につながる
- 遺族厚生年金の有期化に備え、保険や働き方の見直しでリスクへの備えを強化する
働き方とお金を見直すためのセルフチェックリスト
勤務時間とキャリアの選択肢を整理する
- 今の勤務時間は「週20時間未満」か「20時間以上」かを確認した
- 年収は「130万円未満」か「130万円以上」かを把握している
- 今は「扶養内の安心」を優先したいか、「将来のキャリアと収入」を優先したいかを考えた
- 子どもの成長や介護など、ライフイベントに合わせて働き方を変える時期をイメージできる
自分名義の資産形成を始める
- iDeCoやつみたてNISAの制度を調べたことがある
- 毎月いくらなら「無理なく積み立てられるか」を決めている(例:5,000円/1万円)
- 銀行預金だけでなく「投資信託」など長期で育つ資産も持っている
- 「配偶者に万一があっても、自分の資産がある」という安心を持ちたいと感じている
リスクへの備えを強化する
- 夫や自分にもしものことがあった場合、家計をどれくらい維持できるか試算したことがある
- 遺族厚生年金が「5年間で終わる」制度に変わることを知っている
- 生命保険や収入保障保険の見直しをしている(あるいは加入を検討している)
- 出産手当金や傷病手当金など「社会保険から受けられる給付」について把握している
セルフチェックリストの活用の仕方
- まずは「✓」をつけるだけでOK。空欄が多いところが、あなたの「備えどころ」です。
- 家族と一緒にこのチェックリストを眺めながら「今どんな選択をしている?」「次にどんな準備をする?」と話し合うのもおすすめです。
- 年に一度、誕生日や新年など区切りのタイミングで見直すと、自分の変化や進歩がわかりやすくなります。