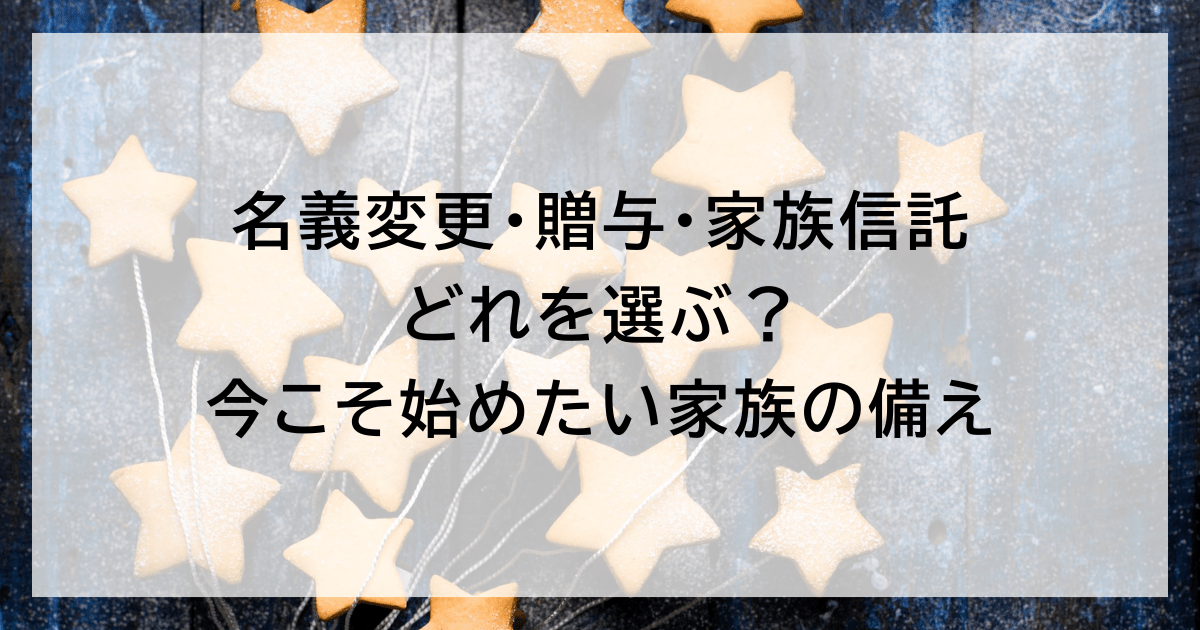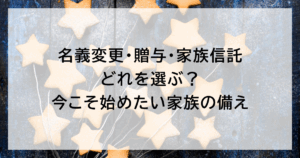「親はまだ元気だし、うちは財産もそんなにないから大丈夫」
そう思って、つい先送りにしてしまう制度や手続きの話。
でも将来の安心って、実は「今」の準備から始まります。
家族の想いをすれ違わせないために。
いざという時に慌てないために。
「まだ先のこと」と思えるうちこそ、話しやすく、選べる制度も多いんです。
この記事では、制度の準備を始めるきっかけや、第一歩の踏み出し方をお伝えします。
- 親が高齢になってきたが、実家や財産の名義がそのままで不安な方
- 相続のときにもめたくないが、何から手をつければいいかわからない方
- 贈与や名義変更、家族信託などの言葉は聞くけど、違いがピンとこない方
- 課税されるタイミングや手続きが複雑そうで後回しにしている方
名義変更・贈与・家族信託 ──3つの制度の違いをざっくり解説
「この家、いずれは私が受け継ぐことになるのかな」
「でも、名義っていつ変えたらいいんだろう? 贈与になるって聞いたけど、そうなの?」
「それに最近よく聞く「家族信託」って……正直ちょっと難しそう」
親の家やお金のことが話題になると、こんなふうにモヤモヤと疑問が浮かんでくることってありますよね。
私も数年前、母と老後の話をしたとき「家の名義、どうしようかしら」とぽつりと言われ、頭の中が「???」でいっぱいになりました。
よく出てくる言葉に「名義変更」「贈与」「家族信託」の3つがあります。
なんとなく聞いたことはあっても、それぞれ何がどう違って、どんな場面で使えばいいのか……
いざ調べると混乱するのも無理はありません。
ここでは、この3つの制度についてざっくりと、でも大事なポイントはしっかりおさえてご紹介します。
「専門用語が多そう」と身構えなくても大丈夫。
日常にたとえながら、イメージしやすく整理していきましょう。
名義変更=登記の「名前」を入れ替える作業
まず「名義変更」とは、たとえば実家の家の登記簿に書かれた「持ち主の名前」を、親から子へと書き換えることを指します。
あくまで法律上の「名義(=所有者)」を変える手続きで、見た目には何も変わりません。
でもその裏には、いろんな「理由」がついてまわるんです。
たとえば「無償で名義を変えた」場合、それは「贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
一方「ちゃんと売買契約を結んで、お金を支払った」という場合は、売買として認識されます。
つまり、ただ名前を変えるだけでも「なぜそうしたのか」がとても大事になるんです。
税務署は「この名義変更、タダで渡してない?」としっかりチェックしてきます。
言ってみれば、名義変更は「氷山の一角」。
水面下には、税金や契約などのさまざまな事情が潜んでいるんです。
贈与=財産を「プレゼント」する制度
次に「贈与」。
これは一言でいえば「プレゼント」です。
たとえば「毎年、子どもに110万円までなら非課税で贈れる」といった話を聞いたことがあるかもしれません。
現金だけでなく、家や土地といった不動産も贈与の対象になります。
ただしこの「プレゼント」、うっかりやると高くつくことも。
たとえば2,000万円の家を贈った場合、贈与税が数百万円かかることもあるんです。
「えっ、そんなに!?」と思いますよね。
でも、それくらい贈与税は高額になる可能性があるので、注意が必要です。
さらに、贈与は「渡す人」「受け取る人」両方の合意があって初めて成立します。
感覚的には「あげたつもり」でも、ちゃんとした契約書がなかったり、名義変更をしていなかったりすると、「それ、贈与と認めません」と言われるケースも……。
プレゼントひとつ取っても、実は「ちゃんとしたダンドリ」が必要なんですね。
家族信託=「未来の安心」を託す仕組み
最近よく耳にするようになった「家族信託」。
これは親が元気なうちに、「将来、自分の財産をどう管理するか」を決めておき、信頼できる家族にその管理を「託す」制度です。
たとえば、親が認知症になってしまうと、もう自分で不動産を売ったり、預金を引き出したりすることができません。
そんなときのために、事前に「この家の管理は、息子に任せます」と契約しておけば、スムーズに対応できるというわけです。
私の友人は、お母さまが元気なうちにこの制度を使って、実家の土地の管理を任されることになりました。
最初は「信託って何それ?」と戸惑っていましたが、将来の介護や相続に備えておくには本当に安心だと感じたそうです。
ただし、家族信託は手続きが少し複雑。
信託契約書を作って、公証役場で認証し、不動産の登記をし直す必要もあります。
そのため司法書士や弁護士など、専門家の力を借りるのが一般的です。
費用はかかりますが、そのぶん、将来の混乱を防げると思えば「安心の投資」とも言えるかもしれません。
3つの制度をざっくりイメージすると…
最後に、それぞれの制度を日常の感覚でたとえてみましょう。
- 名義変更:家の表札を「田中」から「山田」に変えること
- 贈与:ちょっと高級なプレゼントを「どうぞ」と手渡すこと
- 家族信託:信頼できる人に「財布と鍵」を預けて、必要なときに代わりに動いてもらうこと
こうして比べてみると、それぞれの特徴がなんとなくつかめてきませんか?
次は、これら3つの制度が「どんなときに、どれを使うべきか?」という、より実践的な話に入っていきます。
いま迷っている方も、きっとヒントが見つかるはずです。
ケース別:どの制度を使うと良い? 判断の目安と注意点
人生の節目に「そろそろ親のこと、ちゃんと考えなきゃ」と思ったとき、最初にぶつかるのが「制度の選び方」。
名義変更? 贈与? それとも家族信託? 調べれば調べるほど、どれが正解なのか迷ってしまいますよね。
結論から言えば、どの制度が「一番いいか」は家庭ごとの事情で変わります。
でもポイントは、「何を目的にするか」と「どんなことが心配なのか」を明確にしておくこと。
それさえ分かっていれば、必要な制度は自然と絞れてきます。
ここでは、実際によくある3つのケースに分けて、「その時どの制度が合っているのか」「気をつけたいことは何か」を具体的に見ていきましょう。
実家を将来売却・相続させたい場合は?
「親が住んでいた実家、このまま空き家になったらどうしよう?」
そう考え始めたら、名義や登記のことは避けて通れません。
実際、私の友人も「売りたいのに名義が亡くなったお父さんのままで、手続きがストップしてしまった」と困っていました。
不動産の名義が親のまま残っていると、売ることも貸すこともできません。
たとえ「うちは兄が継ぐつもり」と思っていても、登記がそのままではローンの申請やリフォーム工事も進みませんし、税金の負担が大きくなることも。
そこで選択肢に上がるのが「生前に名義を変更する」「贈与する」「遺言を準備しておく」といった方法です。
ただし、名義を変えるだけでも費用がかかるうえ、税金の扱いが厄介になるケースも。
無償であれば「贈与」とみなされ贈与税が発生しますし、売買とみなされれば契約書が必要になります。
そして最近では、相続登記が義務化され、「あとでやればいい」が通用しなくなってきました。
放置しておくと、罰金(過料)を科される可能性も。
これは国としても空き家問題の対策を強化している背景があるからです。
実家に思い入れがある方は特に、名義の整理とともに「どう引き継ぎたいか」も感情面を含めて家族で話しておきましょう。
では次に、親の判断力が落ちてきたとき、どんな制度が安心につながるかを見ていきますね。
高齢の親が認知症になったら…事前に備えるべき制度は?
「最近、母が同じ話を何度も繰り返すようになってきたの…」
こんな風に、親の変化に気づいたときほど心細いものはありません。
でも、だからこそ早めの準備が大事なんです。
その選択肢のひとつが「家族信託」。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、実は今、認知症対策として注目されている制度です。
これは、親が元気なうちに「この財産はあなたに任せる」と子どもに管理を託す仕組み。
たとえば、親の自宅を将来売却することも視野に入れ、長男に信託契約で任せておく——そんなことができます。
もし何も準備せずに親が認知症を発症してしまうと、不動産を売るにも、預金を引き出すにも「本人の判断」が必要になります。
そうなると、成年後見制度しか手段がなくなりますが、これは裁判所の監督下に置かれ、使い道に制限がかかってしまいます。
一方、家族信託であれば親の希望に沿った財産の管理が可能。
費用は司法書士や弁護士に依頼すれば10万円前後かかることが多いですが、それで将来の手間やトラブルを減らせるなら、かなり心強い手段になりますよね。
ただし、信託を「誰に託すか」は慎重に。
兄弟間で感情がもつれる原因にもなりかねません。
「うちは妹と一緒に話し合って決めたよ」といった家族も多く、事前の対話がとても大切です。
次は、「生きているうちに財産を少しでも渡しておきたい」と考えている方に向けて、生前贈与の注意点を詳しくお伝えします。
生前贈与でお金を渡したい場合の落とし穴とは?
「孫の教育費に少しでも役立ててほしくて、毎年100万円ずつ渡してるの」
そう話すおばあちゃんの目はとても優しくて、なんだか温かい気持ちになりますよね。
でも、その善意の裏に「落とし穴」が潜んでいることもあるのです。
よく知られている「年間110万円までは非課税」という制度。
たしかに便利ですが、これ、実は「毎年コツコツ」続けると「定期贈与」と見なされ、後でまとめて課税されることがあるんです。
「え、今さらそんなこと言われても…」という事例、実際にあります。
もうひとつ、「相続時精算課税制度」は、贈与時に税金はかかりませんが、将来の相続でその分が差し引かれる仕組み。
結果的にトータルでの節税にはならないこともあるので、「税金ゼロだから安心♪」とは言い切れないのが現実です。
さらに注意したいのが「名義預金」。
親が子ども名義の通帳を作り、「このお金はあなたのよ」と言いながら実際は親が管理している——
この場合、贈与が成立していないとされ、相続時に「それ、相続財産です」とカウントされることに。
だからこそ、「いつ・いくら・誰に渡したか」を明確に記録しておくことが大切。
贈与契約書を作ったり、通帳を実際に渡したり、「形に残す」ことがカギになります。
不安がある場合は、税理士さんやファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
たとえば住宅資金の一括贈与には特例がありますが、申告を忘れると台無しになるケースも……。
「せっかく準備したのに、あとで揉めるなんて悲しい」。
そうならないためにも、今のうちに正しい知識を持っておくことが、自分たちを守る第一歩です。
次は、こうした制度を使う前に「家族で何を確認しておくべきか?」という、とても大事なステップについてお伝えしていきますね。
制度を選ぶ前に整理しておきたい3つのこと
- 親の意思・家族の関係性をどう確認するか
- 財産の中身と名義を把握する方法
- 相談できる専門家と費用の目安
「親の家の名義、どうしようか?」
そんな話がふと出たとき、「贈与にする? 信託がいい?」と、つい制度の話から入ってしまいがち。
でもちょっと待ってください。
いちばん最初に立ち止まって考えてほしいのは、「なぜやるのか」「誰のためにやるのか」「その準備は整っているのか」という、もっと根っこの部分なんです。
たとえば以前、私の友人が実家の名義変更を急いで進めたところ、親御さんとの関係が一時ギクシャクしてしまったことがありました。
「親のため」と思っていたのに、「勝手に決められて悲しかった」と言われたそうです。
そんなすれ違い、できれば避けたいですよね。
ここでは、制度を選ぶ前に確認しておきたい3つの大切なことを、実体験や失敗しがちなポイントを交えながら、一緒に見ていきましょう。
親の意思・家族の関係性をどう確認するか
一番の出発点は、やっぱり「親がどうしたいか」。
これは制度の選択以前の大前提です。
「子どもに迷惑をかけたくない」「でも、まだ自分で決めたい」など、親の考えは人それぞれ。
話し合わないまま進めてしまうと、たとえ制度が良くても、結果的に関係が悪化してしまうこともあります。
でも、「家の名義、どう思ってる?」なんて、唐突には聞きづらいですよね。
そんなときは、テレビのニュースやドラマ、近所の話題をきっかけにしてみてください。
たとえば、「◯◯さんの家、相続のことで揉めたらしいよ。うちも何か準備したほうがいいのかなあ?」なんて軽く振ってみると、自然に話が入りやすくなります。
また、兄弟姉妹がいる場合は、親と話す前にきょうだい間で「誰が何を考えているのか」共有しておくことも大切です。
「自分は聞いてなかった」「勝手に決められた」となれば、制度以前に信頼関係が崩れてしまいます。
家族間の連携こそが、制度を正しく使うための土台になります。
財産の中身と名義を把握する方法
制度を選ぶうえで欠かせないのが、「親の財産がどこにどれだけあるか」「その名義は誰のものか」を把握しておくこと。
これが意外と抜け落ちがちです。
とはいえ、いきなり「全部見せて」とはなかなか言いづらいですよね。
おすすめは、「いざというときに困らないように、場所だけでも教えてもらえる?」といった聞き方。
たとえば通帳や権利証、保険の証書など、生活に身近なものから少しずつ情報を集めてみましょう。
次のようなリストを作ると、整理がしやすくなります。
- 預貯金(銀行名・支店・口座の種類)
- 不動産(住所・名義人・権利証の保管場所)
- 生命保険や年金(契約者・受取人・証書)
- 有価証券(株や投資信託の証券会社名・名義)
以前、親の通帳が何冊も出てきて「どれが使われているのか全然わからない…」と困ったという声を聞きました。
こうした棚卸しは、制度選びだけでなく、緊急時の備えとしても有効です。
「意外といろいろ持ってるな」と親が自覚するきっかけにもなりますよ。
相談できる専門家と費用の目安
そして最後に、「制度を使いたいけれど、誰に聞けばいいかわからない」という方のために、専門家の役割と費用の目安についてもお伝えします。
- 司法書士:不動産の名義変更、家族信託の設計など
- 税理士:贈与税・相続税の試算や申告の相談
- 行政書士・弁護士:契約書の作成やトラブル防止のアドバイス
それぞれ得意分野が違うため、最初から完璧に使い分けるのは難しいもの。
そんなときは、市役所の市民相談窓口や、各士業団体が行っている無料相談を活用してみてください。
実際に話してみると「なるほど、こういう人に頼めばいいのか」と見えてくることも多いです。
費用の目安としては──
- 不動産の名義変更:5万〜10万円ほど(司法書士報酬+税金)
- 家族信託契約書の作成:20万〜50万円(内容により変動)
- 贈与税の申告(税理士):5万〜10万円程度
最初は「ちょっと高いかも…」と感じるかもしれません。
でも、「あとからトラブルになって何十万円も余計にかかった」なんて話を聞くと、やっぱり最初にしっかり相談しておく大切さを実感します。
制度を選ぶことは、単に書類を整える作業ではありません。
「親の想いをどう受け取り、家族としてどう寄り添っていくか」を考える機会でもあります。
まとめ:制度は「いつか」じゃなく「今」から考えていい
「まだ元気だし」「うちは大丈夫」——その思い込みが、思わぬすれ違いやトラブルのきっかけになることも。
「いつか」じゃなく「今」だからこそできることがあります。
まずは、家族で少しだけ未来の話をしてみませんか?
それがきっと、大きな安心へとつながっていきます。
「親はまだ元気だし、急ぐ理由もないよね」
「うちは大した財産もないから、何か手続きが必要になるようなこともないと思う」
そう思って、制度のことをつい後回しにしていませんか?
私自身も、以前はそうでした。
実家に帰省したときに「まだまだ元気だね〜」と笑い合い、心のどこかで「このまましばらく大丈夫」と勝手に思い込んでいたんです。
でもある日、親が体調を崩して入院したことをきっかけに、「あれ、名義ってどうなってたっけ?」「預金って、誰が管理してるの?」と慌ててしまって…。
まさに、「まだ大丈夫」と思っていたその安心感が、逆に動けなくなる原因になってしまったんですね。
制度をうまく活用できるかどうかは、「いつ話し始めたか」で結果が大きく変わります。
たとえば、認知症などで親が意思をはっきり伝えられなくなると、不動産の名義変更や生前贈与は事実上できなくなってしまうこともあります。
病気やケガで急に判断力が落ちるというのは、誰にとっても他人事ではありません。
高齢化が進む今の社会では、「元気なうちに動く」というのが、実は最も現実的な選択なんです。
でも、いきなり制度を選んだり、専門的な書類を揃えたりしなくても大丈夫。
まずできることは、家族で少しだけ話してみることです。
「これから先、どうしたいと思ってる?」「何が不安?」といった、ほんの短い会話からでも十分なんです。
制度の話って、つい重く感じてしまいがちですよね。
だからこそ、晩ごはんのあとやテレビを見ながらのふとした時間に、日常の延長として話題にするくらいの気持ちでいいんです。
話すたびに、少しずつ気持ちをすり合わせていけば、いざという時の安心感がまったく違ってきます。
次にやっておきたいのが、財産や名義の棚卸し。
不動産、預貯金、保険、証券、車など…いろいろあるようで、いざ確認すると「これって誰の名義?」「どこに契約書があるの?」とわからないことも多いんですよね。
私は実家の引き出しから、20年前の古い通帳や知らない保険の証書が出てきたことがあって、ちょっとした探偵気分になりました。
でも、そのおかげで「これはもう解約していいね」「この名義は変えておこう」と話が具体的に進んだんです。
思っている以上に、家族の「情報の共有」って大事なんだなと実感しました。
そして最後にお伝えしたいのが、「制度はじっくり、でも現実的に比べていこう」ということ。
名義変更、贈与、信託…といった制度は、それぞれにメリットもあれば、注意点もあります。
たとえば贈与なら、税金がかかるケースもありますし、信託は専門家のサポートが必要なこともあります。
どの制度が絶対に正解ということはなくて、「自分たちに合っているか」が一番大事なポイントです。
焦らず、でも目をそらさずに、「うちはどうするのが一番いいんだろう?」と考える姿勢を持っていただけたらと思います。
信頼できる専門家に相談するのも、一歩を踏み出す手助けになりますよ。
最近では、終活や相続の準備を前向きに捉える方も増えてきました。
「縁起でもない話」ではなく、「これからの暮らしを守る準備」として制度を考えてみる。
それは、未来の自分と家族への思いやりそのものです。
もし、数年後に何かあったとき、「あのとき話しておいてよかったね」と言い合える時間を、今から少しずつ重ねていきませんか?
制度のことを知る。
その小さな一歩が、家族の未来に安心を灯す大きな一歩になるはずです。