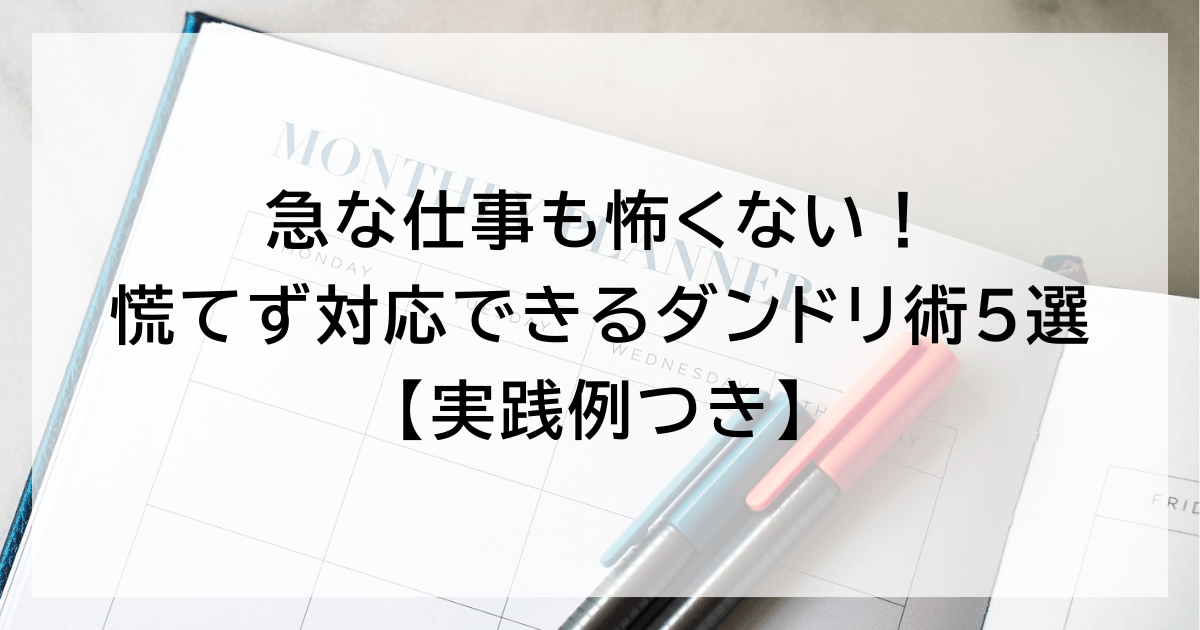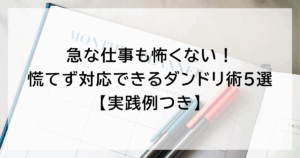「え、今から?」
急な仕事の依頼に、思わず固まってしまった経験はありませんか。
計画的に進めているはずなのに、予定が一瞬で崩れてしまう…。
私も何度もそのストレスに押しつぶされそうになりました。
でも、日常にちょっとしたダンドリ術を取り入れるだけで、不思議なほど落ち着いて対応できるようになるんです。
今回は、今日から実践できる「慌てないための5つの工夫」をご紹介します。
- 業務負担が多く、急な依頼にストレスを感じやすい方
急な依頼に慌ててしまう原因を知る
ある日の午後、デスクに置いたコーヒーがまだ半分も減っていないうちに、上司が軽やかな足取りで近づいてきました。
「今日中にこれ、お願いできる?」
その瞬間、心の中で思わず「え…今ですか!?」と小さく悲鳴。
そんな経験、ありませんか?
私も以前は、急な依頼が来るたびに胸がドキッとして、呼吸が浅くなり、頭の中は「どうしよう」の渋滞でした。
実はこの「慌てる」感情、ほとんどの場合に共通する原因があるんです。
それは――
全体像が見えていないことと優先順位の組み替えが苦手なこと。
なぜ全体像が見えないと慌てるのか
急に頼まれたとき、多くの人は「できるか・できないか」を即答しようとしてしまいます。
だから、頭の中で不安が勝手に膨らみ、「とにかく何か動かないと…」という焦りが生まれます。
たとえば、会議5分前に「この資料、今日中に修正しておいて」と言われたとしましょう。
詳細を聞かずに「はい」と受けた結果、修正内容が想像よりも複雑で、他の予定がすべて後回しに…。
気づけば夜中までパソコンの前、なんてことも。
これはちょうど、地図を持たずに見知らぬ街を歩き回るようなもの。
優先順位をつけられないと、全部が中途半端に
特に管理職やリーダー職だと、すでに予定がびっしりのスケジュールに、突発案件が割り込むのは日常茶飯事です。
そのときに「何を後回しにするか」「誰に任せるか」を決められないと、結果としてすべての仕事が中途半端になります。
これは、夕飯を作っている最中に急な来客があり、掃除とお茶の用意と料理の仕上げを全部同時にやろうとして、結局どれも微妙な仕上がりになる感じに似ています。
慌てやすい自分を知るチェックリスト
まずは、自分がどの段階で慌てるのかを知ることから始めましょう。
以下の質問にYES/NOで答えてみてください。
- 依頼されたら、必ず期限を確認している
- 依頼の背景や目的を聞いている
- 今抱えている全タスクの期限を把握している
- 急な仕事が入っても、優先順位をすぐに組み替えられる
- 手が回らないとき、頼れる人をすぐ思い浮かべられる
実際によくある失敗例
Aさん(38歳・管理職)は、午前中に部下の面談3件と資料作成の予定が詰まっていた日に、別部署の上司から「午後の会議用に、このデータをまとめてほしい」と依頼されました。
詳細を確認せずに「はい」と答えた結果、会議開始30分前になって「データ形式が違う」と指摘され、慌てて修正。
そのせいで、本来の資料作成は夜中までかかってしまいました。
こうした失敗は珍しくありません。
原因は、最初に依頼内容を正確に聞き取らなかったことと、優先順位を見直さなかったこと。
この2つを改善するだけで、同じ失敗はかなり減らせます。
原因がわかれば、解決の糸口はもう見えています。
では、どうすれば急な依頼にも落ち着いて対応できるのか――
次では、今日から試せる5つのダンドリ術をお届けします。
急な依頼を受けても落ち着いて対応できる「5つのダンドリ術」
正直、急な仕事って…あれ、心臓に悪いですよね。
私も以前、午後からのんびり作業を進めようと思っていた矢先に、上司から「これ、急ぎで!」と声をかけられ、頭の中が真っ白になったことがあります。
このとき痛感したのは、「心構え」だけじゃ全然足りないということ。
今回は、私が何度も修羅場をくぐる中で身につけた、今日からできる5つのダンドリ術をご紹介します。
まずは依頼内容を正確に聞き出す
これはもう、断言できます。
急な依頼の成功は、最初の聞き取りで8割決まります。
ここをあいまいにすると、後から「え、そういうことじゃなかったの⁉」という悲劇が待っています。
たとえば、上司に「この資料、急ぎで仕上げて」と言われたとします。
さらに、その資料が「社外プレゼン用」なのか「社内回覧用」なのかによって、必要な見栄えや情報量も大きく変わります。
だからこそ、最初に聞くべきはこのあたりです。
- 期限はいつですか?
- どんな場面で使いますか?
- 完成形はどの形式ですか?(Excel、PDFなど)
- 参考にできる資料やデータはありますか?
すると、依頼者の頭の中も整理され、情報が自然と引き出されます。
そしてもうひとつ大事なのは、「曖昧な表現を放置しない」こと。
もし「とりあえずできる範囲で」と言われたら、「では、〇時までにこの部分を完成でよいですか?」と、こちらから具体的に提案して確認しましょう。
既存の予定を俯瞰して優先順位を整理する
依頼内容がクリアになったら、次は自分のスケジュール全体を見渡す番です。
感覚で「たぶんできる」なんて判断すると、後から予定が雪崩のように崩れることも。
だからこそ、事実ベースで優先順位を入れ替える必要があります。
私はよく、タスク管理アプリ「Trello」や「Todoist」を使っていますが、正直、紙に全部書き出すだけでも十分効果的です。
ポイントは、期限と所要時間をすべて見える化すること。
たとえば「今日中に送って」と言われたメールが、単なる情報共有なら、もっと成果に直結する業務を優先すべきかもしれません。
判断の目安はシンプルです。
- 期限が迫っているか
- 成果に直結するか
この2つで整理すれば、「今やるべきこと」と「後回しでもいいこと」がはっきりします。
もしこの時点で「ほかの業務が遅れそう」とわかったら、迷わず依頼者や上司に早めに共有しましょう。
私もこれをサボって何度か怒られましたが…正直、先に言っておいた方が百倍楽です。
必要なリソースを早めに確保する
正直に言えば、急な依頼ほど「リソースの確保」が勝負どころです。
私も以前、「明日までに顧客向けの提案資料を作って」と急に頼まれたことがありました。
しかもそのデータは経理部が握っていて、グラフ作成はデザイナーの力が必要。
そのとき痛感したのは、「自分がすぐに動ける作業より、他の人に頼む作業を先に動かすこと」の大切さです。
具体的なリソース確保の動き方
たとえば先述の案件の場合には、
- 社内依頼:
経理部に数値データを依頼、総務に最新の組織図をもらう - 部下や同僚への分担:
「ここの部分だけ先にまとめてもらえる?」と、ピンポイントでお願い - 外部サービス活用:
Canvaでサクッとデザイン作成、Chatworkで外注デザイナーと連絡、クラウドワークスで急ぎのデータ入力を発注
特に責任感の強い女性リーダーは、つい「自分で全部やらなきゃ」と抱え込んでしまいがちです。
でも、それは結果的に自分もチームも疲弊させてしまいます。
むしろ、依頼者から見れば「人をうまく動かせる人」こそ信頼される存在です。
早めに声をかければ、相手にも余裕があるうちに動いてもらえる確率がぐっと上がります。
次は、こうして確保したリソースをどう使えば最短で成果に結びつくのかを見ていきましょう。
作業を細分化して短時間で着手する
急な依頼の一番の敵は、「どこから手をつけたらいいのかわからない…」という心理的な重さです。
頭の中では「やらなきゃ」と分かっているのに、心が動かない。
そんな経験、ありませんか?
たとえば「プレゼン資料を作る」というタスクなら、こんなふうに分けます。
- 資料の目的を整理する
- 必要なデータを集める
- スライド構成を決める
- 1枚目のスライドを作る
これらを1タスク=数分〜30分以内に収まるように設定します。
心理学では、人は動き出すとやる気が高まる「作業興奮」という現象があります。
特におすすめなのは、「依頼を受けてから15分以内に1つ目のタスクに着手する」こと。
最初の一歩が早ければ、その後の流れもスムーズになります。
実践テクニック
- タスクは付箋やアプリに1つずつ書き出す
- 「10分以内に終わること」から着手
- 終わったタスクは線を引いたりカードを動かして「見える化」
細分化して進めると、「急ぎなのに進まない」という焦りが減ります。
そして、動き始めたら次に大切なのは——そう、「進捗の共有」です。
依頼者と進捗をこまめに共有する
これ、正直メンタルにも時間にもダメージ大です…。
たとえば資料を半分作った段階で見せれば、「ここはもっと簡単に」「数字を最新に」など、早い段階で修正できます。
共有のメリット
- 方向性のズレを早期に修正できる
- 相手に安心感を与えられる
- 遅延の可能性も早めに相談できる
方法はメールでもチャットでもOKですが、一番早く確実なのは短い口頭報告です。
SlackやMicrosoft Teamsを使えば、画像やファイルもその場で送れます。
ポイントは、「進捗0%」でも共有すること。
「データ待ちですが、届き次第この順番で進めます」と伝えるだけで、依頼者は「ちゃんと考えてくれている」と感じます。
こまめな共有は信頼を積み重ねるチャンスです。
急な依頼にも疲弊しないための長期的対策
急な依頼って、なぜか立て込んでいる日に限ってやってくるんですよね。
以前の私は、そんなたびに「また今日も予定が崩れる…」とため息をついていました。
短期的な対処だけで乗り切る日々は、まるで常に満員電車に押し込まれているような窮屈さ。
だからこそ、日常の中に「突発案件に強い土台」を作っておくことが、長く走り続けるためには欠かせないと気づきました。
ここでは、私が実際に取り入れて効果を感じた、疲弊しないための習慣や環境づくりをお伝えします。
日常的なタスク管理で「対応の余白」をつくる
突発案件に振り回されやすい人の多くは、もともとのスケジュールがパンパン。
私も昔は「時間が空いたら休めばいいや」と思って詰め込みすぎていました。
けれど、ある日カレンダーの予定を80%に抑えるようにしてから、急な依頼への対応力がぐっと上がったんです。
たとえば、GoogleカレンダーやTrelloで「予備時間」を色分けして可視化する方法。
毎朝5分、コーヒー片手に予定を見直す時間をとるだけで、心の準備ができるのも嬉しいポイントです。
「ゆとり時間」を生活に組み込む
時間が詰まりすぎていると、ちょっとした依頼でも生活全体が乱れてしまいます。
例を挙げると…
- 午後3時〜3時半は必ず予備時間としてブロック
- 会議と会議の間に15分のインターバルを入れる
- 昼休み最後の5分を翌日のタスク整理に充てる
この小さな余白が、急な依頼に対する「バッファ」になります。
特に管理職の方は、自分の余裕がチーム全体の安定にもつながることを意識すると、さらに価値を感じられるはずです。
事前の役割分担で「頼れる環境」をつくる
突発案件は、自分ひとりで抱え込むと一気に疲弊します。
以前、私が所属していたチームでは、誰がどの分野を得意としているかを週1ミーティングで共有していました。
そのおかげで「これなら○○さんが早い」とすぐ判断でき、仕事の振り方がスムーズになったんです。
具体的には…
- 得意分野を共有する定例ミーティング
- 業務マニュアルや引き継ぎ資料の常時更新
- SlackやTeamsに「ヘルプ要請チャンネル」を設置
こうした仕組みがあると、急な案件も「チームで乗り越える」感覚になり、心理的な負担が減ります。
メンタルケアも「仕事のうち」と考える
突発案件が続くと、知らないうちに心身がすり減ります。
だからこそ、メンタルケアは「時間が余ったらやる」ではなく、あらかじめスケジュールに組み込むべきだと感じています。
私のお気に入りは…
- 会議前後に深呼吸を3回
- 1時間ごとに1分だけ立ってストレッチ
- 昼休みに5分だけ外に出て空を見上げる
- 週に2〜3回の軽いウォーキング
ほんの数分の習慣ですが、驚くほど気持ちが軽くなります。
忙しいときこそ、自分を整えることが仕事の質を保つ一番の近道です。
長期的な対策は、単に突発案件に対応するためだけではありません。
日々の仕事をより穏やかに、余裕を持って進められるようになります。
毎朝のタスク見直し、ゆとり時間の確保、役割分担の仕組み化、そして日常的なメンタルケア。
まとめ
どれだけ計画的に仕事を進めても、「急にこれお願い!」という依頼は避けられません。
私自身、数年前までは突発案件が来るたびに心臓がドキッと跳ねて、頭の中が真っ白になっていました。
でも、日常の中でちょっとしたダンドリ術を身につけたことで、「慌てる」から「落ち着いて動ける」へと確実に変われたのです。
大事なのは、いきなり完璧を目指さないこと。
今日からできる「小さな習慣」を少しずつ積み重ねることが、将来の大きな余裕につながります。
急な依頼は「想定外」ではなく「想定内」にしてしまう
突然の案件が舞い込むと、多くの人は「予定が崩れた…」と感じてしまいます。
実際、私も以前はそんなたびにストレスが一気に高まり、「もう今日は無理!」と心の中で叫んでいました。
でも、予定の中に「予備時間」を意識的に入れるだけで、驚くほど気持ちが楽になります。
たとえば、Googleカレンダーで30分の「空白枠」を設定したり、タスク管理アプリのTrelloで「緊急度タグ」をつけておいたり――
どちらも5分で設定できます。
小さな習慣が「大きな余裕」を生む
1日5分のスケジュール見直し、15分のゆとり時間の確保、同僚との役割分担の事前共有。
これらは、一見すると地味な工夫かもしれません。
でも、続けることで確実に変化が出てきます。
私の場合、数週間で「仕事が押しがち」だった日々が減り、2か月後には「急ぎ案件もなんとかなる」という自信に変わりました。
イメージとしては、毎日少しずつ貯金していたら、気づけば安心の生活防衛資金ができていたような感覚です。
心身のケアは「贅沢」ではなく「必須」
「忙しいから休む暇なんてない」
昔の私もそう思っていました。
けれど、そんな働き方は長続きしません。
むしろ、パフォーマンスが落ちてしまいます。
昼休みに5分だけオフィスの外を散歩したり、デスクで軽く肩を回したり。
それだけでも午後の集中力が全然違います。
特に女性は、ホルモンバランスや体調の波が気分や集中力に影響しやすいからこそ、自分の体調を守ることを後回しにしないでほしい。
これは贅沢ではなく、長く働き続けるためのメンテナンスです。
今日からの第一歩は「たった10分」でもOK
「そんな余裕ないよ…」と思ったら、まずは小さく始めましょう。
たとえば今日の午後、会議と会議の間に10分だけ予備時間をつくる。
それだけでも十分です。
階段を一段ずつ上るように、ダンドリの力を広げていけます。
最後に
突発的な仕事は、キャリアを重ねるほど増えていきます。
でも、そのたびに疲れ果てる働き方では、自分の時間も心の余裕も削られてしまいます。
今回紹介したダンドリ術を一つずつ試してみてください。
きっと「急な依頼=嫌なもの」から、「急な依頼=冷静に対応できる私を試すチャンス」へと、見方が変わるはずです。
そして次は、このダンドリ術をチーム全体に広げていきましょう。
個人対応とチーム対応の比較
| 項目 | 個人で対応 | チームで対応 |
|---|---|---|
| 即効性 | 高い(自分の工夫ですぐ可能) | 中程度(仕組み化に時間がかかる) |
| 持続力 | 中程度(本人の努力次第) | 高い(役割分担で安定) |
| メリット | 手軽、即実行できる | 負担分散、属人化を防げる |
| デメリット | 限界がある | 会議や調整が必要 |