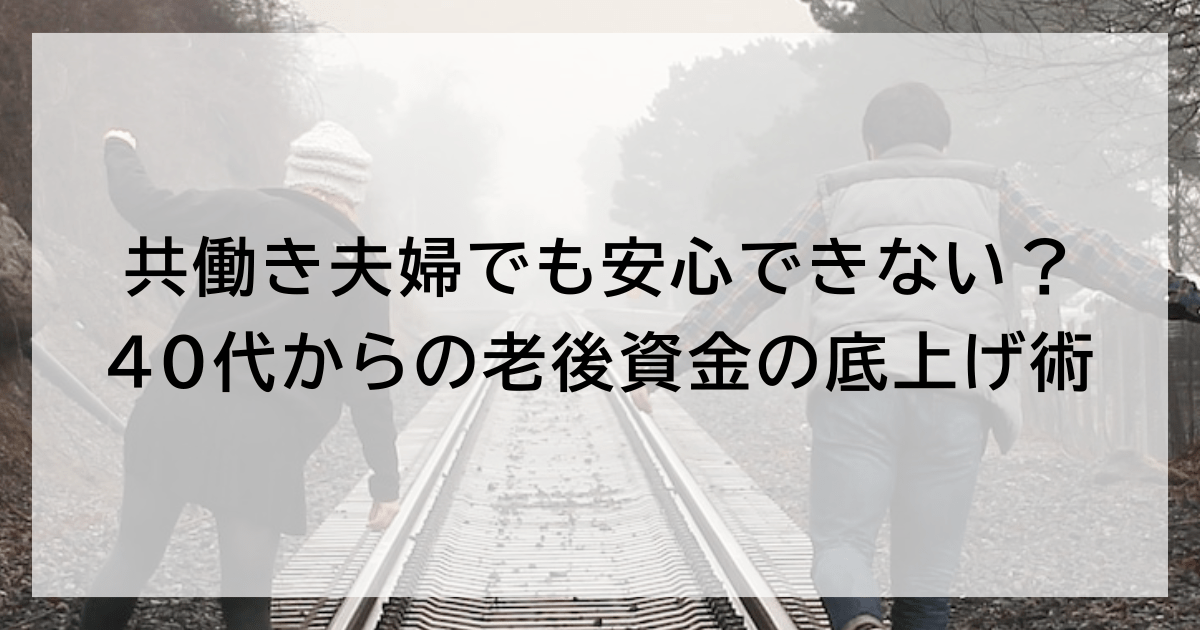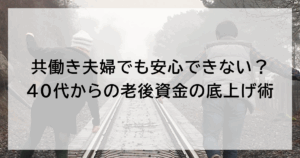「夫婦共働きだから、老後資金は大丈夫だろう」
そんな安心感を持っていませんか?
実は、共働き世帯でも老後資金が不足するケースは少なくありません。
年金だけでは毎月数万円の赤字になる家庭も多く、その差は20年で1,000万円を超えることもあるのです。
特に40代は、子どもの教育費や住宅ローン、親の介護などの支出が重なる時期。
日々の生活に追われ、自分たちの老後資金を「後で考えればいい」と先送りにしがちです。
しかし、このタイミングで一歩踏み出すかどうかが、将来の安心感を大きく左右します。
幸いなことに、40代はまだ老後資金づくりに間に合う世代。
大切なのは「大きく頑張る」ことではなく、小さな工夫を習慣化し、時間を味方につけることです。
本記事では、共働き夫婦が油断せずに老後資金を底上げするための実践術を、分かりやすく解説していきます。
- 共働きでも老後資金は不足する可能性が高い。40代からの底上げがカギ。
- 副収入・家計管理・自動化を組み合わせれば、無理なく資産形成できる。
- 数字だけでなく「夢や楽しみ」を目標にすると、モチベーションが続く。
40代からの老後資金に潜む「見えない落とし穴」
「うちは共働きだし、なんとかなるでしょ」
私自身も40歳を過ぎた頃、心のどこかでそう思っていました。
けれど、現実は甘くありません。
教育費、住宅ローン、親の介護費用…。
いくつもの大きな出費が重なったとき、貯めてきたつもりのお金がみるみるうちに減っていくのです。
まるで水道の蛇口からポタポタ漏れていたのに気づかず、気がついたらバケツが空になっていた、そんな感覚に近いかもしれません。
今の暮らしをやりくりできているからといって、その延長線上に老後の安心があるとは限らないのが現実です。
特に女性は、ライフイベントや親の介護といった「想定外」を背負う場面が多く、「気づいたら計画が崩れていた」というケースが少なくないのです。
ここでは、40代夫婦が直面しやすい代表的な3つの落とし穴を、一つずつ見ていきましょう。
教育費ピークと老後資金準備が重なる現実
40代といえば、多くの家庭で子どもの教育費がピークを迎える時期です。
大学進学ともなれば、学費や仕送りで年間100万円以上かかることも珍しくありません。
私の友人も「毎月の仕送りと学費でボーナスが消えていく」と嘆いていました。
一方で、50代は本来なら「老後資金を貯める最後のゴールデンタイム」のはず。
でも教育費が重なることで、老後資金がどうしても後回しになってしまうご家庭が多いのです。
もちろん、子どもに投資したいという親心は自然なものです。
でも、そのせいで自分たちの老後資金を削りすぎると、将来は逆に子どもへ経済的な負担をかけてしまうリスクがあります。
教育費と老後資金、この二つのバランスをどう取るかが40代からの大きな課題です。
住宅ローンとリフォーム費用のダブル負担
次に立ちはだかるのが、住宅関連の出費です。
40代で住宅ローンが残っている場合、退職までに完済できないケースも少なくありません。
「定年までに終わる予定だから大丈夫」と思っていても、繰上返済できなかったり、予想外に収入が減ったりすれば、家計はすぐに苦しくなります。
さらに意外と見落とされがちなのがリフォーム費用。
たとえば、キッチンやお風呂の水回りの修繕、老後の生活に備えたバリアフリー工事…。
これらは数十万〜数百万円単位の支出になることも珍しくありません。
もし「ローン完済」と「リフォーム費用」が同時期にのしかかれば、退職後に使える資金が一気に削られてしまうこともあります。
住宅は資産であると同時に「お金のかかる存在」でもある、という視点を忘れずにいたいものです。
親の介護費用という「予期せぬ出費」
そして、もっとも計画が立てにくいのが親の介護です。
施設入居となれば、その額はさらに大きくなります。
共働きで収入がある家庭でも、「教育費+介護費用+自分たちの生活費」が同時にのしかかれば、一気に家計が赤字に傾くことも珍しくありません。
特に女性は、介護の担い手となることが多いため、時間的にも経済的にも二重の負担を背負いやすいのです。
「想定外の支出+キャリアへの影響」が重なると、老後資金どころではなくなる現実が待っています。
私の知人も、親の介護がきっかけで時短勤務にならざるを得なくなり、「家計もキャリアもダブルで揺らいだ」と話していました。
こうした状況は誰にでも起こりうることです。
まとめ
教育費、住宅ローンやリフォーム、そして親の介護。
これらがちょうど40代から重なってくるのは、ある意味「人生の必然」かもしれません。
でも共働きだからと油断していると、「なんとなく大丈夫」と思っていた老後資金が大幅に不足するリスクは現実のものになってしまいます。
老後資金不足のシミュレーション
| 項目 | 平均額(月) | 年間 | 20年合計 |
|---|---|---|---|
| 高齢夫婦の平均支出 | 26万円 | 312万円 | 6,240万円 |
| 平均年金収入 | 21万円 | 252万円 | 5,040万円 |
| 毎月の不足額 | 5万円 | 60万円 | 1,200万円 |
だからこそ、「今は出費が多いから」と先送りするのではなく、40代のうちに小さくても老後資金づくりをスタートさせることが大切です。
未来の自分へのプレゼントだと思って、一歩を踏み出してみてください。
次では、そんな不安を解消するために、40代からでも始められる「老後資金の底上げ術」を一緒に見ていきましょう。
40代から始める「老後資金の底上げ」実践術
「もう遅いんじゃないかな…」
と感じるのは、40代で老後資金を考え始めた方の多くに共通する思いです。
実は、私自身も40代のはじめに同じような不安を抱えました。
けれど、老後のお金づくりは「早く始める」ことよりも「仕組み化して続ける」ことが大事だと実感しています。
節約ばかりで我慢を重ねると、ストレスがたまって続きません。
たとえるなら、毎日コーヒーを一杯飲んでいるうちに「いつの間にかポイントカードがいっぱいになっていた」ような感覚でしょうか。
ここでは、40代からでも無理なく始められる具体的な方法のひとつ、iDeCoとNISAのW活用についてお伝えします。
iDeCo・NISAのW活用で長期資産形成
「もう40代からじゃ遅いのでは?」
と不安になる気持ち、よくわかります。
そのカギになるのが、iDeCoとNISAという「国のお墨付き」の制度をセットで使うことです。
なぜ仕組み化が大切かというと、40代は教育費や住宅ローンなど大きな出費が重なりやすく、「余ったら貯金しよう」と考えてもなかなか老後資金に回らないから。
そこで頼りになるのが、自動的に天引きされるiDeCoと、少額から積立投資できるNISAです。
この2つを組み合わせると、「考えなくても資産が積み上がっていく仕組み」を作れます。
iDeCoの特徴とメリット
iDeCoは、自分で掛金を積み立てて将来の年金を準備する制度です。
最大の魅力は「掛金が全額所得控除になる」こと。
つまり、払った分だけ税金が安くなります。
これは、実質的に「利息がプラスされている」ような効果です。
もちろん注意点もあって、原則60歳までは引き出せません。
けれど裏を返せば「確実に老後資金として残せる口座」と考えることもできます。
私の知り合いも、「強制的に老後のお金を守ってくれるのはむしろ安心」と話していました。
NISAの特徴とメリット
一方のNISAは、投資で得た利益に税金がかからない制度です。
通常は株や投資信託の利益に約20%の税金がかかりますが、NISA口座ならゼロ。
2024年から始まった新NISAでは非課税の上限額も拡大し、しかも期限がなくなったので「ずっと」非課税で運用できます。
「コツコツ積み立てが未来のお守りになる」──それがNISAの強みです。
W活用のポイント
では、iDeCoとNISAをどう分けて使えばいいのでしょうか。
シンプルに言えば、
- iDeCo → 老後まで絶対に使わない「年金づくり」
- NISA → 教育費やリフォームなど、将来必要になる可能性がある「柔軟なお金」
という役割分担です。
これなら節税しながら、万が一の出費にも備えられるバランスのいい形になります。
実際に始めるには?
スタートするには証券会社の口座開設が必要です。
どちらも手数料が安く、スマホアプリで気軽に取引できるのが魅力です。
楽天証券なら楽天ポイントで投資ができ、「日常の買い物がそのまま資産形成につながる」という口コミも多く見られます。
「商品選びが不安…」という声もよく聞きますが、最初は「全世界株式インデックスファンド」や「S&P500連動型」といった王道の投資信託から始めれば安心です。
まとめ
iDeCoとNISAをうまく使えば、40代からでも老後資金は十分に底上げできます。
iDeCoで税金を節約しつつ堅実に年金を準備し、NISAで柔軟に資産を育てる。
この二本柱を立てることで、「気づけばお金が貯まっていた」という未来を手にできるのです。
次は、せっかく積み立てたお金を「減らさない」ための工夫──固定費の見直しについてご紹介します。
保険の見直しで毎月数千円~1万円の固定費削減
「毎月の生活費だけで精一杯で、老後のために回せる余裕なんてない」
そんなため息を、友人とのお茶の席でもよく耳にします。
私自身も、子どもがまだ小さかった頃は同じように思っていました。
でも実は、ほんの少し工夫するだけでお金の流れは変わります。
そのカギのひとつが、意外と見落としがちな「保険の見直し」です。
保険って、一度入るとそのままにしてしまう人が多いですよね。
だけど人生は常に変化していて、必要な保障の形も変わっていきます。
40代になると、子どもの進学や独立が近づいたり、住宅ローンの残高が減ってきたり。
さらに医療制度も昔よりずっと手厚くなっています。
なのに、30代の頃と同じ金額・同じ内容の保険を払い続けている…そんなケースは意外と多いんです。
たとえば、子どもが小さい頃に「もしもの時のために」と大きな死亡保障をつけたままにしていると、もう必要ないのに毎月高い保険料を払い続けることになります。
また、医療保険に「先進医療特約」や「通院特約」をいくつもつけていると、その分だけコストが膨らみます。
まるで冷蔵庫に古い調味料を入れっぱなしにしているようなもの。
使わないのにスペース(家計)を圧迫している状態です。
具体的に見直すときのポイントは3つ。
- 死亡保険の保障額を減らす
子どもが社会人になれば、生活費の心配はほとんどなくなります。
保障額を半分にしただけで、月々の保険料が数千円下がるケースも珍しくありません。 - 医療保険は必要最低限でOK
日本は「高額療養費制度」があるので、自己負担は月数万円程度に抑えられます。
手厚すぎる保障は「安心料」という名の無駄払いになりがちです。 - がん保険との重複をチェック
医療保険とがん保険の保障内容がかぶっていないか確認しましょう。
必要な部分だけ残すのがポイントです。
実際に私の知人夫婦(40代)が見直しをしたときは、夫の死亡保険を半分に、妻の医療保険から不要な特約を外すことで、夫婦で月9,000円も固定費が減りました。
年間にすると約10万円。
これをそのまま投資信託で積み立てたところ、20年後には280万円近くに育つ試算になりました。
「保険料を削ったのに、老後資金が増えるなんて!」と、ご本人たちはとても嬉しそうでした。
「でも、どこから手をつけていいのか分からない」という方には、第三者の無料相談サービスを頼るのも一つの方法です。
相談するときは「今より保険料が安くなるか」「不要な特約がついていないか」といった視点を意識すると、営業トークに流されず安心です。
保障を減らすのは勇気がいりますが、その一歩で毎月の負担を減らし、その分を未来のために回せるようになります。
つまり、保険の見直しは「安心を削る」のではなく、「未来の安心を買い直す」こと。
週末にでも家計簿を開いて、冷蔵庫の整理をするような気持ちで、一度見直してみてください。
次は、こうして浮いたお金をさらに活かしていく方法——副収入やスキルを使って「+1万円」を積み上げる工夫についてご紹介します。
副収入・スキル活用で「+1万円」を積み上げる
「あと1万円、毎月収入が増えたら…」
そんな風に思ったこと、ありませんか?
私は正直あります。
子どもの塾代や自分の習いごと、ちょっとした旅行資金。
生活費だけでギリギリだと、どうしても老後資金まで頭が回らないんですよね。
でも、副収入で月1万円を足すだけで、未来は大きく変わります。
数字だけ見ると「たった1万円で?」と驚きますが、これは節約だけではなかなか得られない効果です。
副収入のいいところは「無理をしなくていい」ところ。
副業と聞くと「深夜まで働く」「本業に支障が出る」といったイメージが浮かぶかもしれません。
でも大切なのは「細く長く」続けること。
1万円なら、1日30分から1時間ほどで達成できるペース。
ちょうど好きなドラマを1本観るくらいの時間を副収入に充てる感覚です。
これなら精神的に追い詰められることなく続けられます。
では、具体的にどんな方法があるのでしょうか?
- 在宅ワーク(クラウドワークス、ランサーズ)
文章作成やデータ入力など、特別な資格がなくてもできる仕事がたくさんあります。
たとえば、1件500円〜1,000円の案件を週に数件こなせば、月1万円は十分射程圏内。
私の知り合いは、子どもが寝静まったあと30分だけ作業をしてコツコツ積み上げています。 - スキルシェア(ココナラ、タイムチケット)
「Excelが得意」「イラストを描ける」「人の話を聞くのが上手」
そんな日常のスキルがそのままお金に変わります。
ある友人は「家計簿アドバイス」をサービス化し、1件2,000円で提供。
毎月数件の依頼で1万円を超えています。 - 資格を活かす働き方
FP(ファイナンシャルプランナー)や簿記などの資格を持っているなら、それを活かすチャンスです。
小さな副収入から始まって、将来的にはキャリアアップにもつながることがあります。 - 不用品販売(メルカリ・ヤフオク)
まずは家の整理からスタート。
着なくなった洋服、子どもの教材、眠っていたブランドバッグ。
これらを出品するだけで数万円の収入になった、という話は珍しくありません。
ちょっとした大掃除が、お金と気持ちの両方の余裕につながります。
実際の事例もご紹介します。
都内に住む40代のAさんは、フルタイム勤務のあと夜に30分だけライティングを続け、月に1万円を確保しています。
関西のBさんは「家計簿をつけるのが得意」というスキルをココナラに出品し、月5件ほどの依頼で安定して副収入を得ています。
どちらも「無理なくコツコツ」が共通点です。
ただし、副収入で得た1万円をそのまま生活費に回してしまうと、いつの間にか消えてしまいます。
たとえば、積立NISAや専用の貯蓄口座に直行させる。
心理的にも「未来の自分へのプレゼント」と思えば続けやすくなります。
副収入+1万円の積み上げ効果(年3%運用想定)
| 毎月の積立額 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|
| 1万円 | 約140万円 | 約280万円 |
| 2万円 | 約280万円 | 約560万円 |
結局のところ、副収入で月に+1万円は「特別な人」だけの話ではありません。
自分のちょっとしたスキルや空き時間を使えば、誰にでも可能性があります。
小さな一歩が、将来の大きな安心につながるのです。
そして次に考えたいのは、せっかく増えたお金をどう活かすか。
iDeCoやNISAと組み合わせることで、資産形成はもっと加速します。
その方法を、次で一緒に見ていきましょう。
「お金の不安」を減らすための家計マネジメント
「投資とか副収入とか、やらなきゃと思うけど、そもそも毎月のお金の流れがよく分からないんです」
「老後のことを夫と話したことがない…」
こうした声、実は本当によく耳にします。
私自身、昔は「なんとなく貯金しているし大丈夫かな」と思っていました。
でも、いざ大きな出費があったときに「あれ?どこにどれだけお金があるのか分からない」と焦った経験があります。
老後資金づくりで一番大事なのは、実は「増やすこと」より「整えること」。
お金の流れを整理して「見え化」すること、夫婦で未来について言葉にして共有すること、そしてときには専門家の力を借りること。
これらを積み重ねていくことで、不安は少しずつ小さくなり、安心感に変わっていきます。
家計の見える化で「使途不明金」をなくす
「何に使ったか思い出せないのに、残高が減ってる…」
これ、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
私も以前、ATMで通帳を記帳したときに「え、なんでこんなに減ってるの?」と青ざめたことがあります。
こうした「使途不明金」を減らす一番の方法は、家計を「見える化」すること。
昔ながらのノートに書き込む方法も良いですが、最近はスマホアプリが本当に便利です。
どちらも無料で始められるので、まずは1~2か月試してみると「意外とコンビニで使いすぎてたな」とか「サブスクが二重になってる!」といった発見があります。
こうして浮いた数千円を「老後資金用の口座」に振り替えるだけでも、ちょっとした達成感が得られるんです。
夫婦で老後資金の目標額を共有する
「とりあえず貯金してるけど、老後にいくら必要かは考えたことがない」
実はこれもよくある話。
でも、この「なんとなく」が一番の落とし穴です。
総務省のデータでは、高齢夫婦の平均支出は月26万円ほど。
たとえば、年金だけでは毎月5万円足りないとすると、20年で1,200万円の備えが必要になります。
目標額を出すと「じゃあ毎月いくら積み立てればいいか」が見えてきますし、夫婦で考え方のすり合わせもできます。
実際、夫は「年金で大丈夫」と思っていたけれど、妻は「不安で眠れない」と感じていた、なんてケースも珍しくありません。
数字を目の前に置いて話すと、「二人で一緒に準備している」という安心感が生まれ、家計の不安はぐっと軽くなります。
プロに相談する選択肢も持つ
「家計簿もつけてるし、夫とも話した。でも、この先どう進めればいいか分からない…」
そんなときは、プロに相談するのも一つの方法です。
ファイナンシャルプランナー(FP)の無料相談は、意外と身近なところにあります。
「プロに相談なんてハードルが高い」と思うかもしれませんが、実際に相談してみると「え、こんな制度があったんだ」と新しい発見があるものです。
特に40代は、まだ方向修正がきく大事な時期。
まとめ
家計マネジメントは「節約して我慢すること」ではなく、「未来の安心を整えること」。
見える化で無駄を減らし、夫婦で目標を共有し、ときにはプロの力も借りる。
この3つを意識するだけで、「お金の不安」はずっと軽くなります。
そして、土台が整ったら次は「どう増やすか」。
投資や副収入を組み合わせて、少しずつ未来の安心を積み上げていきましょう。
40代からの老後資金準備を「習慣化」するコツ
「老後のお金の準備は大事だとわかっているのに、つい後回しにしてしまう」
これ、私自身もずっとそうでした。
40代って、子どもの教育費や親の介護、仕事での責任が一気に重なる時期ですよね。
自分のことを考える余裕なんてない、と感じるのは自然なこと。
ポイントは「頑張る」より「仕組みに任せる」。
考えなくてもお金が積み上がる仕組みを作れば、気づいた頃にはしっかり備えができているのです。
先取り貯蓄の自動化で「考えなくても貯まる」
お金を貯める基本は「余ったら貯金」ではなく「先に取り分けて残りで生活する」こと。
頭では理解していても、実際はなかなか難しいんですよね。
私も昔、「今月は交際費が多かったから無理…」と何度も挫折しました。
給与天引きの財形貯蓄や銀行口座の自動積立を使えば、毎月の手間なく積み立てが進みます。
「気づいたら1年で12万円貯まっていた!」という小さな驚きが、未来の安心につながります。
考えなくても続くのが、習慣化の最大の武器です。
ライフイベントごとの「見直し」を当たり前にする
仕組みを作ったら終わり、ではありません。
人生には転職や子どもの進学、親の介護など、出費が一気に増えるタイミングがあります。
その時期に一度立ち止まって、家計を「リセット」する習慣を持つことが大切です。
たとえば、子どもが大学に進学する頃は教育費が急にかかります。
また、収入が変わるときもチャンス。
転職や昇進で収入が増えたら、そのまま生活費に回すのではなく、貯蓄や投資の積立に回す。
いわば「見直しのクセ」をつけておくと、家計は柔軟に対応でき、無理なく長く続けられるのです。
小さな成功体験でモチベーションを育てる
正直なところ、「老後のためにコツコツ貯める」って遠すぎて実感が湧きにくいですよね。
私も最初は「モチベーションが続かないな」と何度も思いました。
そんな時に助けになるのが「小さな成功体験」。
たとえば、「1年間で10万円貯まった!」と数字で確認できると、「ちゃんとできてる!」と自信になります。
習慣は「できた!」という感覚から生まれるもの。
小さな喜びを繰り返すことで、長期的な資金準備も自然と続けられます。
まとめ
40代からの老後資金づくりを習慣化するコツは、「自動化」「見直し」「小さな成功体験」の3つです。
無理なく仕組みに任せ、節目ごとに調整し、達成感を積み上げる。
それだけで、未来の安心はぐっと近づきます。
次は、こうして整えたお金の流れをどう「増やして守るか」。
ここまで進めてきたあなたなら、きっと次のステップも前向きに取り組めるはずです。
まとめ
40代からの老後資金準備は、決して遅すぎることはありません。
むしろ「今だからこそできる工夫」があります。
ここまで見てきたように、共働きだからといって安心するのではなく、計画的に「底上げ」をしていくことが大切です。
副収入やスキルを活かした小さな仕事を取り入れるだけで、毎月+1万円が積み上がります。
一見ささやかに思える金額でも、20年続ければ数百万円の差に。
クラウドワークスやスキルシェア、資格を活かした活動など、自分のライフスタイルに合った方法を選ぶのがポイントです。
どんなに収入を増やしても、支出が漏れていては意味がありません。
家計簿アプリを使えば、無駄な支出や二重契約が一目で分かります。
浮いた数千円をそのまま老後資金に回せば、ストレスなく資金形成が進みます。
貯蓄や投資は、一度の努力ではなく「続ける仕組み」を作ることが成功の秘訣です。
自動積立やつみたてNISA、iDeCoを設定しておけば、「気づけば貯まっていた」という安心感につながります。
加えて、転職や子どもの進学といったライフイベントごとに見直しを習慣にすることで、無理なく続けられます。
「老後に夫婦で世界一周旅行に行きたい」
「孫に誕生日プレゼントを渡せるおばあちゃんになりたい」
といった具体的な夢を思い描けば、お金を貯める行為そのものがワクワクに変わります。
共働きは確かに強みですが、それだけで老後資金が十分とは限りません。
40代の今から「収入の底上げ」「家計の見える化」「習慣化」の3つを実践することで、将来の不安はぐっと軽くなります。
小さな一歩を積み重ね、未来の安心を自分たちの手でつくっていきましょう。
老後資金づくりの3本柱
| 工夫のポイント | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 収入の底上げ | 副収入・スキル活用 | 資金の上乗せ |
| 支出の見える化 | 家計簿アプリ・無駄削減 | 毎月数千円改善 |
| 習慣化 | 自動積立・定期見直し | 長期的な安心 |