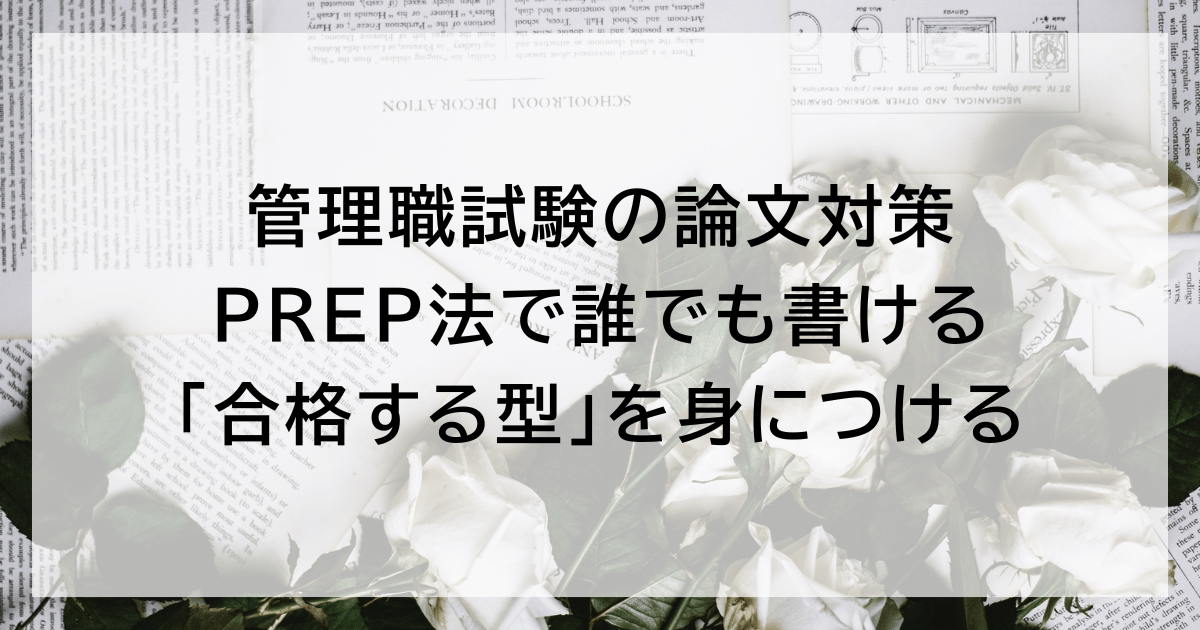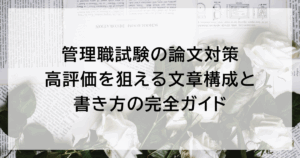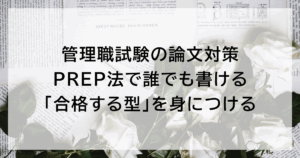管理職試験の論文は「型」を知っているかどうかで大きく差がつきます。
日ごろ文章を書くのが得意な方でも、試験本番では限られた時間のなかで論理的に、かつ採点者に伝わりやすい形でまとめなければなりません。
そのときに役立つのが「PREP法」です。
PREP法とは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(再結論)という流れで文章を組み立てる方法。
シンプルながら論理が通りやすく、採点者に安心感を与える効果があります。
特に女性の受験者のなかには、「論文はセンスや経験値が必要」と思い込んで苦手意識を抱える方も多いのではないでしょうか。
ですが、論文試験に必要なのは「センス」ではなく「型」です。
型さえ覚えれば、緊張する試験当日も自然に手が動き、安心して書き進めることができます。
この記事では、管理職試験の論文で使えるPREP法の活用法や、時間内に書ききるためのトレーニング方法を紹介します。
「書き始めるとまとまらない」「途中で時間切れになる」そんな悩みを解決できるヒントをぜひ持ち帰ってください。
- 論文試験で「何を書けばいいか分からない」「話が散らかってしまう」と不安を抱えている方
- 時間内にうまくまとめられず、結論が弱くなる方
- 自分の経験や考えをどう文章に落とし込めばよいか迷っている方
- 女性管理職候補として、読み手に「論理的で分かりやすい」と思わせたい方
論文試験で「型」が求められる理由
管理職試験の論文を書くとき、私自身も最初は「文章力さえあれば大丈夫」と思っていました。
でも実際に練習を始めてみると、思いついたことを並べただけではまとまりがなく、結論がぼやけてしまうんです。
まるで友人との雑談みたいに、話があちこち飛んでしまう感じ。
これでは、試験官に伝わるはずがありませんよね。
論文試験で本当に問われているのは、文章の上手さではなく「論理的に考えて課題を解決できるか」という力です。
だからこそ、型を意識して書くことが大切なんです。
型があると、こちらの考えがすっと相手に届きやすくなります。
逆に、型を使わないまま自由に書き進めると、せっかくの経験や意見が埋もれてしまい、評価が伸び悩むリスクがあります。
実際、私の周りの女性受験者からも「気づいたら前置きが長くなって、結論にたどり着けない」「どうしても感情に寄ってしまって、論理が弱くなる」といった声をよく耳にします。
これは能力の問題ではなく、単純に「型」を知らないだけ。
型を取り入れるだけで、同じ内容でも見違えるように伝わりやすくなるんです。
たとえば、よく出題されるテーマのひとつに「働き方改革」があります。
型を使わずに書くと「私も長時間労働でつらい思いをした経験があり…だから改善したいと思っています。最近は在宅勤務も増えてきて…」という流れになりがちで、結論がぼやけます。
ところが型を意識すると、
「働き方改革は社員の健康と生産性の両立に不可欠です(結論)。
なぜなら、労働時間の是正や柔軟な勤務は離職を防ぐからです(理由)。
私の部署でも在宅勤務を取り入れたことで育児中の女性社員が働き続けられた事例があります(具体例)。
だからこそ、柔軟な制度を整備し、社員一人ひとりが力を発揮できる環境づくりが必要です(再結論)」
と、すっきり筋が通った文章になるんです。
この違いはとても大きい。
試験官は何十枚もの答案を短時間で読みます。
その中で「最初に結論が明確に書かれている」「理由が整理されている」「具体例で説得力が増している」答案は、強く印象に残ります。
型を使うことは、試験官に対する“思いやり”でもあるんですね。
そしてもうひとつ。
女性にとって型を使う最大のメリットは「自信を持って書ける」ことだと思います。
試験中、「私の意見って浅いんじゃないかな」「説得力に欠けるかも」と不安になる瞬間は必ずあります。
でも型に沿って結論・理由・具体例を並べるだけで、不思議と論理的で説得力のある文章に仕上がるんです。
私は「型があるから大丈夫」と思えるだけで、緊張が和らぎ、落ち着いて筆を進められました。
さらに型は、文章のためだけでなく「思考整理のツール」にもなります。
論文試験は国語のテストではなく、管理職として「課題にどう向き合い、どう解決策を導くのか」を見る試験です。
型を使って整理された答えを書ける人は「この人なら現場をまとめられる」と試験官に感じさせやすいのです。
要するに、論文試験で型が求められる理由は大きく3つ。
「型は窮屈そう」と思うかもしれませんが、実際にはあなたの魅力を引き出す枠組み。
枠があるからこそ、自由に安心して表現できるのです。
さて、ここまで読んで「じゃあ具体的にどんな型を使えばいいの?」と気になってきた方も多いはず。
そこで次に紹介したいのが、ビジネス文書やスピーチでも広く使われている「PREP法」です。
PREP法とは? 基本の流れを理解しよう
管理職試験の論文って、「文章の上手さ」よりも「どう伝えるか」の方が大事なんですよね。
私自身も最初は、長く丁寧に書けば評価されると思っていました。
でも実際に書いてみると、前置きばかり長くなってしまって、「で、結局何が言いたいの?」と自分で読み返しても分からなくなることがありました。
そんなときに出会ったのが PREP法 です。
名前だけ聞くと堅苦しい印象ですが、要は「結論を先に言って、理由と具体例で支えて、最後にもう一度結論で締める」というシンプルな流れです。
Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再結論)の頭文字を取ってPREP。
まるでプレゼンの道具箱みたいな存在で、使い方を覚えると文章の見栄えがぐっと変わります。
ではなぜ、この方法が管理職試験と相性抜群なのか。
試験では「課題にどう向き合い、どう対応するか」を限られた時間の中で示さなくてはいけません。
けれど、多くの人が「ついエピソードから入りたくなる」「話が回り道してしまう」「結論が最後にちょこんと出てくる」なんてパターンに陥りがちです。
これだと、試験官が冒頭で「この人、結局何を言いたいんだろう?」と首をかしげてしまうんです。
「私はこのテーマについてこう考える」とはっきり示すことで、読み手に安心感を与えられるんですね。
そのうえで理由を補い、具体的な体験や事例で説得力を加え、最後にもう一度結論で締める。
たったこれだけで、論文全体がぐっと筋の通ったものになります。
たとえば、出題テーマが「女性管理職の育成」だったとしましょう。
PREP法を使えばこんな流れになります。
- 最初に「女性管理職を増やすことは、組織の成長に欠かせない」と結論を出す。
- 次に「多様な視点があることで意思決定の質が高まる」と理由を述べる。
- そこに「私の部署でも女性係長がリーダーとなり、新しい顧客層を開拓できた」という具体例を加える。
- そして最後に「だからこそ、女性リーダーの登用と育成を進めるべきだ」と再度結論で締める。
こうして整理すると、書いている自分も迷子にならずに済みますし、読む相手も「なるほど」とすんなり受け止めてくれます。
特に論文試験は制限時間があるので、この「迷わない書き方」は本当に大きな武器になります。
「でも、私にできるのかな?」と心配になる方もいるかもしれません。
大丈夫です。
PREP法は慣れてしまえば日常の会話や職場の報告でも自然と使えるようになります。
実際、ビジネス研修やスピーチ指導でも必ずと言っていいほど紹介される方法で、オンライン講座などでも基本スキルとして扱われています。
つまり社会人としての「必須アイテム」なんですね。
そして、ここでお伝えしたいのは「PREP法はただのテクニックではない」ということ。
私自身、試験勉強でこの方法を意識し始めてから、上司への報告や会議での発言にも自信が持てるようになりました。
考えを整理して伝える力は、論文試験にとどまらず、日常の仕事や人間関係にも役立つんです。
さて、ここまででPREP法の基本はつかめてきたと思います。
次はもう少し踏み込んで、「実際に論文試験で使うと、どんなメリットがあるのか」を具体的に見ていきましょう。
論文試験でのPREP法の実践ステップ
「PREP法の流れは分かったけれど、実際に試験でどう使えばいいの?」と感じる方は多いと思います。
私も最初はそうでした。
頭では理解しているのに、白紙の答案用紙を前にすると手が止まってしまうんですよね。
でも安心してください。
少し練習すれば、試験会場でも迷わず書けるようになります。
ここでは、私自身も実践して効果を感じた「PREP法の4ステップ」を紹介します。
流れさえつかめば、あとは自然に手が動くようになりますよ。
Step1:まずは結論を先に決める
試験問題には必ず「あなたの考えを述べよ」とありますから、出題を読んだらまずは「一文で答える」と心がけてみてください。
たとえば「リーダーに必要な資質は何か」と問われたら、「私は、リーダーには傾聴力が最も必要だと考える」と一文で決めてしまう。
完璧でなくて大丈夫です。
あとで理由や事例を補えば形になります。
ただし気をつけたいのは、設問の意図を読み違えないこと。
昔の私も「リーダーの資質」を問われているのに「職場改善策」を延々と書いてしまったことがあり、あとで「あぁ、全然ズレてた」とがっかりしました。
Step2:理由を2〜3点に絞る
このときのコツは「2〜3点に絞る」こと。
理由をたくさん書きたくなる気持ち、よく分かります。
でも多すぎると文章が散らかって、逆に説得力が落ちてしまうんです。
たとえば「リーダーには傾聴力が必要だ」と結論を出したなら、理由は「(1)部下の信頼を得られる」「(2)現場の課題を正しくつかめる」といった具合に整理するとスッキリします。
特に女性の受験者にとっては、人間関係や日常の細やかな観察が強みになります。
たとえば「家庭と仕事を両立する部下の声を拾うことで、職場全体の安心感につながる」といった視点は、現場感覚がある人だからこそ書ける理由です。
試験官にとっても新鮮に映ります。
Step3:自分の経験や具体例を入れる
理由だけ並べても「きれいごと」で終わってしまいます。
これがあると文章が一気に生き生きとしてきます。
たとえば「部下の声を尊重することが大事」と書いたなら、「私の部署では新人の提案を取り入れたことで作業効率が2割改善した」と付け加える。
大げさな成果でなくても大丈夫です。
「後輩の相談に乗って一緒に改善策を考えたら、チームが前向きになった」といった小さなエピソードでも十分。
むしろそういう日常的な経験こそ、管理職としての視点につながります。
これが試験本番で本当に役に立ちました。
Step4:最後にもう一度結論で締める
「以上の理由から、私は〜と考える」という形で、同じ言葉を使うのが効果的です。
「結論を繰り返すのはくどいのでは?」と思うかもしれません。
でも、試験官は短い時間で大量の答案を読みます。
だからこそ、結論を二度伝えることで「この人はこう考えているんだな」と強く印象づけられるのです。
私も最初は「わざわざ繰り返すなんて…」と思っていましたが、添削を受けたときに「最後のまとめがあると文章が締まって見える」と指摘され、なるほどと納得しました。
この4ステップに沿って書けば、「途中で迷子になる」「話が脱線する」といった不安は解消されます。
むしろ「型に沿って書けば自然に論理的になる」という安心感が得られるんです。
PREP法の流れ図
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| Point(結論) | 最初に結論を述べる | 採点者に論旨を伝える |
| Reason(理由) | なぜそう考えるのかを示す | 論理性を補強 |
| Example(具体例) | 経験や事例を挙げる | 説得力を高める |
| Point(再結論) | 結論を繰り返す | 印象を残す |
さて、型をつかんだら次に気になるのは「制限時間内にどうやって書ききるか」ですよね。
次では、忙しい女性でも取り入れやすい、時間内に仕上げるための練習法をご紹介します。
時間内に書ききるための練習法
論文試験でよく耳にする悩みのひとつが、「時間が足りなくて最後まで書けなかった」という声です。
私自身も過去に模試で同じ経験をしました。
頭の中には伝えたいことがたくさんあるのに、時計の針がどんどん進んでいく焦り。
書き終わらない答案用紙を見て、なんとも言えない悔しさを感じたのを覚えています。
時間配分例(試験60分の場合)
| 作業 | 推奨時間 | ポイント |
|---|---|---|
| 構成案作成 | 10分 | 骨組みをしっかり作る |
| 本文執筆 | 40分 | PREP法で展開 |
| 見直し | 10分 | 結論・誤字脱字を確認 |
管理職試験の論文は、ただ文章を書くのではなく、限られた時間で「結論を端的に示す」「理由や事例で説得力を持たせる」という高度な技術が求められます。
だからこそ、普段から「時間を意識した練習」を積み重ねることが大切です。
ここでは、忙しい女性でも続けやすいトレーニング法をいくつかご紹介します。
ニュース記事を一言でまとめてみる
まずおすすめなのが、日常的に触れるニュースを使った練習です。
新聞やネット記事を読んだら、「私はこう考える」と結論を一文で言い切ってみる。
そして、なぜそう考えるのか、理由を2つほど挙げ、最後にもう一度「だからこうすべき」と締める。
たとえば保育園の待機児童に関する記事を読んだら、「職場の柔軟な働き方支援が必要」と結論を置き、理由に「女性の離職を防げるから」、具体例として「フレックスタイム制度で継続勤務が可能になった事例」などを添えると自然と整理できます。
私も通勤電車の中でよくこの練習をしました。
15分だけ集中! 構成メモトレーニング
次に効果的なのが「過去問を使った15分構成練習」です。
出題を読んだら、15分で結論・理由・事例をメモにまとめてみる。
最初は「あぁ、時間が足りない」と焦りますが、続けていくうちに「ここは削っても大丈夫」「この順番の方が伝わりやすい」と取捨選択が早くなります。
私はこの練習を夜の家事が終わった後に取り入れていました。
15分なら疲れていても意外と取り組めますし、毎回構成メモだけでも積み重ねれば本番での安心感につながります。
忙しい毎日に取り入れる工夫
「子育てや家事でまとまった時間がない」という方も多いでしょう。
そんなときはスキマ時間を味方につけましょう。
通勤中にスマホで記事を読んで頭の中で要約する、昼休みに設問だけ見て「結論一文」を考えてみる。
これだけでも立派な練習になります。
最近はオンライン講座も充実していて、スマホから論文の添削を受けられます。
私も試しに利用したのですが、自分では気づけなかった癖を指摘してもらえて目からウロコでした。
外部の力を借りるのも効率的な方法です。
スキマ時間トレーニング例
| 時間帯 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 通勤電車 | ニュース記事をPREPで要約 | 3〜5分 |
| 昼休み | 過去問の構成案を作成 | 15分 |
| 夜のリラックスタイム | 書いた答案を自己チェック | 10分 |
型に慣れると安心感が生まれる
こうして日常の中で「時間を区切って型に沿って考える練習」を重ねていくと、不思議と本番でも手が止まらなくなります。
緊張で頭が真っ白になっても、「まず結論を一文、そのあと理由と事例」と流れを知っていれば、自然と手が動きます。
試験官にとっても、型に沿った答案は読みやすく、内容が整理されている分、信頼感を与えやすいのです。
焦らず最後まで書ききる力は、一夜漬けでは身につきません。
だからこそ、小さな習慣を今日から始めることが、合格へのいちばんの近道なのです。
さて、あなたならこの中でどの方法から始めてみますか?
まとめ
論文試験は一見ハードルが高く感じられますが、実は「型」を押さえれば誰でも安定した答案を書けるようになります。
その代表的な型がPREP法です。
結論から始めることで論旨が明確になり、理由と具体例を示すことで説得力を増し、最後に再度結論を強調することで読後感をしっかり残せます。
この流れは読む人に安心感を与え、内容以上に「伝わりやすさ」という点で大きな加点につながります。
たとえば「部下の育成方法」でも「働き方改革」でも、「まず結論を言う」「理由を添える」「具体例を出す」「再度結論をまとめる」という型を適用できます。
つまり、テーマが変わっても慌てる必要がありません。
型に沿って骨組みを作り、その枠の中に自分の経験や知識を入れ込むだけで、まとまりのある論文に仕上がります。
もちろん、型を知るだけでは不十分です。
試験本番では限られた時間で答案を書ききる必要があるため、日ごろからのトレーニングが欠かせません。
忙しい女性におすすめなのは「スキマ時間トレーニング」です。
たとえば、朝の通勤電車でニュース記事を一つ選び、PREP法で3分以内に要約してみる。
昼休みに過去問を開き、15分だけで構成案を書き出す。
短時間でも継続すれば「考える順番」が自然に身につき、試験本番でのスピードと安心感に直結します。
また、過去問や模擬問題を解く際は「時間を測る」ことを意識しましょう。
制限時間を設けることで、答案全体の配分感覚が鍛えられます。
さらに、書いた答案を読み返して「結論が冒頭にあるか」「理由と具体例がセットになっているか」をチェックすることで、改善点が見つかります。
最後に強調したいのは、「論文は才能ではなく習慣で決まる」ということです。
PREP法という型を知り、日常的に練習していけば、これまで論文に苦手意識をもっていた方でも必ず上達します。
自分の考えを整理しやすくなるだけでなく、仕事上のプレゼンや報告書作成にも応用でき、キャリア全体にプラスの影響を与えてくれるでしょう。
つまり、PREP法を身につけることは、管理職試験合格への近道であると同時に、日常業務の質を高める自己投資でもあります。
今日から小さな一歩を踏み出して、論文試験を「怖いもの」ではなく「自分の力を伝えるチャンス」に変えていきましょう。
- 論文試験は「センス」ではなく「型」で攻略できる
- PREP法はどのテーマにも使える万能フレームワーク
- 日常のスキマ時間を活かした練習が合格力を高める