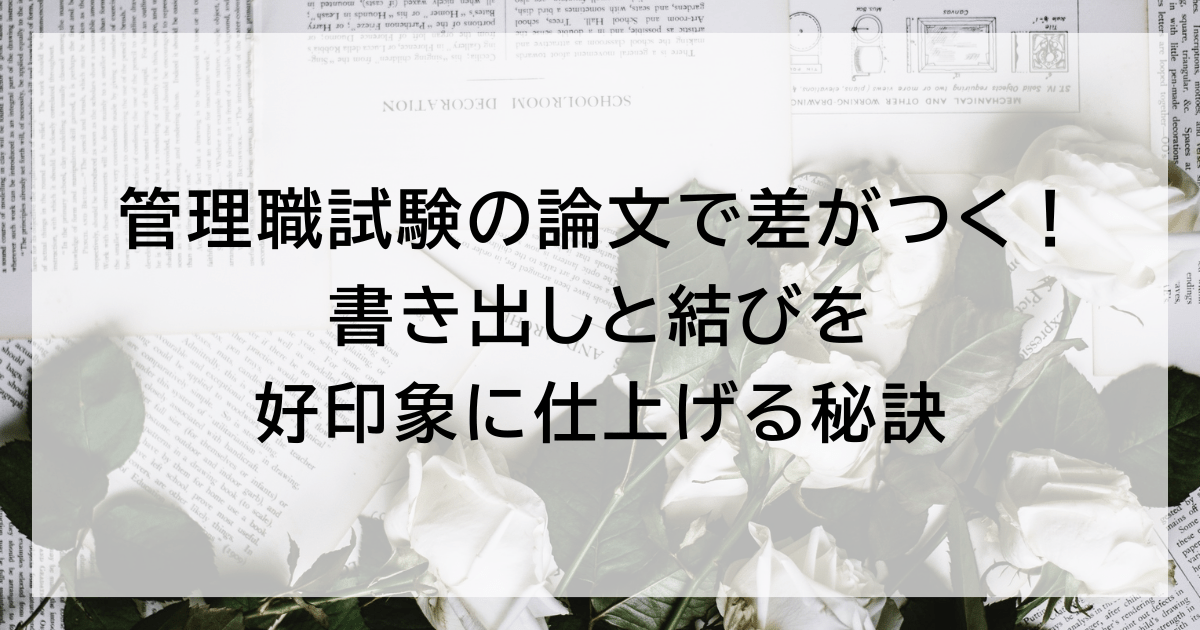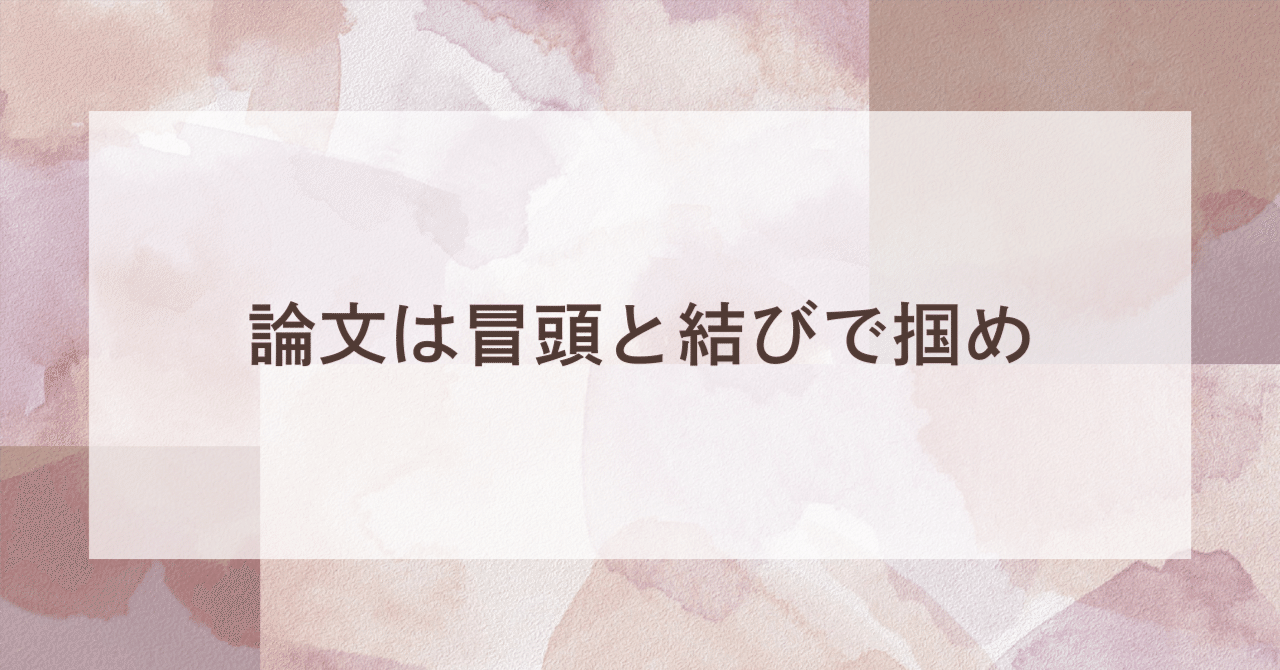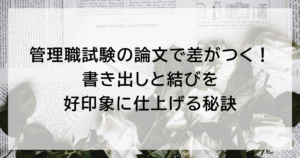管理職試験の論文を書くとき、一番悩ましいのが「どう始めるか」と「どう終えるか」ではないでしょうか。
実際、私自身も最初に挑戦したときは、書き出しでいきなり手が止まり、結びでは「以上です」としか書けずに落ち込んだ経験があります。
どんなに中身をしっかり準備しても、冒頭と結論の印象が弱ければ「説得力に欠ける」と評価されてしまうのです。
試験官は数多くの論文を読みます。
その中で目に留まるのは、スムーズな書き出しと、余韻を残す結びを持つ論文です。
言い換えれば、冒頭と結論こそが「合否を分ける決め手」になりやすいのです。
では、どうすれば読んだ人に「この人は管理職らしい視点を持っている」と感じてもらえるのでしょうか。
本記事では、書き出しと結びを磨くための具体的なコツを紹介します。
さらに、忙しい女性管理職候補でもスキマ時間で練習できる方法も取り上げます。
これを押さえれば、論文全体の完成度が大きく変わり、合格にぐっと近づけるはずです。
- 管理職試験の論文対策で、書き出しや結びの表現に悩んでいる方
- 仕事や家庭で忙しく、効率よく論文対策を進めたい女性管理職候補
- 採点者に「リーダーらしい」と思われる論文を書きたい方
なぜ「書き出し」と「結び」が大切なのか
管理職試験の論文で差がつくポイントは、意外にも「中身の濃さ」そのものではありません。
つまり「書き出し」と「結び」なのです。
私自身、初めて論文対策をしたとき、原稿の真ん中部分に力を入れすぎて、冒頭と結論はつい手を抜いてしまったことがあります。
ところがフィードバックで返ってきたコメントは「出だしが弱い」「最後の意志表示が足りない」ばかり。
考えてみれば、試験官は限られた時間の中で大量の論文を読むわけです。
まるで本屋さんで立ち読みするとき、最初の数行で「この本、読みやすそうだな」と感じるか、「ちょっと合わないかも」と閉じてしまうかが決まるのと似ています。
最初の一文で「この人は課題を理解している」と安心できれば、その後の文章にも耳を傾けてもらえます。
そして最後の結びがしっかりしていれば、「この人に部下を任せても大丈夫だ」と納得感を与えることができるのです。
具体例で考えてみましょう。
ある受験者が「私は日々の業務を通じて…」と始めたとします。
一見丁寧ですが、どこか曖昧で印象に残りにくいですよね。
一方で「働き方改革が進む今、管理職に求められるのは『効率的な業務推進と部下の成長支援』である」と始めたらどうでしょうか。
課題を的確に押さえていて、読み手の期待値がぐっと高まります。
結びも同じです。
「努力していきたいです」で締めれば、正直「結局、何をするの?」と物足りなさが残ります。
でも「業務改善と人材育成を両立し、持続的に組織力を高めることで会社の成長に貢献したい」と言えば、管理職としての姿勢がはっきり伝わりますよね。
女性管理職を目指す方の中には、「強すぎる言い方は敬遠されないかな」「感情的に見えないかな」と心配される方も多いと思います。
私自身もそうでした。
でも論文試験では、むしろ簡潔で力強い表現が評価につながります。
大事なのは「自分らしい言葉」で安心感を与えること。
きちんと課題を理解し、リーダーとしてどう行動するかを伝えれば、その強さは決して押しつけには映りません。
ここをしっかり押さえれば、途中の表現に多少の弱さがあっても、全体の評価はグッと上がります。
次は、実際に「好印象を与える書き出し」のパターンと注意点について見ていきましょう。
あなた自身の経験に引き寄せながら、説得力のある一文を作るコツを一緒に探っていきます。
好印象を与える書き出しのパターンと注意点
論文試験では、最初の一文が「その人の第一印象」になります。
大げさに聞こえるかもしれませんが、採点者は冒頭の数行で「この人はしっかりテーマを理解しているか」「最後まで読み進めて安心できるか」を直感的に判断します。
私も初めて添削を受けたとき、途中の議論には手を入れられなかったのに、冒頭一文だけで「弱い」と言われた経験があります。
そこから、「書き出しが全体のトーンを決めるんだ」と痛感しました。
結論からいえば、好印象を与える書き出しには大きく2つの型があります。
そしてもちろん、避けたほうがいいNGパターンもあります。
これらを意識しておくと、書き出しで迷わなくなり、論文全体に自信を持って臨めるようになります。
課題提示型
まず取り組みやすいのが「課題提示型」です。
テーマを冒頭でシンプルに言い換え、背景や前提を押さえたうえで自分の考えへとつなげる方法。
いわば「地図を広げてから旅を始める」ような安心感を与えられます。
たとえば「働き方改革が進むいま、管理職に求められるのは効率的な業務推進と部下の成長支援である」と書き出すと、採点者はすぐに「この人は課題を理解している」と納得できます。
逆に「私は日々の業務を通じて〜」と始めると、漠然としていて弱く映ってしまうのです。
「そんなにうまく要約できる気がしない…」と思う方もいるかもしれません。
私も最初はそうでした。
そのとき役立ったのは、新聞の見出しや厚生労働省の報告資料などを「一行で説明する練習」をすること。
少しずつ慣れてくると、文章がスッと頭に浮かぶようになります。
もし体系的に学びたいなら、オンラインでも学べるの論文対策講座が便利です。
添削を受けながら型を身につけると、自然に自分の言葉で課題提示ができるようになります。
体験・現場視点型
もうひとつ効果的なのが「体験・現場視点型」。
自分の業務経験を冒頭にさらっと一文で示すことで、現場感のある説得力を出す方法です。
「私は新規プロジェクトの進行管理を担当する中で、部下の育成と業務効率化の両立が大きな課題だと感じてきた」と書き始めれば、読む側は一瞬でその人の現場に引き込まれます。
ただし、ひとつ注意があります。
それは「長々と語らないこと」。
昔の私もそうでしたが、「せっかくの経験だから」と細かく書きすぎると、主題がぼやけてしまいます。
大事なのは一文か二文でキュッとまとめて、すぐに論点に進むこと。
もし「短くまとめるのが苦手」という方は、毎日1分で「今日の業務の気づき」をメモする習慣をつけるといいですよ。
論文対策だけでなく、会議での発言もぐっと洗練されます。
NG例
最後に、避けたほうがいい書き出し方についても触れておきましょう。
これだと論理が弱く、ただの感想文に見えてしまいます。
具体的な課題が見えないまま文章が続くと、読み手は「結局何を言いたいの?」と不安になります。
要は「主張が弱すぎる」か「前置きが長すぎる」かのどちらかです。
ここを避けるだけで、文章全体がぐっと引き締まります。
このように、課題提示型と体験視点型を意識しつつ、NG例を避ければ、冒頭の数行で好印象をつかめます。
論文の始まりはまさに「勝負どころ」。
ここを押さえれば、その後の展開にも自然と自信が生まれます。
次は、結びの部分で差をつけるコツを一緒に見ていきましょう。
良い書き出しと悪い書き出しの比較
| 種類 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|
| 課題提示型 | 「働き方改革が進む今、管理職に求められるのは効率化と人材育成である。」 | 「私は日々の業務を通じて…」と曖昧に始める |
| 体験型 | 「新規プロジェクトで部下育成と業務効率化の両立を痛感した。」 | 前置きが長く、論点に入る前に脱線してしまう |
| 項目 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|
| 書き方 | 「近年の働き方改革により〜」と背景を示す | 「私は〜と思います」と唐突に主張 |
| 印象 | 大局を理解していると伝わる | 個人的意見に見えて説得力が弱い |
結びで差がつく! 説得力ある締め方のコツ
論文を書いていて、「最後、どうまとめればいいんだろう…」と手が止まった経験はありませんか?
私も管理職試験の練習をしていたとき、そこが一番の悩みどころでした。
結びというのは、論文でいうところの「エンディングの音楽」のようなもの。
最初の数行がオープニングで印象を決めるなら、最後の数行は余韻を残す部分です。
採点者も、最後の一文を読んだときに「この人の考えは筋が通っていたか」「リーダーらしい視点を持っているか」を無意識に判断しています。
だから、結び次第で評価がぐっと上がることもあれば、逆に減点につながってしまうこともあるんです。
では、どうまとめれば「説得力のある締め」になるのでしょうか?
ここでは3つのポイントをご紹介します。
提案+効果で終える
まず一番わかりやすいのが、「提案+効果」で締めくくる方法です。
たとえば「業務改善の仕組みを導入することで、部門全体の生産性と働きやすさの両立が期待できる」といった形ですね。
私自身、最初は「そんなに具体的に書けない…」と悩みました。
でも、日頃からちょっとした業務改善の成功例や、他部署の取り組みをメモしておくと、いざというときに書ける材料になります。
最近は「BizHint」や「日経ビジネス」といったサービスで、他社の事例を知る機会も増えました。
そうした実例をストックしておくと、自然に「提案+効果」の形に落とし込めるようになりますよ。
リーダー視点を盛り込む
次に大切なのは、リーダーらしい視点を結びに入れることです。
管理職試験では「あなたがどう頑張るか」よりも、「組織をどう動かしていくか」に注目されます。
たとえば「部下一人ひとりの成長を支えることで、組織全体の成果につなげていきたい」と締めくくると、個人の決意を超えて、チーム全体を見据えていることが伝わります。
ここで気をつけたいのは「私が頑張ります」で終わらないこと。
リーダーに求められるのは、自分だけでなく周囲をどう巻き込めるかという視点だからです。
もし「リーダー視点ってどう書けばいいの?」と迷ったら、転職支援サイトなどのインタビュー記事がおすすめです。
現役の管理職がどう部下を育て、組織を導いているかを知ると、自分の言葉に落とし込みやすくなります。
NG例
もちろん、避けた方がいい結び方もあります。
これでは、せっかく積み上げた内容が一気に尻すぼみになり、努力がもったいないです。
たとえば本文で触れていない施策を、突然「結論」で書いてしまうと、「結局何を言いたかったの?」と読んだ人を混乱させます。
結びはあくまで「これまでの主張の集約」。
新しい話を広げる場ではありません。
結びは、論文全体を「きれいにラッピングするリボン」のようなもの。
少しの工夫で印象ががらっと変わります。
「提案+効果」で明快にまとめ、「リーダー視点」で広がりを持たせ、NG例を避ける。
これだけで結びの完成度は格段に上がります。
論文は最後まで読まれて初めて評価されるもの。
次の章では、こうした書き出しや結びをどう練習すれば自然に書けるようになるのか、具体的な方法をご紹介します。
試験直前の勉強にも役立ちますので、ぜひ続けて読んでみてください。
良い結びと悪い結びの比較
| 項目 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|
| 提案型 | 「改善を導入すれば生産性と働きやすさを両立できる」 | 「改善が必要だと思う」で終わる |
| リーダー視点型 | 「部下の成長を支え、組織成果につなげたい」 | 「以上です」で締める |
書き出しと結びを磨く練習方法
論文試験の勉強と聞くと、「1問まるごと仕上げなきゃ」と身構えてしまう方、多いのではないでしょうか。
私自身も最初はそうでした。
机に向かって冒頭から結論まで書き切ろうとして、時間ばかりかかり、結局どこが伸びたのかよく分からない…。
そんなもどかしさを感じていました。
でも実際には、全部を一気に仕上げる必要はないんです。
むしろ効率を考えると「書き出し」と「結び」だけに集中して練習したほうが、短時間でグッと力がつきます。
なぜなら、論文全体の印象は冒頭と結論でほとんど決まってしまうから。
まるで映画の予告編やラストシーンのように、最初と最後で「この作品は良かった」と記憶に残るのと同じですね。
忙しい毎日を送る女性にとって、この練習法はスキマ時間でできる「時短の切り札」になります。
では、具体的にどう取り組めばよいのでしょうか。
大切なポイントは3つです。
1つ目は「模範解答を自分の言葉に置き換えること」
予備校の教材や過去問集には模範解答が載っていますよね。
でも、それを丸ごと暗記しても、本番の試験でそのまま出題されるわけではありません。
私もかつては模範解答を覚え込んでいましたが、実際の試験では「これをどう当てはめればいいの?」と手が止まってしまいました。
むしろ、「模範解答の考え方を、自分の経験にどう言い換えられるか」と考えるほうがはるかに実践的です。
たとえば「人材育成が課題」と書かれていたら、自分が新人教育で工夫したエピソードを盛り込む、といった具合です。
ちょっとした置き換えでも、文章にリアリティが出て「机上の空論ではない」と伝わるのです。
2つ目は「時間を区切ってパターン練習をすること」
一気に書こうとすると気が重くなりますが、「書き出しだけ10通り」「結びだけ10通り」と小分けにすると、不思議と気楽に取り組めます。
通勤電車の中でスマホにメモする、昼休みにノートに3行だけ書く。
それだけでも十分な練習になります。
こうしてバリエーションを増やしておくと、本番で「このテーマならあのパターンが合う」と自然に引き出せるようになるんです。
まるでクローゼットにお気に入りの服が揃っていて、その日の気分に合わせて選べるような安心感があります。
3つ目は「第三者の目を借りること」
自分では「いい感じにまとまった!」と思っても、他人が読んだら伝わっていない…なんてこと、ありませんか?
私も同僚に読んでもらって「話は分かるけど印象に残らない」とズバッと言われ、落ち込んだことがあります。
けれど、その一言で「もっと具体例を入れたほうがいい」と気づけたんです。
身近に頼める人がいなければ、専門のサービスを活用するのも手です。
たとえば論文添削を行っている講座などでは、プロの講師が赤ペンで改善点を教えてくれます。
まるで料理教室で「もうひとつ塩を足すともっと美味しくなるよ」と指導してもらうような感覚で、文章がみるみる変わっていきます。
この3つを組み合わせれば、冒頭と結論の表現力は確実に磨かれていきます。
特に、仕事に家庭にと毎日走り回る女性管理職候補にとって、「冒頭と結論だけ練習する」方法は現実的で続けやすいアプローチです。
結局のところ、論文試験は一度で完璧に仕上げるものではありません。
短い時間を積み重ねながら、自分の言葉で説得力をつけていく試験です。
書き出しと結びをしっかり練習しておけば、全体の完成度は驚くほど引き上がります。
次のまとめでは、これまでのポイントを振り返りながら、合格に直結する学びを整理してみましょう。
練習法のステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 模範解答を自分流に置き換える | 実務経験を盛り込む |
| 2 | 書き出し・結びを分けて10パターン練習 | 短時間でも繰り返せる |
| 3 | 第三者に読んでもらう | 客観的な改善点を発見できる |
まとめ
論文試験は「内容」だけでなく「見せ方」も問われる試験です。
その中で特に重要なのが、書き出しと結びです。
冒頭は、読者を惹きつける「入り口」であり、結びは「印象を固定するラストシーン」。
この二つが整っているだけで、文章全体の評価は格段に上がります。
たとえば「近年の働き方改革に伴い、組織には効率と柔軟性の両立が求められている。その中で私の所属部署でも〜」と書き始めると、試験官は「この人は大きな流れを理解している」と安心して読み進められます。
反対に「私は〜と思う」で始めてしまうと、説得力が弱くなりがちです。
「業務改善を導入することで、生産性と働きやすさを両立できる」と書けば、論理がきちんと締まります。
また「部下一人ひとりの成長を支えることで組織全体の成果につなげたい」と結べば、管理職らしい視点を示せます。
一方で「以上です」「おわりです」と唐突に終わるのはNG。
文章全体を雑に扱っている印象を与え、評価を下げかねません。
さらに、書き出しと結びを強化するには練習法も工夫が必要です。
「冒頭だけを10パターン」「結論だけを10パターン」と短時間で繰り返すと、表現の引き出しが増えて本番で応用しやすくなります。
模範解答をそのまま覚えるのではなく、自分の経験や部署の事例に引き寄せて書き換えることも大切です。
そうすることで文章にリアリティが生まれ、採点者に「実務感覚を持っている」と伝わります。
そして可能であれば、第三者に読んでもらうことをおすすめします。
自分では良いと思った表現も、他人から見ると伝わりにくいことはよくあります。
論文添削サービスなどを活用すれば、プロ講師から具体的なアドバイスを受けられ、短期間で改善できます。
結局のところ、論文試験は「一度で完璧に仕上げる」ものではなく「小さな工夫の積み重ね」で合格に近づく試験です。
ぜひ今日から、自分の言葉で冒頭と結論を練習してみてください。
- 書き出しは「背景+問題提起+方向性」を示すことで信頼感を与える
- 結びは「提案+効果」や「リーダー視点」で締めると管理職らしさが伝わる
- スキマ時間を使って「冒頭・結論だけ練習」することで表現の幅が広がる