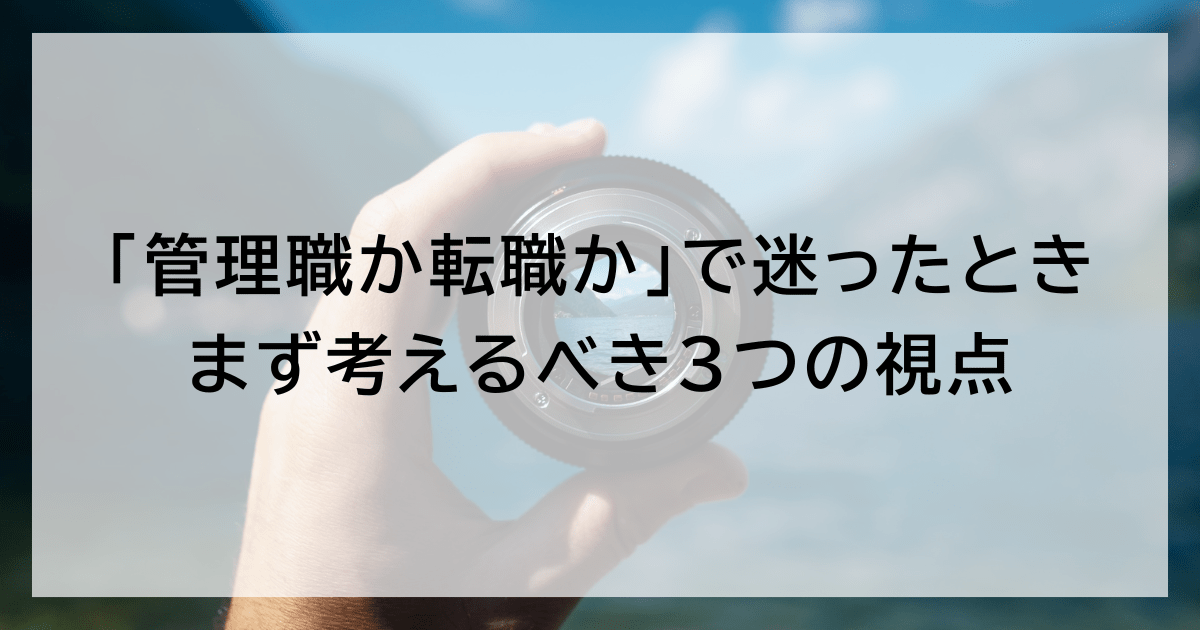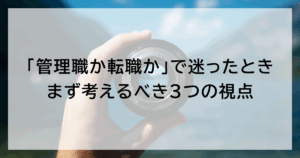「このまま今の会社で管理職を目指すべき? それとも思い切って転職すべき?」
そんな問いに心が揺れるのは、責任ある立場で頑張ってきたからこそ。
そして40代という節目に差し掛かると、これまでのキャリアの延長線ではなく、「これからの自分」にとって本当にふさわしい働き方を考えたくなるものです。
この記事では、焦らずに選択するために必要な「立ち止まる勇気」について深掘りしていきます。
あなた自身の本音に、いまこそ耳を傾けてみませんか?
- 管理職を打診されたが、自信がないし、家庭との両立も不安に感じている方
- 今の職場では女性管理職のロールモデルがいない方
- 転職も頭をよぎるが、年齢やキャリアがネックになりそうと思っている方
- 何を基準に判断すべきかわからない方
自分が「何を大切にしたいのか」を見つめ直す
迷いの根本には、「今後のキャリアや人生で何を大切にしたいか」がはっきりしていないことが多いものです。
ここでは、「働き方」「やりがい」「家庭とのバランス」「安心感」など、自分の価値観を整理するための簡単なワークや問いかけを通じて、判断の土台をしっかり整えるサポートをします。
あなたが今、最も大切にしたいものは?
「管理職を目指すべきか、それとも転職するべきか」
そんな悩みに直面するとき、まず立ち止まって考えてほしいのは、「自分は今、人生で何を一番大切にしたいのか」ということです。
私もかつては、周りの期待に流されてしまい、自分の気持ちが後回しになっていた経験があります。
結果的に、後から「これで良かったのかな?」と不安になってしまったこともありました。
たとえば、あなたは今、仕事において「キャリアアップ」を望んでいますか?
それとも「規則正しい生活と家族との時間の確保」が一番の優先でしょうか?
または「仕事にもっとやりがいを感じたい」「プライベートの時間を犠牲にしたくない」といった気持ちが強いかもしれません。
これらはどれも間違いではなく、どの選択もあなたらしさの表れです。
おすすめなのは「優先順位の棚卸しワーク」。
紙に書き出すのもスマホのメモを使うのも自由です。
たとえば「キャリア」「収入」「自由な時間」「家族との時間」「心の安定」「成長実感」といった項目を用意し、それぞれに1〜5の優先度をつけてみましょう。
私自身、これをやってみて、頭の中が整理されてスッキリした経験があります。
特に私たち女性は「全部頑張らなきゃ」と思い込みがちですが、このワークを通じて「今はここを大切にしよう」と自分に優しくなれるのも大きな効果です。
忙しい毎日だからこそ、ちょっと立ち止まって深呼吸し、「今の私の一番」を見つけることから始めてみませんか?
迷いの正体は「自分の本音」とのズレかもしれない
「管理職になるべきか、それとも転職か」と迷うとき、その迷いは実は選択肢の良し悪しではなく、「自分の本音としっかり向き合えているかどうか」がカギになっていることが多いのです。
たとえば「管理職を勧められたけれど、自分には向いていない気がする…」と感じるとき、それは本当に適性がないのか、それとも「失敗が怖い」「女性だから孤立しそう」という漠然とした不安がブレーキをかけているだけなのか、すぐにはわからないもの。
私も、そうした不安に振り回されて、なかなか決断できなかった時期がありました。
逆に「転職したいけど年齢的に厳しいのでは?」と思い込んでいたものの、実際に求人情報をチェックすると意外とマッチする仕事があったという経験も。
こうした「不安」は、社会の固定観念や過去の経験、周囲の声に左右されていることが多いのです。
たとえば「女性管理職は孤独」「転職はキャリアのリスク」というイメージは、必ずしも今の現実を反映していません。
だからこそ、まずはその不安やモヤモヤに名前をつけて、「それは本当のこと? それとも思い込み?」と自分に問いかけてみましょう。
私もノートに書き出してみて初めて、自分の不安が過剰だったと気づいたことがあります。
「家庭との両立が難しいかも」という不安なら、具体的に何がネックなのか、誰の言葉や経験が影響しているのかを探ってみてください。
少しずつ本音に向き合うことは怖いけれど、それができたら、未来の自分がずっと楽になります。
次は、管理職という選択肢をよりリアルに捉えるためのポイントをご紹介します。
自分の選択をもっと納得のいくものにするために、一緒に見ていきましょう。
「管理職になる」とはどういうことかを現実的に捉える
「管理職って大変そう…」そんな漠然とした不安、実は私たちの多くが感じているものです。
責任の重さや家庭との両立など、心配になるのは当然。
でも、そのイメージだけで判断してしまうのは、ちょっともったいないかもしれません。
ここでは、管理職の「リアル」を、メリットと負担の両面から整理しながら、自分に合うかどうかを見極めるヒントをお届けします。
管理職になるメリットと「得られるもの」
「管理職」って言葉を聞くと、どんなイメージが浮かびますか?
「重圧がすごそう…」「家のことと両立できるの?」そんな声が聞こえてきそうですが、実は私自身、そう思っていた一人です。
でも実際に管理職になってみて感じたのは、想像していた以上に「得られるもの」が多かったということ。
もちろん大変なこともありますが、その分だけ得られる景色も、手応えも変わってきます。
たとえば、真っ先に実感したのが「発言の重みが増す」こと。
以前は、会議で何か提案しても「ふーん」で終わっていたのに、管理職になると「それ、やってみよう」と即実行に移ることも増えました。
あのときの、チームの目がキラッと輝いた瞬間は、今でも忘れられません。
そしてやっぱり現実的な話としては、「収入が上がる」ことも見逃せません。
特に、子どもの進学や住宅ローンなど、これから大きなお金が動く年代にとっては、昇給や賞与の変化は家計の安心材料になります。
さらに、管理職経験があると、将来の選択肢がグッと広がります。
たとえば他社でのマネジメント職にチャレンジしたり、ゆくゆくは起業という道も見えてくる。
今はまだピンとこないかもしれませんが、「あ、自分にもそういう可能性があるんだ」って気づくだけで、キャリアの景色が少し変わってくるんです。
それに、社内外の人とのつながりが一気に増えるのも、意外とうれしいポイント。
部署を超えたプロジェクトや社外とのやりとりが増えて、「あ、自分の仕事って、こんなふうに社会とつながってるんだな」って実感できるようになります。
もちろん、いいことばかりではありません。
でも「自分の中にある可能性」に光を当てられるのが、管理職の大きな魅力。
では、その一方で覚悟しておきたい「リアルな負担」についても、次で正直にお話ししていきますね。
想定される負担やプレッシャーも知っておく
さて、メリットを知ったら、今度は「じゃあ、どれくらい大変なの?」という点にも目を向けてみましょう。
管理職になってまず多くの人が直面するのは、「時間の使い方がガラっと変わる」ことです。
部下の相談、会議の準備、トラブル対応…と、1日のスケジュールは分刻み。
私も最初のころは、「保育園のお迎えに間に合わない!」「夕飯、今日も冷凍…」と、何度も慌てました。
さらに、「責任の重さ」が、思った以上に心にのしかかる瞬間もあります。
「チーム全体の成果は自分の責任」
「失敗したら自分が謝る」
そんな立場になると、プレッシャーがぐっと高まります。
時には、夜中にふと目が覚めて、「あの判断、本当に良かったのかな…」と考え込んでしまうこともありました。
とくに女性の場合、「管理職としての責任」だけでなく、「母親としての役割」や「妻としての役割」にも気を配っている方が多く、知らず知らずのうちに心身のバランスを崩してしまうこともあります。
でも、だからこそ大事なのは「準備」と「相談できる相手の存在」です。
「ロールモデルがいない」「残業が多そうで不安」と感じているなら、あらかじめ上司や人事に相談するのも立派な選択肢。
人事の仕事をしている立場から言うと、「言ってくれたら、もっと配慮できたのに…」と思うことは意外と多いんです。
また、「どんな負担なら耐えられるのか」「ここだけは譲れない」という自分の「境界線」を知っておくこともとても大切です。
プレッシャーに燃える人もいれば、穏やかさを何より大事にしたい人もいますよね。
どちらが正解でも不正解でもありません。
あなたの「ちょうどいいバランス」を見つけてあげてください。
最後にひとつだけ。
「大変そうだからやめておこう」ではなく、「自分が前向きに進むために、何が必要か」を考えてみてください。
備えがあるだけで、選択肢はぐっと広がります。
次は「女性管理職が少ない職場」で感じる、あの独特のプレッシャーや不安について、一緒に掘り下げてみましょう。
「女性管理職が少ない会社」でどう考える?
「この会社で、女性が管理職になれる未来なんてあるのかな…」
そんな不安を、面談の帰り道でぽつりと口にした後輩の言葉が、今も忘れられません。
私自身もかつて、似たような疑問を胸に抱えながら働いていました。
でも――「女性管理職が少ない」からといって、それだけでネガティブに捉える必要はないんです。
大切なのは、その背景を見極めたうえで、「自分はどうありたいか」を考えること。
その視点次第で、未来は大きく変わります。
まず知っておきたいのは、女性管理職が少ない会社には、ざっくり2つのタイプがあるということ。
ひとつは、制度や文化そのものがまだ男性中心にできている会社。
たとえば、上層部に女性が一人もいなかったり、育児支援制度があっても誰も使っていなかったり。
こうした環境では、「育児と両立しながら管理職なんて無理」と感じてしまうのも無理はありません。
もうひとつは、制度は整っているけれど、「前例」がない会社。
制度も支援もあるのに、なぜか女性がその一歩を踏み出していない。
あるいは、「上の人に女性がいないから自信が持てない」と足踏みしている状態かもしれません。
この2つ、似ているようで大きく違います。
前者は「仕組みそのものが壁」になっている会社。
後者は、「最初の一人になることに勇気が必要なだけ」というケースも多いんです。
では、自分の会社はどちらのタイプなのか、どう見極めればいいのでしょう?
それには、会社が「本音で」女性管理職をどう考えているかを観察するのが一番。
たとえば…
- 育児や介護との両立支援制度は「名ばかり」ではなく、実際に利用されているか?
- 管理職や役員に女性が何人いるか?
- 面談で「将来的に管理職を目指したい」と言ったとき、どんな反応が返ってくるか?
こうした「空気感」を読み取ることがヒントになります。
口コミサイトの情報や、社外の知人の話も参考になるかもしれませんね。
「でも、私が『最初の女性管理職』になったら、きっと孤独だし、大変そう…」
そう感じる方もいると思います。
実際、ロールモデルがいない環境で挑戦するのは、勇気が要ることです。
けれど、今は外部のつながりも以前よりずっと豊かになっています。
たとえば、女性管理職向けのオンラインコミュニティや研修、SNSを通じたつながりなど、視野を広げれば味方は意外とたくさん見つかるものです。
私も、社内に相談相手がいなかった頃、同じような悩みを抱える女性とSNSでつながったことが、どれほど心強かったか。
「一人で全部抱えなくていい」という感覚があるだけで、前を向けることもあるんです。
そして、もうひとつ大切にしてほしいのが、「その会社で、自分はどう働いていきたいか」という視点。
「女性管理職第1号として、風を起こしたい!」という人もいれば、「無理せず、自分らしいペースでキャリアを築きたい」という人もいる。
どちらも、立派なスタンスです。
ただし、会社の文化や価値観と、自分の「これから」があまりにもズレていると、しんどくなってしまう。
たとえば、「残業当たり前の風土」や「育児は女性がするもの」という空気感に、自分の考え方が合わない場合、そのズレがじわじわとストレスになっていくことも。
だからこそ、自分の価値観を再確認するチャンスだと思ってみてください。
どんな環境に身を置くかは、自分の人生をどうデザインしたいかによって変わります。
「女性管理職が少ない会社」——そこには、課題もあるけれど、可能性もたくさんあります。
今の職場で未来を描くのか、新しい環境に飛び込むのか。
それを決めるときに、この視点があなたの「軸」になるはずです。
さて、ここまで「管理職になる」「転職する」それぞれの選択肢について、現実的な視点から整理してきました。
でも、いちばん大切なのは、焦らず、一度立ち止まって「自分がどう生きたいか」を見つめること。
次は、その「立ち止まる勇気」について、もう少しだけ一緒に考えてみましょう。
「転職」という選択肢の現実と準備
転職は「人生の再スタート」のように感じられるかもしれません。
でも、実際にはメリットもデメリットもあります。
とくに30〜40代の女性にとっては、「希望の働き方ができるのか?」「年収は維持できるのか?」「今より後退しない?」と、気になることは山ほどあるはず。
この記事では、現実的な転職市場の動きと、自分の「強み」をどう見つけるか、そして後悔しないための準備について、等身大の視点からご紹介します。
転職で得られるもの・失うかもしれないもの
「もう限界かも。このまま続けるより、転職したほうがいいのかもしれない」
そう思った夜、私も何度かスマホ片手に転職サイトを開いたことがあります。
目に飛び込んでくる「年収アップ」「リモートOK」「女性管理職活躍中!」――そんな言葉に、一瞬、希望が灯る。
でも、その先に何が待っているのか。不安もつきまといますよね。
転職の一番の魅力は、やっぱり「環境を変えられる」ということです。
たとえば、残業がほとんどなくなったり、在宅勤務ができたり。
中には「こんなに気持ちよく働ける職場があるなんて!」と感じる人もいます。
また、今までの経験を武器に、キャリアアップや年収アップが叶うケースもあります。
実際、私の友人は、リーダー経験を評価されて、前職より年収が100万円以上アップしました。
でも、転職は「ゼロからのスタート」でもあります。
前の職場で築いてきた信頼関係、職場の空気感、ちょっとした暗黙の了解――そういうものは、新しい職場では通用しません。
最初は名前も顔も知らない環境に飛び込み、「私はこういう人間です」と一から伝えていく努力が必要になります。
また、前職では「当たり前に任されていた仕事」が、新しい環境では任されないことも。
自分の力を発揮するまでに、時間がかかることもあるのです。
特に30〜40代になると、子育てや親の介護など、ライフイベントと重なる時期でもありますよね。
だからこそ、「転職で本当に得たいもの」を明確にすることが、とても大切です。
たとえば、「今の自分は『自由な時間』を何より大切にしたいのか」「それとも、『ポジションや裁量』を重視したいのか」――それによって、選ぶべき道は変わってきます。
転職は、決して魔法の杖ではありません。
でも、自分の人生にとって意味のある一歩になる可能性は、十分にあります。
では、その一歩をどう踏み出すのか。
次は、「自分の市場価値」を知るためのヒントを見ていきましょう。
自分の「市場価値」を知るには?
「転職してみたいけど、そもそも私に声がかかる求人なんてあるの?」
そんなふうに、自信を持てないでいる方、多いのではないでしょうか。
私自身も、「この年齢で…」「育休でキャリアが空いたから…」と、いろいろな「足かせ」を勝手に感じていました。
でも、最近は「スカウト型」の転職サービスが増えていて、予想以上に「需要がある自分」に出会えることがあります。
たとえば、ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトなどに登録すると、匿名で自分の職務経歴を公開し、それに興味を持った企業から直接スカウトが届く仕組み。
自分の希望を出さなくても、「こんな企業が私に興味を持ってくれるんだ」と知るだけで、自信につながることがあります。
もうひとつ大切なのが、「職務経歴の棚卸し」です。
いざ転職活動を始めようと思っても、「何を書けばいいかわからない…」となることが多いですよね。
そんなときは、これまでの実績を紙に書き出してみるのがおすすめです。
たとえば、「同時にいくつの案件を回していたか」「どんな工夫でチームをまとめたか」「提案がどう成果につながったか」など、できるだけ具体的に。
そして、可能であれば、信頼できる上司や同僚、あるいはキャリアコンサルタントに、「私の強みって何だと思いますか?」と聞いてみてください。
自分では当たり前にやっていたことが、実は「それすごいね」と評価されることもあります。
こうして、自分のことを「他人の目線」で見てみると、意外と「市場価値って、ちゃんとあるんだ」と気づける瞬間があります。
それでもやっぱり、年齢の壁や家庭の事情が気になる…という方もいるでしょう。
だからこそ、次は「40代以降のキャリア設計」について、もう少し踏み込んで考えてみたいと思います。
40代以降の転職で大切にしたい視点
「もう40代。転職なんて遅いのかも…」
「今の職場にもやもやはあるけれど、新しい場所で本当にやっていけるのか、不安で踏み出せない」
そんな声を、私自身も、そして周囲の同世代の女性たちからもよく耳にします。
けれど、率直に言って——40代以降の転職は「遅い」どころか、「再スタートの絶好のタイミング」でもあります。
ポイントは、焦らず、そして準備と視点を少し変えること。
そうすれば、年齢を重ねたからこそ見えてくる景色があるんです。
「スキル」よりも、「姿勢」や「柔軟性」が問われる世代
40代の転職では、「どんなスキルを持っているか」だけでなく、「どんな姿勢で働けるか」「どんなチームプレイヤーか」が評価されるようになります。
たとえば、20〜30代の頃は、「実務能力」や「成果」が前面に出る傾向がありましたが、40代になると、企業が求めるのは「即戦力」でありながら、「協調性」や「適応力」もある人材。
これは、まさに人生経験を積んできた私たち世代の強みでもあります。
「年下の上司とどう関係を築くか」といったリアルな課題に直面することもあるでしょう。
そんな時は、「年齢=プライド」ではなく、「経験=懐の深さ」として柔らかく関わる姿勢が、結果的に信頼を生みます。
5年後・10年後の「自分の暮らし」を想像してみる
今のあなたが大切にしているものは何でしょうか?
子育てが一段落した人もいれば、親の介護や自身の健康に目を向け始めた人もいるかもしれません。
だからこそ、転職を考えるなら「今すぐの条件」だけでなく、「これから先の暮らし」を見据えてみてください。
たとえば、
- 「子どもが独立したあとは、もう一度バリバリ働きたい」
- 「家族との時間を優先しながら、週3〜4日ペースで柔軟に働きたい」
- 「地方に移住してリモートで仕事を続けたい」
こんなふうに、自分の「未来の理想」から逆算してキャリアを考えることが、後悔のない選択につながります。
「目に見えにくい強み」を棚卸しする
これまでのキャリアで得てきたものは、履歴書に書けるような「肩書」や「役職」だけではありません。
たとえば、
- トラブルを穏やかにおさめたコミュニケーション力
- 後輩を育てる中で育んだ信頼関係
- 部署間の板挟みを何度も乗り越えた「調整力」
これらはすべて、あなたの唯一無二の「武器」です。
けれど、自分では意外と気づきにくいもの。
そんなときは、キャリアコーチや転職エージェントに相談して、第三者の視点から棚卸しをしてみるのもおすすめです。
「あ、それも強みなんだ」と気づけた瞬間、ちょっとだけ自分を好きになれるかもしれません。
焦りが生む「転職の落とし穴」にご注意を
「もう限界、早く今の職場から抜け出したい」と思う気持ち。
痛いほどわかります。
私もそうでした。
けれど、その焦りが判断を鈍らせてしまうこともあるんです。
「思っていた職場と違った」
「年収は上がったけれど、心がすり減っている」
そんなふうに、転職したあとで再び悩みがぶり返すことも。
特に40代以降は「次の転職」が難しくなるケースもあるため、慎重さと前向きさのバランスを意識することが大切です。
「正社員だけが正解」ではない。選択肢はもっと広がっている
今は、副業やリモートワークなど、柔軟な働き方が少しずつ当たり前になりつつある時代です。
「フルタイムで朝から晩まで働く」以外の選択肢が、現実味を帯びてきました。
たとえば、
- フリーランスとして専門スキルを活かす
- 週3日勤務の時短正社員
- 複業として複数の会社と関わるワークスタイル
「私にはこのスタイルがちょうどいい」
そんな働き方を選ぶことが、これからの時代の「スタンダード」になっていくかもしれません。
40代以降の転職は、「再出発のスタートライン」
大丈夫。
あなたのキャリアは、まだまだこれからです。
これまで積み上げてきた経験も、失敗も、喜びも、すべてがあなたの「土台」になります。
そこに、自分自身の願いや価値観を丁寧に重ねていけば、40代以降の転職は「再構築」ではなく「新しい自分の物語」の第一章になるのです。
次は、これまで考えてきた「管理職か転職か」の迷いに、どんな視点で向き合うと自分らしい決断ができるのか、一緒に考えていきましょう。
管理職か転職か ——決める前に「立ち止まる」ことの意味
焦って決断を下すのではなく、一度深呼吸して「自分はどう生きたいのか」に立ち返る時間を持つこと。
それが、後悔のない選択への近道です。
キャリアの棚卸しワークや信頼できる人との対話などをご紹介します。
「管理職になるべき? それとも転職した方がいいの?」
その問いが頭の中をぐるぐる回って眠れなかった夜、私もありました。
周りはどんどん昇進していくし、同年代の友人は新天地で活躍していたりして、「このままでいいのかな?」と焦ってしまう。
40代に差しかかると、そんな葛藤がふとした瞬間に顔を出しますよね。
でもね、焦って出した結論は、あとから「本当にこれでよかったのかな」と引っかかることが多いものです。
だからこそ、まず最初にやってほしいのが、「立ち止まる」こと。
たとえるなら、分かれ道に立ったときに、地図も見ずに歩き出すより、ちょっと腰を下ろして、風の向きや足元の道を確かめるような時間です。
そもそも、なぜ「立ち止まる」ことが大切なのでしょうか?
それは、正しい判断をするには、まず「自分の本音」を見つけることが必要だからです。
毎日、仕事に追われ、家庭にも責任があり、周りからの期待も背負っていると、「私、本当はどうしたいの?」という気持ちがどこかに置き去りになってしまいがち。
だけど、心の奥のざわつきって、実は「これでいいの?」というあなたの直感からのサインだったりするんです。
そんなときは、ぜひこんな問いかけを自分にしてみてください。
- これまでの仕事の中で、どんな時に心からやりがいを感じた?
- 自分らしく働けていたと感じた瞬間って?
- 逆に、心がすり減ったのはどんなときだった?
この振り返りは、まるで引き出しの奥に眠っていた「自分らしさ」をそっと取り出す作業です。
私は実際にノートに書いてみたのですが、意外にも「人を支える役割に喜びを感じていた」ことに気づき、転職の際の軸になりました。
もうひとつ大切なのは、「ひとりで抱え込まないこと」。
信頼できる人——たとえば、旧友や同僚、あるいは家族など——に、ただ話してみるだけでも、気づきが生まれます。
「答えをもらう」のではなく、「考えを整理するために話す」。
このスタンスがポイントです。
私は、学生時代の友人に話したことで、「私は『がんばりすぎ』てたのかも」と気づかされ、気持ちがスッと軽くなった経験があります。
また最近では、オンラインで気軽に相談できるキャリアカウンセリングやコーチングサービスも増えてきました。
ちょっと前なら「相談する=弱さ」なんて思われがちでしたが、今は「自分を見つめ直す強さ」としてポジティブに受け止められる時代です。
私も一度キャリアコーチと話したことで、自分の価値観や強みを客観的に整理できました。
こうして「立ち止まる時間」は、キャリアだけでなく、これからの生き方全体を見直すきっかけにもなります。
何を大切にしたいのか、どう働いて、どう暮らしたいのか。
その答えは、周りではなく、あなた自身の中にちゃんとあります。
次は、ここまで考えてきたことを整理しながら、自分に合った道を選ぶための「まとめ」と「今日からできる3つのアクション」をご紹介します。
気持ちのモヤモヤは、少しずつ輪郭を持ちはじめています。
あとは、それに名前をつけて、一歩踏み出すだけです。
まとめ:どちらの道も、あなたらしく選んでいい
管理職になることも、転職することも、どちらが「正解」というわけではありません。
ここでは、自分にフィットする選択をするための考え方と、「今すぐできる3つの行動」を提案します。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
きっとあなたは今、キャリアの大きな分かれ道に立っていて、その分、たくさん考えたり、迷ったりしてきたのだと思います。
その姿勢自体が、すでに「あなたの未来への投資」です。
結論から言えば、管理職になることも、転職することも、どちらも間違いではありません。
どちらの道にも良さがあり、難しさもあります。
大事なのは、他人の期待や周囲の評価に振り回されることなく、「自分にとってどうありたいか」という軸を持つこと。
管理職として、組織の中でリーダーシップを発揮していく未来も素敵ですし、環境を変えて、新しい業界や職場で自分を試してみる転職もまた、大きなチャレンジです。
不安がゼロになる日は来ないかもしれません。
でも、不安の奥には、あなたの「こうありたい」という願いがあるはず。
その気持ちを大切にしてあげてください。
そして、ここからは「あなたらしい選択」をするために、今すぐできる3つの小さなアクションをご提案します。
- 価値観を見える化するワークをやってみる
ノートでもスマホのメモでもOKです。
「私がこれからも大事にしたいものベスト5」を書き出してみてください。
仕事の内容、働く場所、人間関係、家庭とのバランス…。
頭の中のモヤモヤが、言葉にすることでスッキリ整理されていきます。 - 誰かと「今の気持ち」を言葉にしてみる
話すことで、意外なほど自分の本音に気づけることがあります。
決して「答えをもらう」必要はありません。
「ちょっと聞いてもらえる?」そんな感じで、心を開ける相手に話してみてください。 - 外部のサポートを活用する勇気を持つ
キャリアカウンセリングや、自治体が提供している無料の就労支援もあります。
プロの視点からフィードバックをもらうことで、思いもよらない可能性が見えてくることも。
最後にお伝えしたいのは、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらが私らしいか」で選んでほしいということ。
これから先の人生も、仕事も、あなた自身のもの。
どんな道を選んでも、そこに「納得」と「希望」があれば、きっと大丈夫です。
あなたが誇りをもって進める選択ができるよう、心から応援しています。