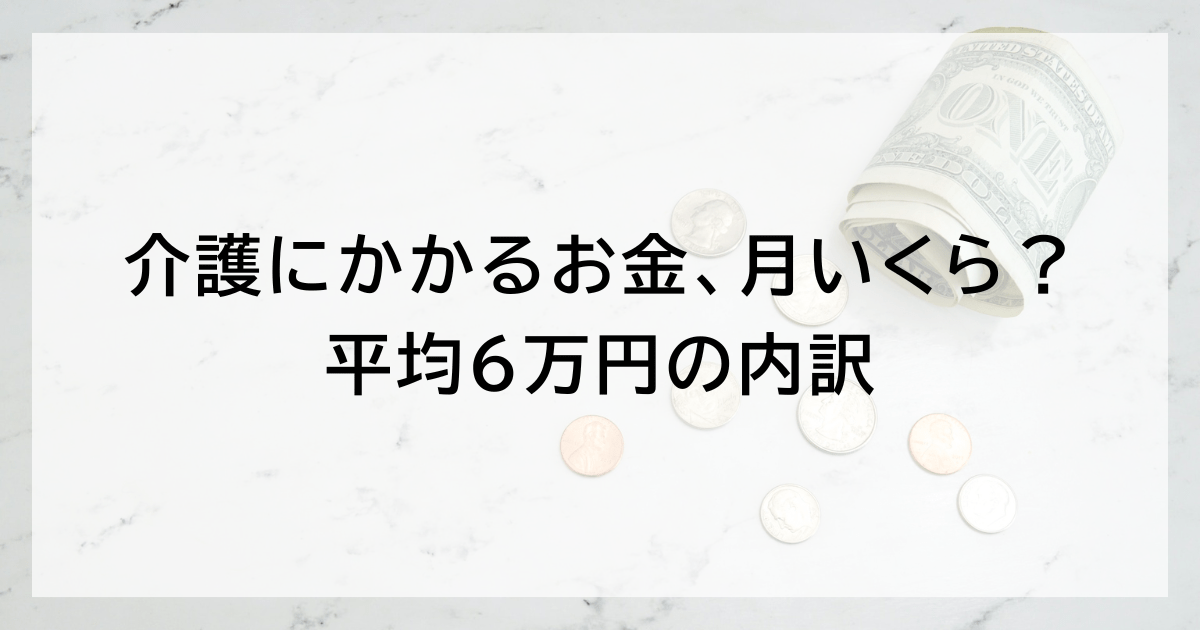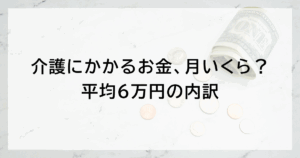「介護が突然始まったら、どうしたらいいの?」
そんな不安を、あなたも感じたことはありませんか?
私も母が急に体調を崩したとき、何から手をつけていいのか分からず途方に暮れました。
一方で、少しずつ準備を進めることで、こんなに心が軽くなるんだと実感したんです。
この記事では、親が元気なうちからできる「お金の備え」について、家族の気持ちに寄り添いながら具体的にお伝えします。
あなたにとっての安心への第一歩を、一緒に踏み出してみませんか?
- これから介護に関わるかもしれないと感じている方
- 介護が現実味を帯びてきて「費用の全体像」を知りたい方
- いざという時の備えとして「月いくらかかるのか?」を把握したい方
介護にかかるお金、月平均6万円の意味とは?
「介護にかかるお金は、月にだいたい6万円くらい」
そんなデータを目にすると「思ったより高い…」と感じる人もいれば、「あれ? 意外と少ない?」と拍子抜けする人もいるかもしれませんね。
私も最初にこの数字を聞いたとき、正直どちらの感情もわきました。
でも実際に親の介護を身近に感じるようになってから「この6万円って一体どういう意味なんだろう?」と疑問が湧いてきたんです。
結論から言うと、この「6万円」という数字は、あくまで平均的な在宅介護のケースをもとにした金額です。
厚生労働省などの公的データに基づいていますが、実際の暮らしの中では、その額だけで済むケースはそう多くありません。
たとえば、親が元気なうちは週に何度かデイサービスを利用したり、ヘルパーさんに来てもらったり。
そのくらいであれば自己負担額は比較的抑えられますが、状態が変わって通院が増えたり、入浴の介助が必要になったりすると、一気に負担が増えていきます。
さらに施設入所となれば、その月額は10万円〜20万円を超えることもめずらしくありません。
6万円というのは、ほんの「入り口の数字」と言えるかもしれませんね。
では、6万円には何が含まれているのでしょうか?
主な内訳は、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスにかかる利用料(自己負担分)、福祉用具のレンタル代、そしておむつや日用品、通院に伴う医療費など。
いわば「毎日の暮らしを支えるための小さな積み重ね」がこの金額です。
そして「介護保険があるから安心」と思っている方にもお伝えしておきたいのが、公的介護保険制度の仕組み。
原則として、サービス利用料の1割(一定の所得がある場合は2〜3割)を自己負担するルールになっています。
たとえば月に10万円分のサービスを受けた場合、自己負担は1万円〜3万円になります。
「じゃあ残りの金額はどこから?」というと、それ以外の生活費や医療費、食費などはすべて実費。
しかも、こうした「見えにくい支出」が意外と大きく、知らないうちに家計を圧迫していくのです。
さらに「誰がそのお金を負担するのか」も大きな課題です。
理想は親の年金や貯蓄からの支払いですが、すべてをまかなうのが難しいケースも増えています。
実際、親の生活費や施設代の一部を子どもが肩代わりしているご家庭も少なくありません。
私の友人も「気づいたら自分のパート代がほとんど親の介護に消えてた」なんて、ぽつりと漏らしていました。
それでは「実際にどのくらい備えておけば安心なの?」という問いに答えるなら──
在宅介護中心であれば、月5万〜8万円程度。
施設介護まで視野に入れるなら、月15万〜25万円ほどは見ておいたほうがいい、というのが現場の肌感覚です。
このように「月6万円」という数字は一見わかりやすいようで、実はとても幅があるもの。
親の健康状態や希望、どんなサービスを使うかによって、必要な費用は大きく変わってきます。
だからこそ、「平均だけを見て安心しないこと」がとても大切なんです。
次は「実際にどんな介護サービスに、いくらくらいかかるのか?」という内訳を見ていきましょう。
数字の裏側にある「リアルな暮らし」を知ることで、あなた自身の備えも、少しずつ輪郭を持ち始めるはずです。
介護費用の内訳:どんなサービスに、どのくらい使っているの?
介護のお金って「だいたい月6万円くらい」と聞いても、それが何に使われているのかピンとこない方も多いのではないでしょうか。
私自身も、親の介護がちらつき始めたとき「6万円って、何にそんなにかかるの?」と正直、実感が湧きませんでした。
でもいざ調べてみると「あぁ、これも必要だよね」「たしかに、そこにもお金がかかるよね」と、ひとつひとつ納得せざるを得ない現実が見えてきました。
ここでは、介護費用の中でも特によく使われる項目を大きく3つに分けてご紹介します。
「うちはまだ先の話」と思っている方にも、きっと役に立つはずです。
まずは、在宅での介護を支えてくれる「訪問・通所系サービス」から見ていきましょう。
訪問・通所系サービス(デイサービス、ヘルパーなど)
在宅介護をしている家庭で、最も頼りにされているのがこの「訪問・通所系サービス」です。
私のまわりでも「親は家で過ごしたがってるし、できるだけ通いとヘルパーで…」という声をよく聞きます。
デイサービス
たとえばデイサービス。
日中だけ施設に通い、入浴や食事、リハビリなどを受けられるサービスです。
週2回の利用で、自己負担は月に9,000円〜15,000円程度。
1回あたり1,000円前後とはいえ、積み重なるとそれなりの金額になります。
ヘルパー
また、ヘルパーさんによる訪問介護も一般的です。
買い物の付き添いや掃除、食事の支度などをお願いできるのですが、これも1回あたり数百円から。
ただ、たとえば1日2回来てもらうと、月に1〜2万円程度は見ておいた方がいいかもしれません。
知人のひとりは「最初は週1で十分だと思ってたけど、親の体調が不安定になって、気づけば週3に…」と話していました。
費用は確かにかさみますが「誰かが見てくれている」という安心感は、お金には代えがたい価値があります。
次に、費用がぐっと上がる「施設介護」のケースを見てみましょう。
施設利用の場合(特養、老健、有料老人ホーム)
「いざとなったら施設に入れば安心」と思っていませんか?
その気持ちはよく分かります。
でも、実際には「どんな施設を選ぶか」でかかる費用が大きく変わってきます。
特養
たとえば、特別養護老人ホーム(特養)は公的施設なので、月額はおおよそ8万円から。
比較的手の届く金額です。
ただし、入所には要介護度の高さが求められ、希望者も多いため、地域によっては2〜3年待ち…なんてことも珍しくありません。
老健
介護老人保健施設(老健)は、医療とリハビリの中間的な位置づけ。
月8万〜12万円くらいですが、基本的には短期入所を前提としており、ずっと住み続ける場所ではないんです。
有料老人ホーム
一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅(いわゆる「サ高住」)のような民間施設になると、ぐんと費用が跳ね上がります。
月15万円〜30万円、場合によってはそれ以上。
入居時に数百万円単位の一時金が必要なところもあります。
「親がCMで見たあのホーム、気に入ってるみたい」と軽く思っていたら、実はとても高額な施設だった…という話もよく聞きます。
できれば一度パンフレットを取り寄せたり、家族で一緒に見学に行ったりして、現実とのすり合わせをしておくことをおすすめします。
では、次は見落としがちだけど地味に負担になりやすい「実費」の部分を見ていきましょう。
おむつ代・医療費・日用品などの実費
介護を始めると、思った以上に「保険のきかないお金」が出ていきます。
これがまた、地味に効いてくるんです。
おむつ代
たとえばおむつ代。
紙おむつ、尿とりパッド、肌に優しいタイプ…と選んでいくと、月に5,000円〜1万円はかかります。
うちの親も肌が弱くて、ちょっとでも合わないとすぐ赤くなってしまうので、こだわるようになりました。
医療費
次に医療費。
高齢になると何かしらの慢性疾患を抱えていることが多いので、通院や薬代もバカになりません。
訪問診療や訪問看護を受けている場合は、月に1万円以上になることもあります。
日用品
さらに、清拭用のウェットシート、口腔ケア用品、ティッシュやタオル、衣類の買い替え、デイサービスのお弁当代や交通費…こうした「日常の延長にある支出」も、意外と家計にのしかかってきます。
「気づいたら財布からお金がどんどんなくなってる」と母がぼやいていたのを思い出します。
家計簿に書くほどでもない細かなお金。
でも、そういう出費こそ、後から大きく効いてくるんですよね。
さて、ここまで見てきたように、介護にはさまざまな形の「お金」がつきもの。
でも、怖がる必要はありません。
次は「じゃあ、どう備えればいいの?」という視点から、一緒に考えてみましょう。
どんな介護スタイルかで、かかる金額はまったく違う
「介護にいくらかかるのか」と聞かれても、答えに詰まってしまう方が多いと思います。
実はこの答えは「どんな介護の形を選ぶか」によって大きく変わってくるんです。
介護には主に3つのスタイルがあります。
- 在宅介護+訪問サービス型
- 自宅+通所(デイサービス)併用型
- 施設介護型
それぞれ、金額だけでなく家族の心身の負担、安心感、親との距離感など、見えてくる風景がまったく違います。
私自身、親の介護について考えはじめたとき「お金のこと」よりも、「どんなふうに暮らしてもらうのがいいんだろう」と悩みました。
お金の話って、つい後回しになりがち。
でも、選ぶスタイルによってかかる費用は、数万円〜数十万円と大きく差があるのが現実です。
ここでは、それぞれの介護スタイルについて、月額の目安やメリット・デメリットを比べながら紹介します。
今すぐじゃなくても、将来「どうする?」と話し合うときの大きなヒントになるはずです。
在宅介護+訪問サービス型
「できるだけ家で過ごしてもらいたい」「目が届くところで見守ってあげたい」。
そんな想いから選ばれるのが、在宅介護に訪問サービスを組み合わせるスタイルです。
わたしの母も「父には、最後まで自分の家で暮らしてほしい」とよく言っていました。
このスタイルは、経済的な負担が比較的軽く、介護度がそれほど高くないうちは特に選ばれやすい方法です。
費用の目安としては、訪問介護(ヘルパー)を週に2〜3回利用した場合、月1万〜2万円ほど。
これにおむつ代や通院などの医療費を加えても、月3〜5万円くらいに収まることが多いです。
ただし費用は抑えられても、家族の負担は大きくなりがちです。
夜中にトイレの介助をしたり、休日に買い物や病院の付き添いをしたり…気づけば「自分の時間がなくなってた」という声も珍しくありません。
友人のひとりは、最初「親の介護くらい、私がちゃんとやらないと」と思っていたそうです。
でも半年経たないうちに、寝不足と疲労で倒れそうになって、思い切ってデイサービスを取り入れたと話してくれました。
「がんばりすぎない」という選択も、立派な介護のひとつ。
次は、そんな無理の少ないスタイルとして注目されている「自宅+通所型」を見ていきましょう。
自宅+通所(デイサービス)併用型
「親は家で暮らしたい。でも、ずっと一緒にいるのは正直しんどい…」そんな声に応えてくれるのが、デイサービスを取り入れたこのスタイルです。
具体的には、平日の昼間だけ通所施設で過ごし、夜や週末は自宅で家族と過ごすという形。
これなら介護する側の生活も保ちながら、親も安心して暮らせます。
費用は、デイサービスを週3回程度利用した場合で、自己負担が月1.5万〜2.5万円ほど。
これに医療費や日用品費を足すと、だいたい月5万〜7万円くらいが相場です。
メリットは何と言っても「1人で抱え込まなくていい」こと。
わたしの知り合いは「お昼だけでも見てくれるだけで、気持ちが軽くなる」と言っていました。
親も、施設でのレクリエーションやお風呂、栄養バランスの良い食事で、いきいきとした表情を取り戻したそうです。
ただし、デイサービスに最初から乗り気な親御さんは、正直あまり多くありません。
「知らない人ばかりで不安」「恥ずかしい」と抵抗を感じる方も。
そんなときは、見学や体験利用から始めるのがおすすめです。
実際、「行ってみたら楽しかった!」と、週1が週3になった例もたくさんあります。
では次に、介護そのものを施設に任せる「施設介護型」について見ていきましょう。
施設介護型(入所施設メイン)
「もう自宅では支えきれない」「見守りが24時間必要になってきた」
そんなタイミングで考えるべきなのが、施設介護です。
金額面で言えば、いちばん費用がかかるスタイルですが、そのぶん介護の安心感は圧倒的です。
自分の生活も守りながら、親の安全も確保したい…そんな願いを支えてくれます。
特別養護老人ホーム(特養)なら、月8万〜12万円ほどが相場。
民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)になると、月15万〜30万円が目安になります。
さらに、入居時に一時金として数十万〜数百万円を求められる施設もあります。
「そんなの、うちはムリ…」と思ってしまうかもしれません。
でも、経済的に厳しい家庭には、補助制度もあります。
「高額介護サービス費制度」や「補足給付」など、所得に応じて費用を軽減できる仕組みも用意されています。
まずは市区町村の窓口で相談してみるのがおすすめです。
それともうひとつ、大事なのが「情報の早めの確保」。
人気の特養などは入所待ちが1年以上なんてこともザラです。
「そろそろかも」と思ったら、資料請求や施設見学だけでも先に済ませておくだけで、心の余裕が違ってきます。
ここまで読んで、「うちはどのスタイルが合うんだろう…」と少し考えはじめた方もいるかもしれませんね。
次は、家族の状況や親の希望をふまえた「介護スタイルの選び方」について、もう少し深く掘り下げていきます。
無理なく、安心して、そして何より、後悔しない選択のために。
あなたにとって、そしてご家族にとっての「ちょうどいい介護」を一緒に考えていきましょう。
「うちに合う介護」はどう選ぶ? 無理なく続けるスタイルの見つけ方
介護スタイルを選ぶって、正解がないぶん、すごく悩ましいですよね。
「親の希望」「お金のこと」「自分の仕事や生活」「きょうだいとの関係」…考えなきゃいけないことが多すぎて、何から手をつければいいのかわからなくなることもあると思います。
でも、焦らなくて大丈夫です。
ここでは「介護のスタイルをどう選ぶか」について、押さえておきたいポイントを整理していきます。
いちばん大事なのは「無理せず続けられること」。
今の自分たちにとって、ちょうどいい介護を一緒に探していきましょう。
まずは「親の気持ち」を聞いてみる
スタートは、やっぱり親の気持ちを知ることから。
「できるだけ家で暮らしたいのか」「プロに任せたいのか」「施設に入るのは不安じゃないか」
聞きづらくても、まずは率直に会話してみることが大切です。
私の母は、ある日ぽつりと「できれば最後までこの家にいたいの」と話してくれました。
そのひと言が、わたしたち家族の介護の方向性を大きく左右しました。
気が進まなかったけれど、ちゃんと聞いてよかったと思っています。
普段の雑談の中でさりげなく「もし体が弱ったら、どうしたいと思ってる?」なんて聞いてみるのもおすすめです。
次に「家族の状況」を正直に見つめる
介護は「チーム戦」です。
だからこそ、家族全員の状況も整理しておきましょう。
たとえば…
- 誰がどれだけ時間を取れる?
- 仕事や子育てとの両立は可能?
- 自宅での介護に向いている間取りか?
- きょうだいで役割分担できそうか?
「理想の介護」だけで突き進んでしまうと、あとで心も体も疲弊してしまいます。
「今できること」「できないこと」を正直に把握することが、実は最も思いやりのある選択です。
お金のことは「ざっくり」でもいいから早めに確認
介護スタイルの選び方において、お金の確認は避けて通れません。
でも、いきなり細かく調べるのは大変ですし、ハードルも高いですよね。
まずは、ざっくりでもいいので下記のような項目をチェックしてみてください。
- 親の年金額(毎月の収入)
- 介護費用に使える貯蓄の目安
- 子ども世代がサポートできるか(+どこまで可能か)
- 必要があれば、公的支援制度の利用も視野に
「月6万円」といった平均値にとらわれすぎず、親の介護状態・希望するスタイルに合った費用感を調べることが大切です。
「一度決めたら変えられない」わけじゃない
介護のスタイルは、一度決めたら絶対そのまま…というわけではありません。
むしろ、体調の変化や家族の状況によって、柔軟に変えていくのが自然な流れです。
たとえば…
- 最初は在宅+訪問サービス → 徐々にデイサービスを追加
- 在宅が難しくなってきた → 一時的にショートステイを利用
- 施設介護へ移行 → 事前に見学・予約でスムーズに
介護は長丁場。
だからこそ「今できること」を積み重ねながら、無理せず更新していけばいいんです。
完璧を目指すより、変わりながら続けることの方がずっと大事。
「相談できる場所」を持っておこう
どうしても迷ってしまうとき、ひとりで抱えないことも大切です。
介護は「情報を持っている人がラクになる」面もあります。
たとえば、
- 地域包括支援センター(介護の総合窓口)
- ケアマネジャー
- 介護経験のある友人
「ちょっと話を聞いてもらおうかな」くらいの軽い気持ちでも大丈夫。
知識が増えることで、不安の正体が見えてきて、気持ちが軽くなることもよくあります。
チェックリスト:介護スタイルを選ぶ前に考えたい5つのこと
最後に、介護スタイルを考えるときに確認しておきたい項目を、チェックリスト形式でまとめました。
- 親の希望や不安を、直接または間接的に聞いたことがある
- 家族全体でのサポート体制(時間・場所・距離感)を共有できている
- 介護にかかる費用の目安を調べてみた
- 施設見学やサービス体験など、情報収集を始めている
- 誰かに相談する準備がある、または相談先を知っている
すべてに丸がついていなくても、大丈夫。
ひとつひとつ、少しずつ進めていくことが何より大切です。
いざというときに慌てない! 介護の備えは思っているよりシンプルです
「介護なんて、まだまだ先の話」と思っていたのに、ある日突然その日がやってくる——そんな経験をした人は、実はとても多いんです。
実際に始まってから、あわてて情報を調べたり、書類を探したり、お金の準備に追われたり…。
心も体も休まる間もなく、気がつけば自分自身が疲れ果てていた——なんて話もめずらしくありません。
私自身、母が急に倒れて入院したとき、まさにその状態でした。
「要介護認定ってどうやって申請するの?」「介護保険証ってどこにあったっけ…」と、病院の待合室でスマホ検索を繰り返しながら、頭の中はパニック。
大人になってから、あんなに心細かったのは久しぶりでした。
だからこそ、声を大にして言いたいんです。
「親が元気なうちに、ほんの少しでもいいから準備を始めておこう」と。
備えるといっても、難しいことではありません。
完璧を目指す必要はまったくないんです。
むしろ「ちょっとだけ知っておく」「必要なものを一箇所にまとめておく」——そんな小さなアクションが、いざというとき自分自身を助けてくれることになります。
たとえば、こんなことから始めてみませんか?
今からやっておくと安心なことリスト
□ 親の保険証券や年金に関する書類を、どこにあるか一緒に確認しておく
□ 要介護認定の申請の流れをざっくり調べてみる(市役所や地域包括支援センターのサイトなど)
□ きょうだいと「もしものとき、どう協力する?」と軽く話しておく
□ 親が通っている病院や薬局、担当医の名前・連絡先をメモしておく
□ 地元の地域包括支援センターの連絡先をスマホに登録しておく
これらの準備、すべて一気にやろうとすると大変ですが「今日は書類を探すだけ」「今週末に少し話すだけ」でも十分。
少しずつ積み重ねておくことで、いざというときの安心感がまるで違ってきます。
それから、もうひとつ大切なのが「親の気持ちを聞いておくこと」。
たとえば…
- 「最期まで家で過ごしたい?」
- 「施設に入ることはどう思ってる?」
- 「延命治療って…どうしたい?」
なかなか切り出しにくい話ではあるけれど、できれば元気なうちに、軽い雰囲気で話題にできると理想的です。
たとえば「この前テレビで介護の特集やってたよ。うちも少し考えておこうか?」とか、帰省のタイミングで、「ねえ、お母さん通帳ってどこにあるの?」と聞くだけでも立派な第一歩です。
まとめ:自分のペースで、でも少しずつ「お金のリアル」と向き合っていこう
「介護にはお金がかかる」と聞くと、ついドキッとして身構えてしまいますよね。
実際、月に5万円〜15万円、施設を利用すれば20万円以上かかるケースも少なくありません。
でも、それを聞いて「全部準備しておかなくちゃ」と焦る必要はありません。
大切なのは、「今できることを、できる範囲でやっておく」ことなんです。
私たちは、日々の暮らしの中で、仕事や家事、子育てや自分の健康など、もうすでにたくさんのことを抱えて生きています。
そのなかで、いきなり介護の準備まで完璧にやるのは、どう考えても無理がありますよね。
だからこそ、ちょっとずつ。
たとえば、今月は「書類の場所だけ確認する」、来月は「きょうだいと電話で話す」——それだけでも、備えはちゃんと進んでいきます。
そして何より大切なのは、「ひとりで抱えこまない」こと。
相談できる場所や人は、実はたくさんあります。
- 市区町村の「地域包括支援センター」
- ファイナンシャルプランナー(お金の相談役)
- 介護経験のある友人や知人
- SNSや本、新聞、テレビの特集番組も貴重な情報源
どこかに話すだけでも、気持ちがラクになったり、新しい視点を得られたりします。
- 「介護が始まってから」ではなく「今」から備えておくと安心
- お金の準備だけでなく、情報整理や家族との対話も大切
- 完璧を目指さなくてOK。今できることをひとつずつ
- 支援制度や専門家の力を借りて「自分を守る介護」を意識しよう
まずは、小さな一歩から。
「お母さんの通院先って、今どこだっけ?」
そんなさりげない問いかけが、未来の自分と家族を守る「最初の一歩」になるかもしれません。