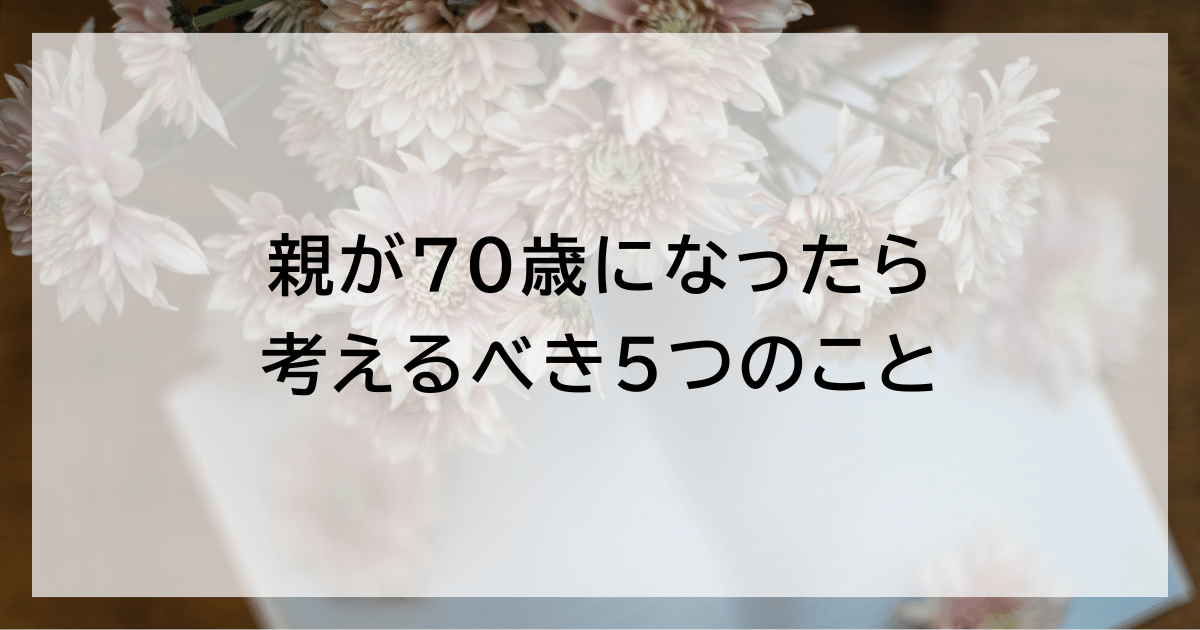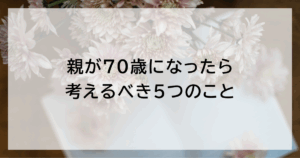「まだ元気だけど、そろそろ親のことをちゃんと考えなきゃ」
そんな気持ちがふと頭をよぎることはありませんか?
親が70歳を迎える頃は、見た目も気力もまだまだ元気。
でもその一方で、少しずつ身体の変化や暮らしの不安が重なってくる時期でもあります。
このタイミングこそ、介護やお金、住まいなどの「これから」について、そっと気づき、やさしく備え始める絶好のチャンス。
本記事では、今だからできる備えのヒントをお届けします。
- 親が70歳を超えたけど、何か備えた方がいい?
- 介護っていつから始まるの?
- お金の準備ってどうすればいい?
- 実家のこと、今のうちにどうしたらいい?
- 本人が元気なうちに何を話しておくべき?
親の「健康と暮らし」の現状を把握する
70歳を過ぎた親を目の前にすると、「まだまだ元気そうだな」と感じること、きっと多いですよね。
私自身、母が70歳を迎えたとき、ほとんど毎日散歩してるし、LINEの返信も早いし、正直「まだまだ先かな」と思っていました。
でも、ある日ふと気づいたんです。
「あれ、最近よく病院に行ってない?」「話がちょっとループしてる?」——。
なんというか、見た目には分からない「変化の始まり」みたいなものを感じたんです。
実はこの時期こそ、将来の備えをゆるやかに始める、絶好のタイミングです。
「大きなトラブルが起きてから」ではなく、「まだ何も起きていない今」だからこそ、冷静に、やさしく、親の変化に目を向けられる。
そう考えると、少し気がラクになりませんか?
もちろん「見守る」といっても、じっと観察したり、詮索したりするわけではありません。
あくまで「最近どうかな?」と、暮らしの中の変化にそっと気づいていく。
それだけで、いざというときに慌てずに済む、やわらかな安心が育まれていきます。
ここでは、まず「健康」と「日常生活」の2つの視点から、どんなことに気をつけておけばいいのか、一緒に見ていきましょう。
健康状態をゆるく観察するポイント
親の健康を見るときに、医師のような細かいチェックは必要ありません。
むしろ大切なのは「あれ?なんだか前と違うかも…」という「小さな違和感」を受け止めること。
その感覚が、未来の備えにつながっていきます。
たとえば、こんなポイントに注目してみてください。
通院の頻度や内容の変化
「この前も病院って言ってたな…」と思ったら、ちょっと聞いてみてください。
「最近どうしたの?」「薬、変わったりした?」とさりげなく話題にしてみましょう。
体調不良を本人が自覚していないこともありますし、自己判断で薬を増やしている場合も。
薬の飲み忘れや管理
「あれ、薬ちゃんと飲んでる?」と聞くと「大丈夫、大丈夫」と返されがちですが、ピルケースが溜まっていたり、飲み残しがあったりしませんか?
複数の病院にかかっていると、薬がかぶっていることもあるので注意が必要です。
認知機能のさりげないサイン
「さっきも同じ話、聞いたかも?」というようなこと、増えていませんか?
曜日や時間の感覚が曖昧になるのも、初期の兆候のひとつ。
でも責めずに、穏やかに。
話をそらさずに付き合うことで、自然と気づきが深まります。
生活リズムの変化
「朝早く目が覚めるようになった」「お昼寝が長くなっている」「食欲が落ちた気がする」——こうした「生活のズレ」にもヒントが隠れています。
遠方に住んでいると、こうした変化は見えにくいもの。
だからこそ月に1回でも電話をしてみる、帰省のタイミングで一緒に食卓を囲んでみる。
その中での会話や表情に、何か気づくことがあるかもしれません。
「あれ?」と思ったことを、すぐに「心配」に変える必要はありません。
ただ少しだけ気に留めておく。それだけで十分です。
その「やさしいアンテナ」が、未来の安心の土台になります。
次は、もっと日常の中にある変化のサインに目を向けてみましょう。
日常生活の変化をキャッチするチェック項目
健康状態と同じくらい、あるいはそれ以上に「変化」が見えやすいのが、毎日の暮らしぶりです。
介護が必要になる前には、実は日常の中に小さなサインが現れています。
以下のような項目、思い当たるものがあれば、そっと心に留めてみてください。
食事まわりの変化
最近、食欲がない様子はありませんか?
「料理が面倒」と言うようになったり、冷蔵庫の中が同じものでいっぱいだったり。
疲れや気力の低下は、ときにはうつのサインであることもあります。
家の掃除・片づけの様子
以前はきちんとしていた家が、少しずつ散らかっていたり、ホコリが目立つようになったり。
「掃除が追いつかない=体力が落ちている」こともあるんです。
洗濯物が溜まっていないか、ゴミ出しのタイミングが乱れていないかもヒントになります。
買い物やお金の管理
同じ商品を何度も買っている、レシートが山積み、光熱費の払い忘れ。
こうした変化があれば、認知機能や判断力に何らかの「揺らぎ」があるかもしれません。
外出や運転の頻度
「最近あまり出かけてないな」と思ったら、運転や歩行に自信をなくしているのかも。
出かけるのが億劫になるのは、心身のどこかに「ブレーキ」がかかっているサインです。
服装や身だしなみの変化
オシャレ好きだった親が、いつも同じ服を着ている。
髪が伸び放題、化粧をしなくなった…。
それは身体的な不自由さや、心の元気の低下を知らせていることもあります。
これらの変化は、LINEのやりとり、電話の声、何気ない会話からも気づくことができます。
「なんとなく気になったな」ということがあれば、スマホのメモ帳にポンと書いておくだけでも後から役立ちますよ。
大事なのは、気づいたことを「なかったこと」にしないこと。
深刻に受け止めなくてもいいんです。
でも見て見ぬふりをせずに、そっと見守る視点を持ってみてください。
次は、こうした「ゆるい見守り」の先にある、介護保険制度や要介護認定について、ご紹介していきます。
介護保険制度と要介護認定をざっくり理解しておく
「介護保険って聞いたことはあるけれど、正直よくわからないんです」
これは、私のまわりでもよく聞く声です。
制度の名前はなんとなく知っていても、実際にどうやって使うのか、どんなときに関わるのか——いざというときに戸惑ってしまう人は少なくありません。
でも親が70代に入ったら、介護保険が「まだまだ先」の話ではなく、「そろそろ視野に入れておきたい」ものになってきます。
あれこれ詳しく調べなくても大丈夫。
今のうちに「なんとなく」知っておくだけで、もしものときの安心感が、ぐっと変わってきます。
ここでは「要介護認定って何?」「申請ってどこにするの?」「使えるサービスにはどんなものがあるの?」といった基本のキホンを、専門用語に頼らず解説していきます。
それに加えて、意外と知られていない「元気な70代でも使えるサービス」についてもご紹介しますので、「うちはまだ関係ないかも…」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
それではまず「いざ」という時にあわてないための、介護保険制度の「入り口」から、一緒に見ていきましょう。
「いざ」というときのための基礎知識
介護保険制度とは、40歳以上のすべての人が加入している「公的なしくみ」です。
この制度があることで、将来もし親が介護を必要とする状況になったときに、必要な支援やサービスを自己負担1〜3割の範囲で受けることができます(※負担割合は所得により異なります)。
この制度のスタートラインとなるのが「要介護認定」です。
この認定を受けてはじめて、介護保険を使ってサービスを利用できるようになります。
じゃあその「要介護認定」って、どうやって受けるの? と思いますよね。
流れは次のようになっています。
- まず市区町村の介護保険担当窓口に申請します(本人でも家族でも、ケアマネジャーさんの代行でもOK)
- そのあと、市の職員さんが自宅を訪ねてきて、体の状態や生活の様子をチェック
- 同時に、かかりつけ医に診断書(意見書)を書いてもらいます
- 最後に「介護認定審査会」という専門家チームが、これらの情報をもとに認定レベルを決定します
認定の結果は「要支援1〜2」「要介護1〜5」という7つのレベルで通知されます。
通常は申請から約1ヶ月で届きます。
このプロセスを「なんとなくでも」知っておくと、もし親が急に入院したり、退院後の生活が不安になったときにも「まずは市役所に相談すればいい」と行動の糸口が見えてきます。
「でも、まだそこまでじゃないし、要介護って言われるのはちょっと…」と感じる方もいるかもしれません。
そんなときに知っておいてほしいのが、「要支援」というステップの存在です。
これは「介護が必要なほどではないけれど、ちょっと助けがあるとラク」という段階で利用できるサービスです。
たとえば掃除や買い物のお手伝い、転倒防止の運動、見守り訪問など、暮らしの中の「ちょっと困った」をサポートしてくれる内容が中心です。
「まだ大丈夫」は、「今ならゆるく始められる」タイミングでもあります。
制度は「人に迷惑をかける」ものではなく、長年支払ってきた保険料で「自分と家族の安心を買う」ようなもの。
その視点を持っておくと、使うことへの抵抗感がぐっと減ってきます。
次は、実際に70代の親世代が使い始めることが多い、身近な介護保険サービスを見ていきましょう。
70代で使われ始める意外なサービス
介護保険と聞くと、寝たきりや認知症のイメージが強くて「うちはまだ関係ない」と思っていませんか?
でも実は、介護保険のサービスって、元気なうちから「ちょっと手助けがほしいとき」にも使えるんです。
たとえば、
デイサービス(通所介護)
これは週に何回か施設に通って、入浴や食事、体操、レクリエーションなどを受けられるサービス。
ご本人にとっては外出のきっかけにもなり、社会とつながる時間にもなります。
家族にとっても「その間に買い物や病院に行ける」といった意味で、実は大きな支えになります。
ショートステイ(短期入所)
数日から1週間ほど施設に泊まるサービスです。
家族が旅行や出張で不在になるときや、ちょっと疲れてリフレッシュしたいときにも利用できます。
「いきなり施設に入るのは不安…」という親にとって、お試し体験にもなります。
訪問介護・訪問看護
ヘルパーさんや看護師さんが自宅に来てくれて、掃除・調理・お風呂・通院の付き添い・薬の管理などを手伝ってくれます。
「できるだけ自宅で暮らしたい」という親の気持ちを叶えながら、無理なく生活を続けられるよう支えてくれる頼もしい存在です。
福祉用具のレンタル
介護ベッド、手すり、歩行器などが必要になったときにすぐ借りられる制度です。
「使うのはまだ先」と思っていても、早めに手すりをつけて転倒を防いだり、体力を温存したりするために導入する方も増えています。
これらのサービスを利用するには「要支援」または「要介護」の認定が必要ですが、費用は原則1〜3割の自己負担で済みます。
「でも、どれをどう使えばいいの?」と不安になりますよね。
そんなときは、ケアマネジャーという介護の専門家に相談すると、今の状態や希望に合ったサービスを一緒に考えてくれます。
市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどにご相談を。
介護の入り口に立った70代は、不安や責任が重くのしかかる時期…ではありません。
むしろ「必要なときにちゃんと助けがある」安心感を知ることで、心がふっと軽くなる、そんな時期かもしれません。
次は、こうした制度やサービスを支えるうえで欠かせない「お金のこと」を一緒に見ていきましょう。
「誰がどのくらい負担するの?」という、ちょっと聞きにくい話にも触れていきます。
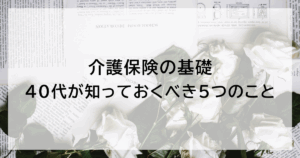
お金のことを「ぼんやり」から「なんとなく」把握へ
「介護って、結局いくらかかるの?」
この問いに、はっきり答えられる人は少ないかもしれません。
私自身、最初は見当もつかなくて、不安ばかりが先に立っていました。
お金にまつわる話って、なんだかモヤモヤしていて、手をつけづらいものですよね。
特に、親のお金のことになると「ちょっと聞きづらいな」と感じる方も多いと思います。
でも「完全に理解しなきゃ」と身構える必要はまったくありません。
むしろ、「なんとなくわかってきたかも」くらいで大丈夫なんです。
その「なんとなく」が、未来の自分たちを助けてくれるんです。
介護や医療が必要になったとき、「誰が・いつ・いくら・どこから出すのか」。
この「お金の流れ」をぼんやりでもつかんでおくことで、いざというときの慌て方がまるで違ってきます。
ここでは親の生活費や収入のざっくりとした把握方法、そして保険のチェックポイントについて、2つの視点からご紹介します。
最初にお伝えしたいのは「親の毎月の生活費、だいたいどれくらいなんだろう?」という、素朴だけど大切な問いについてです。
年金・収入と支出の大まかな確認
介護の話を考えるとき、避けて通れないのが「お金の話」。
わかってはいても、親に「生活って年金だけ?」「貯金はどのくらいあるの?」なんて聞くのは、ちょっと勇気がいりますよね。
でも介護が現実になったときに、支払いの一部が自分に回ってくる可能性がある——そう思うと、やっぱり「なんとなくでも」知っておいた方がいいなと思うようになりました。
では、何から始めればいいのでしょうか?
大事なのは、1円単位で把握することではなく「生活がちゃんと成り立っているかどうか」をゆるやかに感じ取ることです。
たとえば、こんな会話から入ってみてはどうでしょう?
- 年金や収入の状況:
「年金、2カ月に1回って言ってたけど、足りてる?」と聞いてみると、無理のある生活をしていないか、感覚的につかめます。 - 支出のイメージ:
「食費とか光熱費って、月にどれくらい?」と尋ねると、生活のリズムやゆとりも見えてきます。 - 貯蓄の有無:
「もし入院とかあったら、通帳ってどこにある?」と聞くことで、万が一のときの対応がぐんとラクになります。
口座数を知っておくだけでも安心です。 - 介護の備えや希望:
「施設に入るのはどう思う?」と未来のイメージを聞くと、自然と「費用の話」にもつながっていきます。
ちなみに、介護サービスの自己負担は原則1〜3割。
たとえばデイサービスに週2回通った場合、月5千円〜1万円くらいが一般的。
でも、介護の度合いが高まっていけば月3〜5万円以上になることも。
突然その金額を用意するのは、やっぱり大変ですよね。
だからこそ、今のうちに「親のお金がどう出入りしているか」を、ざっくりでいいので把握しておくと安心なんです。
通帳や契約書に細かく踏み込まなくても「なんとなく生活は回ってるな」「備えはまだ弱いかも」くらいの感覚を持つだけでも、将来の備えになります。
続いては、見落とされがちな「保険」の話にうつります。
意外と「入ってるけど中身がわからない」というケース、多いんです。
認知症保険・医療保険の加入状況を確認
親世代の会話のなかで「保険にはしっかり入ってるから大丈夫」とよく聞きます。
でもその「しっかり」って、実は思い込みだったり、過去のままだったりすることも。
私も、母の引き出しから出てきた保険証券を見て「これ、まだ有効なの?」と困った経験があります。
医療費や介護費用がかかりやすくなる高齢期だからこそ「今、どんな保険に入っているか」を知っておくことはとても大切です。
とくに、認知症保険や医療保険は、いざ使おうとしたときに「そんなのあったの?」と慌てるケースも多いので、あらかじめ軽く確認しておくと安心です。
ここでは、チェックしておきたいポイントを整理してみます。
医療保険
まず確認したいのが、入院時に給付が出る医療保険。
入院1日あたり○千円、手術で一時金が支払われる、といったものです。
高齢になると入院のリスクは高まるため「何日目から給付されるのか?」「上限日数はあるか?」などを見ておきましょう。
認知症保険・民間の介護保険
最近増えているのが、認知症になったときに一時金が出る保険や、要介護状態になると年金のように毎月お金がもらえる保険です。
ただし、これらは加入していても保険証券の場所がわからなかったり、家族がその存在を知らなかったりして、請求漏れが起こりやすい保険でもあります。
確認しておきたいことは、
- 加入している保険会社と、保険の種類
- 保険証券や「契約内容のお知らせ」の保管場所
- 保険金の支払い条件(例:どんなときに給付されるのか)
- 保険金を請求する窓口や方法
もしも「内容が古そう」「よくわからない」というときは、毎年届く「保険内容のお知らせ(契約確認通知)」をチェックしてみましょう。
不明な場合は、本人の同意があれば保険会社に問い合わせもできます。
今の高齢者は20〜30年前に加入した保険をそのまま継続しているケースも多く「5日以上入院しないと給付が出ない」「通院は対象外」といった「今の生活スタイルに合わない設計」のままのこともあります。
「うちの親、保険には入ってるって言ってたけど…」
そんな方は、まずは「保険会社どこだったっけ?」と、気軽に話してみるところから始めてみてください。
そして次は、そんなお金の話とも深く関わってくる「住まい」の問題へと話を進めていきます。
「この家、あと何年住める?」と、ふと気になる実家のこと。
備えのヒントを、一緒に考えていきましょう。
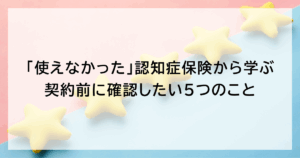
実家や住まいに関する「気づきと備え」
ふと実家に帰ったとき「この家、あと何年住めるんだろう?」とよぎったこと、ありませんか?
畳のへこみ、手すりのない階段、寒さがしみるお風呂場…子どもの頃には気にならなかった「違和感」が、急に目に入ってくるんです。
住み慣れた家は、親にとっては「心のよりどころ」であり、長年の記憶が詰まった宝箱のような場所。
でも一方で、その「慣れ」こそが、小さなリスクの見落としにつながってしまうこともあるのです。
たとえば段差に気づかずつまずいたり、真冬の脱衣所で寒暖差にふらついたり。
ちょっとしたことが、大きなケガや体調不良の引き金になることもあります。
また「この家、誰の名義だったっけ?」「もし親がいなくなったら、相続はどうなるの?」という問題も、意外と手つかずのままになりがちです。
ここでは、そんな「住まいにまつわる気づき」をもとに、今のうちにできる備えについて考えていきます。
大げさに構える必要はありません。
まずは、小さな確認と対話から始めてみませんか?
実家の片づけ、名義、老朽化チェック
「実家のこと、気にはなるけど、なんとなく後回しにしてしまう…」
そんなふうに思っている方、きっと多いですよね。
けれど、親が元気なうちだからこそ確認しておけることって、実はたくさんあります。
特に以下の3つは、早めに目を向けておくと安心です。
家の老朽化や暮らしにくさをチェック
外壁のヒビや雨漏り、軋む床、冷たい水回り…。
築30年以上の家では、目に見えないところで劣化が進んでいることもあります。
親世代は「まだ住めるから大丈夫」と言うかもしれません。
けれど、私たちから見ると「転ばないか心配」「寒暖差で体に負担がかからない?」と感じることもありますよね。
一例として、
- トイレや浴室に手すりがあるか
- 段差が多くないか
- 冬場の寒さ対策ができているか
- キッチンやお風呂に使いづらさがないか
こうしたチェックは、暮らしやすさの「土台」を整える第一歩。
名義や相続の確認
「この家、名義はお父さん? それともお母さん?」「相続のことって、きょうだいで話したことある?」
ふと頭によぎっても、なかなか話題にしづらいテーマです。
でも親が亡くなったあとに名義が曖昧なままだと、相続手続きがスムーズに進まず、家族の関係にも影を落とすことがあるんです。
チェックしておくと安心なのは、
- 家の名義人(登記簿や固定資産税の書類で確認できます)
- 相続について親がどう考えているか
- 将来的にどう扱うか(住み続ける? 売却する?)
「そんな大げさな話、まだ早いかな…」と思っても、いま少しだけ情報を知っておくだけで、将来の選択肢が広がります。
親の「これからの暮らし方」への希望を聞いておく
「この家、ずっと住みたい?」「どこか困ってるところ、ある?」
そんなやさしい問いかけから始めてみてください。
たとえば、
- リフォームしたいと思っているのか
- 将来は施設に入ることも視野に入れているのか
- 自宅で最期を迎えたいのかどうか
この「親の希望」を聞いておくだけで、子どもとしてできることの方向性が見えてきます。
全部を一度に聞く必要はありません。
「そういえば気になっててさ」くらいの軽い切り出し方でも、十分にきっかけになりますよ。
さて、ここまでで「家の外側」や「法律的なこと」を見てきましたが、次はもっと日常的な、家の中に潜む事故のリスクについてご紹介します。
「家の中の事故」が最も多いという現実
「ケガや事故って、外で起きるものでしょ?」——そう思っていた私も、ある日母がリビングで転倒してしまい、その考えを改めることになりました。
実は、高齢者の事故の大半は「家の中」で起きているんです。
消費者庁によると、70代以降では転倒・転落や、寒暖差による体調不良(ヒートショック)が原因で救急搬送されるケースが年々増加しているとのこと。
とくに注意したいのが、以下の2つです。
転倒・つまずき
「たった一度の転倒が、寝たきりのきっかけになってしまった」
そんな話、聞いたことありませんか?
小さな段差やカーペットの端、配線コード、暗い廊下——日常の中に、転倒の「トラップ」は潜んでいます。
特に注意したいのは、
- トイレや和室の出入り口の段差
- 手すりがない階段や廊下
- 夜間、寝室からトイレまでの導線
- ズレやすいキッチンマット
ヒートショック
冬場になると増えるのが「ヒートショック」と呼ばれる事故です。
急激な温度差で血圧が乱れ、失神や心臓発作を起こしてしまうというもの。
とくに脱衣所やトイレ、お風呂のような「寒暖差が大きい場所」で起きやすいのが特徴です。
チェックしたいポイントは、
- 脱衣所やトイレに暖房器具があるか
- お風呂の温度設定が高すぎないか(42度以上は注意)
- 入浴前後にしっかり水分補給しているか
「ヒーターなんて大げさ」と思うかもしれませんが、小型の脱衣所ヒーター1台で防げる事故があります。
大事なのは、「今できる小さなこと」を積み重ねること。
何かが起きてから動くのではなく「気づいたときが始めどき」なんです。
無理のない範囲で少しずつ住まいの安全を整えていけば、親も子も、もっと安心して過ごせるようになります。
次は、いよいよ「親との関係」や「気持ちの整理」について一緒に考えていきます。
ちょっと聞きづらいことを、どうやって話せばいいか——その「声のかけ方」もご紹介していきますね。
親と「今」だからこそできる話をしておく
介護や老後のことって「そろそろ考えないと」と頭では分かっていても、実際に親と話すとなると…どうしても身構えてしまいますよね。
「こんなこと聞いたら嫌がられそう」「そもそも、何から聞けばいいのか分からない」——そんなふうに感じている方、多いのではないでしょうか。
でも実は、親が元気な「今」こそが、こうした大切な話を始める絶好のタイミングなんです。
本人の意思を確認しておくことで、いざというとき、私たち子ども世代も落ち着いて判断できますし、なにより——親の望みをちゃんと叶えてあげられる可能性が高くなるのです。
たとえばお金のこと、延命治療の希望、実家のこと、遺言書の有無など。
どれも将来、誰かが判断を迫られるテーマだからこそ「いま話しておいてくれて助かった」と思える日がきっと来ます。
ここでは、いわゆる「エンディングノート」に書かれるような話題を、日常の延長線で無理なく話せるコツをご紹介していきます。
まずは「ちょっと聞きづらいけど、いちばん大切」とされるテーマから見ていきましょう。
お金・延命治療・実家・遺言書の話、どう切り出す?
「お金のことを聞くなんて、なんだか失礼な気がする」
「延命治療の話なんて、縁起でもないよね」
こんな気持ち、正直とてもよくわかります。
でも、介護や看取りに関わる可能性のある家族だからこそ、知っておくことが、親の希望を叶えるための第一歩になるんです。
お金の話は「もしものときのために」
「通帳ってどこにあるの?」「保険の連絡先、分かるようにしてる?」
こうした話は「全部教えて」ではなく「困ったときにあわてないように知っておきたいだけ」というスタンスで聞くのがポイントです。
たとえば、こんなふうに切り出してみてください。
「もし入院とかになったとき、どこに何があるかわからないと私も困っちゃうからさ…」
「今じゃなくていいんだけど、通帳とか保険ってどこにまとめてある?」
「親の不利益を防ぐために」という気持ちが伝われば、むしろ「そうだね、話しといたほうがいいか」と受け止めてもらえることが多いですよ。
延命治療の話は「誰かの話」をきっかけに
「人工呼吸器、胃ろう、延命治療……正直どう思ってる?」
そう聞けたら一番いいけれど、いきなりはハードルが高いですよね。
おすすめなのは、テレビや新聞の話題から自然に入ること。
「さっきのニュースでさ、延命治療はしないって決めてた人がいたんだけど…お父さんならどうする?」
「『ピンピンコロリ』って昔は聞いたけど、最近はどうなんだろうね」
こうやって「自分のことじゃない誰か」の話を入り口にすると、親も客観的に自分の考えを話しやすくなるようです。
実家や持ち家のことは、自分の未来の話でもある
実家に誰も住まなくなったらどうするか——これは、親だけでなく子ども世代の人生設計にも関わる話です。
「この家、将来どうする予定? 売ったり貸したりって考えてる?」
「もし誰も住まなくなったら、どうしたいって思ってる?」
あくまで「意見を聞かせてほしい」という姿勢で、少しずつ考えを引き出していけるのが理想です。
遺言書については「家族を守るツール」として
「遺言って書いてあるの?」とストレートに聞くよりも、こんなふうに伝えてみてください。
「最近、遺言書があると家族の揉めごとを防げるって聞いたよ」
「きょうだいで意見が分かれると、私が板挟みになりそうで怖くてさ…」
「親を責めるのではなく、こちらの不安や気がかりを正直に伝える」ことで、心の距離がぐっと近づきます。
どの話題も「全部話さなくていい」「一気に聞き出さなくていい」んです。
大切なのは、親の自由を大事にしながら「本人の意思」だけでも知っておきたいという気持ちをベースにすること。
それでもどうしても切り出しにくいときは、エンディングノートというツールを紹介するのもひとつの手。
「こんなのがあるらしいよ」「書いてもらえたら私も安心かも」と、自然な流れをつくれます。
次に、こうした話をどうやって日常の中に取り入れていくか、きっかけの見つけ方をご紹介します。
「まだ元気な今」だからこそできること
「今は元気なんだから、そんな話はまだ早いよ」
そう言われるのは、ごく自然な反応です。
でも、だからこそ「元気な今」にしかできない話があるんです。
体調を崩してから、あるいは認知機能が落ちてからでは、大事なことを確認する機会そのものが失われてしまうこともあります。
たとえば、介護の希望や看取りの場所。
「自宅で過ごしたいと思ってる?」
「もしものとき、どこで最期を迎えたい?」
最近では「自宅で看取られたい」という希望も増えていますが、実際にそれを叶えるためには、家族の協力や体制づくりが必要になります。
だからこそ本人の本音を聞いておくことが、後悔しないための備えになります。
話しにくいことは「何気ない瞬間」をきっかけに。
- 実家でゆっくりしているとき
- ニュースやドラマで介護の話題が出たとき
- 通帳や年金の話になったとき
「もしものとき、どうしてほしい?」
「実はちょっと不安に思ってたことがあってさ…」
こんなふうに、あなたの気持ちを素直に伝えることが、何よりの入り口になります。
「元気なのに縁起でもない」と感じる親には、
「これは『別れの準備』じゃなくて『備えの会話』なんだよ」
と伝えてみてください。
大切なのは、何度かに分けて少しずつ積み上げていくこと。
一度きりの会話ではなく「前にこんな話したよね」と思い出せるよう、メモやノートに残しておくと、それが将来の自分や家族を守る「資産」になります。
次は、これまでの備えをふり返りながら、「今できることリスト」を一緒に整理していきます。
小さな対話が、やがて大きな安心につながっていきますように。
「今できること」チェックリストで「備え」を少しずつカタチに
親の介護や老後のことを考え始めると、思わずため息が出る瞬間がありますよね。
「やることが多すぎて、何から手をつけたらいいのか分からない…」
私も、最初は手探りでした。
気持ちばかりが焦って、空回りする日もあったほどです。
でも、ひとつ気づいたんです。
すべてを一気にやる必要なんて、どこにもない。
大切なのは、「今できることを、できる範囲で、無理なく始めること」。
そう思って一歩踏み出してみると、不思議と気持ちが少しずつ軽くなっていくんです。
この記事の最後にご紹介するのは、そんな「小さな一歩」を踏み出すための「今できること」チェックリスト。
これまでご紹介してきた内容をぎゅっとまとめて、今このタイミングだからこそ取り組める項目を並べました。
完璧を目指さなくても大丈夫。
気になったところから、ひとつずつ試してみてくださいね。
親の健康・暮らしの様子を、そっと見守るための項目
☐ 通院の頻度や飲んでいる薬について、さりげなく話を聞いた
☐ 最近の生活リズムや体力の変化に、ちょっと気づいたことがある
☐ 掃除や洗濯、買い物など、家事で困っていそうな様子を感じたことがある
☐ 食欲や食生活の話題を、日常の会話に取り入れてみた
ちょっとした違和感や変化に気づけると、それが将来の介護の「やわらかな下地」になります。
介護制度やお金の話に備えるための項目
☐ 要介護認定ってどんな制度?という基本をなんとなく調べてみた
☐ 介護保険で使えるサービス(デイサービス、ショートステイなど)を知った
☐ 親の年金や毎月の支出について、軽く話題にしてみた
☐ 親が入っている保険(医療・認知症など)の種類や、証券の保管場所を確認した
お金の話って重たく感じがち。
でも「ちょっとだけ知ってる」だけで、いざというときの不安がグッと減ります。
実家や住まいのリスクを見つけるための項目
☐ 実家の古さや不便さに「これ、大丈夫かな」と思ったことがある
☐ 段差、階段、浴室の寒さなど、気になる場所を把握している
☐ 家の名義や、固定資産税の通知書が誰宛かを確認した
☐ 相続や売却について、きょうだい間で一度話題に出したことがある
「なんとなく不安」から「どこが心配なのか」に変わると、次のアクションが見えてきます。
親との「これから」を話すための項目
☐ 延命治療や施設入所について、親の考えを一度でも聞いたことがある
☐ 遺言書やエンディングノートの話題を、軽くでも出したことがある
☐ 「老後どう過ごしたい?」という希望を聞いてみた
☐ 親の困りごとや不安に耳を傾ける時間を、意識して作ったことがある
正解を得ることが目的じゃないんです。
「聞こうとしてくれた」——その姿勢が、何より親の支えになります。
こうした話って、「やらなきゃ」と思いながらも、つい先送りにしてしまうものですよね。
気づけば1年、また1年…という方も、きっと多いのではないでしょうか。
でももし、このリストの中にひとつでも「やったかも」と思える項目があったなら——
あなたはもう「備えのスタートライン」に立っています。
- 完璧でなくていい
- 話し合いが途中で止まっていてもいい
- 家族と意見が食い違ってもいい
大切なのは「見ようとしていること」。
そして「考えようとしている気持ち」があること。
これからも、親の変化や自分の感情にそっと寄り添いながら、
「未来の安心」を、少しずつ一緒に育てていきましょう。