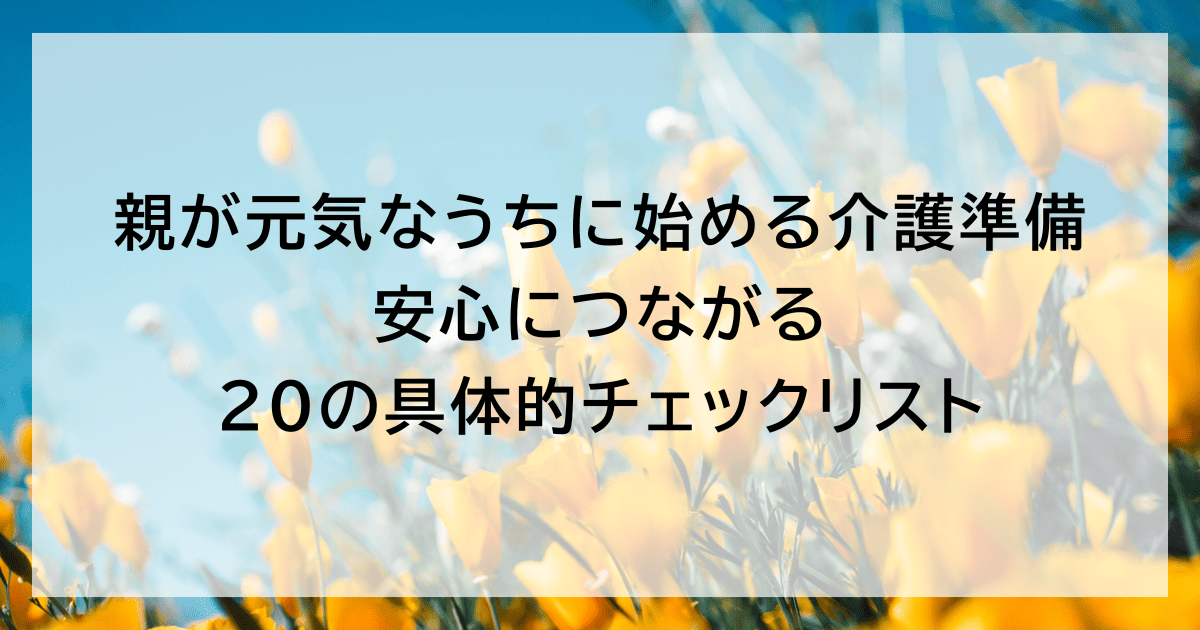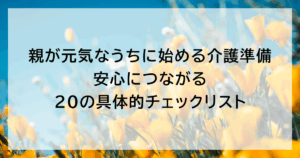「まだ先のことだから…」とつい後回しにしがちな親の介護準備。
ですが、実際に親の体調が急に変わったとき、多くの人が「もっと早く備えておけばよかった」と口を揃えます。
医療やお金、住まい、兄弟姉妹との連携…。
やるべきことは頭ではわかっていても、いざとなると慌ててしまい、必要な書類や制度を調べるだけで数日が過ぎてしまうケースは少なくありません。
特に、仕事や子育てと両立しながら介護に向き合う世代にとっては、余計に大きな負担になります。
だからこそ「親が元気なうちに」準備を始めることが何より大切です。
準備といっても大げさなことではなく、かかりつけ医の連絡先をメモしておく、冷蔵庫の中を一緒に整理してみる、といった小さな一歩からで大丈夫。
積み重ねることで、漠然とした不安が「できたことリスト」に変わり、心が軽くなっていきます。
この記事では、生活・心・お金・未来の4つの視点から「今からできる20の介護準備チェックリスト」をまとめました。
介護準備の4つの視点
| 視点 | 主な内容 | チェック例 |
|---|---|---|
| 生活面 | 健康・住まい・緊急連絡 | かかりつけ医の情報、住まいの安全点検 |
| 心・家族 | 親の希望・兄弟姉妹とのルール | 延命治療の意向、役割分担の確認 |
| お金・手続き | 費用試算・資産整理・制度確認 | 介護費用シミュレーション、通帳管理 |
| 未来の準備 | 自分の働き方・IT活用・自分の備え | 介護休業制度確認、見守りアプリ活用 |
チェック形式なので、ご自身の状況に合わせて確認できます。
今日からできる一歩を一緒に始めてみませんか?
親が元気なうちにやっておきたい「介護準備チェックリスト」
介護はある日突然、嵐のようにやってくることがあります。
私自身も知人の体験談を聞いて、「あのときもっと準備していれば…」という後悔の重さに胸が痛くなったことがあります。
普段は親が元気に暮らしている姿を見て、「まだ大丈夫」と思いがち。
でも、いざとなったときに必要なのは、生活の細かな工夫から家族との話し合い、お金や手続き、自分の働き方まで、本当に幅広くて何から手をつけたらいいか分からなくなるものです。
最近はニュースでも「介護離職」や「老老介護」という言葉を耳にする機会が増えましたよね。
社会全体が直面している課題だからこそ、今のうちから一歩踏み出す意味があります。
この記事では、親が元気なうちにできる準備を 「生活」「心」「お金」「未来」 の4つの視点から整理しました。
下にまとめた20項目のチェックリストを見れば、全体像がパッと分かり、家族で話し合うきっかけにもなります。
「全部やらなきゃ」と力む必要はありません。
まずは眺めてみて、心に引っかかったものから一つ選んでみましょう。
今日できる小さな一歩が、将来の自分と親を守る大きな安心につながります。
| No. | 項目 | 具体例 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 1 | 親の健康状態を確認する | 健康診断やかかりつけ医の診察記録を整理 | ☐ |
| 2 | かかりつけ医の連絡先を共有 | スマホや連絡ノートに記録 | ☐ |
| 3 | 薬や通院の情報を把握 | お薬手帳をコピーして家族で共有 | ☐ |
| 4 | 親の希望を聞いておく | 在宅介護か施設希望かを雑談の中で確認 | ☐ |
| 5 | 延命治療や医療方針を話し合う | 「人生会議」ACPを参考に話す | ☐ |
| 6 | エンディングノートを準備 | 「もしもノート」を親と一緒に記入 | ☐ |
| 7 | 兄弟姉妹と役割分担を話す | 通院担当・買い物担当などを決める | ☐ |
| 8 | 家族で定期的な話し合いの場を設ける | 月1回LINE通話や対面で近況共有 | ☐ |
| 9 | 見守りサービスを試す | 見守りカメラや郵便局の訪問サービス | ☐ |
| 10 | ITツールの使い方を一緒に練習 | LINEビデオ通話や写真共有アプリ | ☐ |
| 11 | 自宅の安全点検をする | 段差解消・手すり設置・転倒防止マット | ☐ |
| 12 | 介護にかかる費用を試算する | 在宅・施設別にシミュレーション | ☐ |
| 13 | 資産や口座の整理を進める | 通帳・保険証券・年金通知書をファイル化 | ☐ |
| 14 | 公共料金や固定費の支払い方法を確認 | 自動引き落としや口座名義を見直す | ☐ |
| 15 | 家計簿アプリを導入 | マネーフォワードMEなどで資産を見える化 | ☐ |
| 16 | 公的支援制度を調べる | 介護保険、高額介護サービス費制度 | ☐ |
| 17 | 相談窓口を把握 | 地域包括支援センターやケアマネ | ☐ |
| 18 | 勤務先の介護制度を確認 | 介護休暇・介護休業・時短勤務制度 | ☐ |
| 19 | 自分の将来の備えも考える | 医療保険・介護保険・信託制度を見直す | ☐ |
| 20 | 家族の思い出を残す | 一緒に旅行・アルバム作成・趣味活動 | ☐ |
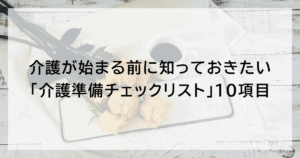
親が元気なうちに備えるべき「生活面のチェック」
「実家って安全なのかな…?」
ふとそんな不安を感じる瞬間、ありませんか?
特に離れて暮らしていると、親の暮らしぶりが見えにくく、心配が募るものです。
私自身も、ある日母から「階段でつまずきそうになった」と聞いたとき、急に現実味を帯びて胸がざわついた経験があります。
元気なうちだからこそ、日常生活を見直すことが、安心につながる大事な準備になるのです。
健康・医療に関する確認
一番大切なのは、親の医療情報を整理しておくことです。
急な発熱や入院時に「かかりつけ医は?」「今飲んでいる薬は?」と分からず慌てるケースは、本当に多いのです。
お医者さんや薬局は「普段の情報」を前提に治療を進めます。
たとえば薬の重複や飲み合わせは、間違えば命に関わることも。
だからこそ、普段から正確な情報を家族で共有しておきましょう。
- かかりつけ医の名前・電話番号・住所をメモにして冷蔵庫に貼る
- 薬局で「お薬の一覧表」をもらい、LINEや写真で家族と共有
- 健康診断の結果はファイルにして保管
厚生労働省も推奨している「お薬手帳」は、まさに命綱。
親が持ち歩くだけでなく、家族も写真で保存しておくと安心です。
医療情報を「見える化」する。
それが介護準備の第一歩になります。
住まいと日常生活の点検
次に見直したいのは、暮らしの舞台となる家。
高齢者が介護を必要とする原因で最も多いのが「転倒」と言われています。
見慣れた実家でも、ちょっとした段差や暗い廊下にリスクが潜んでいるのです。
私の友人は、実家の廊下に小さな絨毯を敷いていたのですが、それがずれてお母様が転びそうになったことをきっかけに片付けたそうです。
「たったこれだけで安心感が違う」と話していました。
- 段差を解消し、必要な場所に手すりを設置
- 冷蔵庫の中を点検して、古い食品や過剰ストックを整理
- 家電を操作が簡単なものに買い替える(大きなボタンの電子レンジ、自動オフ機能付きポットなど)
「片付け」は見た目を整えるだけではありません。
親の暮らしを守る、立派な「介護準備」です。
連絡・緊急対応の備え
最後に意外と忘れがちなのが「緊急時の備え」です。
親が急に倒れたとき、病院で必要になるのは保険証や診察券、お薬手帳。
これらがバラバラに保管されていると、家族は探すだけで何時間も費やしてしまいます。
- 緊急連絡先(兄弟姉妹、かかりつけ医、近所の知人)を紙とスマホ両方に記録
- 保険証・診察券・お薬手帳をまとめてファイル化し、置き場所を家族で共有
- 入院バッグ(下着、パジャマ、スリッパ、充電器など)を一式準備
「ちょっと大げさじゃない?」と思うかもしれません。
でも、実際に介護を経験した方ほど「もっと早く準備しておけばよかった」と口を揃えます。
緊急対応を「見える化」しておくこと。
それが家族全員の安心につながります。
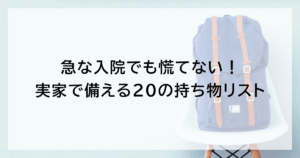
次の準備へ
生活面のチェックは、介護が始まる前だからこそ最大の効果を発揮します。
家や医療情報を整えておくことで、いざというとき慌てずに済むのです。
そして次に大切なのは、親や兄弟姉妹と「どう介護について話し合うか」。
生活の基盤を整えたら、心と家族関係の準備へと進んでいきましょう。
親子で話しておきたい「心と家族の準備」
「親に介護の話なんて、どう切り出せばいいのだろう?」
私自身も何度も迷いました。
元気そうに見えるからこそ、「そんな話をしたら縁起でもない」と思われそうで、口に出すのをためらってしまうのです。
兄弟姉妹との関係だって同じ。
小さなすれ違いが、後から大きな溝になることもあります。
だからこそ、少し勇気を出して、元気なうちに話しておくことが大切なのです。
親の希望を共有する
介護が始まる前に「どんな介護を望んでいるのか」を聞いておくだけで、家族にとっては大きな安心になります。
たとえば「できるだけ家で過ごしたいのか」「施設に入るのも選択肢にあるのか」「延命治療を望むのか」——
これらを知らないまま判断するのは、真っ暗な道を手探りで歩くようなものです。
私は母と旅行中、ふと「もし将来介護が必要になったら、どこで暮らしたい?」と聞いたことがあります。
母は少し考えてから「家がいいけど、みんなが大変なら施設でもいい」と答えました。
たった一言でも、心の重荷が軽くなったのを覚えています。
厚生労働省が推奨する「人生会議(ACP)」の取り組みを活用したり、「エンディングノート」「もしもノート」を書き始めるのもおすすめです。
文章にすることで、親の気持ちが「形」として残り、家族全員の支えになります。
兄弟姉妹でのルール作り
介護は長期戦になることが多く、「なんとなく」で始めてしまうと「私ばかり負担している」という不満が積み重なります。
結果、仲の良かった兄弟姉妹がぎくしゃくしてしまうことも。
私の知人は、母親の介護をきっかけに姉妹間で衝突したそうです。
理由は単純で、「誰が通院の付き添いをするか」が曖昧だったから。
話し合いをして役割分担を決めてからは、驚くほどスムーズに回るようになったと言っていました。
- 定期的に集まり「親の近況アップデート」をする
- 通院・買い物・役所の手続き・費用負担を分担する
- LINEグループやGoogleドライブで情報を共有する
また、地域包括支援センターでは、家族全体で相談に乗ってくれます。
第三者が入ると公平性が増し、トラブル防止にもなります。
心の負担を軽くする工夫
介護準備というと暗いイメージが先に立ちますが、必ずしもそうではありません。
むしろ、親の心を支えることは「前向きな時間」になることもあります。
たとえば、一緒に旅行へ出かけて思い出を作ったり、アルバムを整理したり。
趣味や地域活動を続けられる環境を整えることも大切です。
私の父は、近所のカラオケサークルに通うのが楽しみで、それが「生きがい」になっています。
こうした活動があるだけで、本人の表情が全然違います。
孤独感や経済的な不安をただ聞いてあげるだけでも、親は安心するものです。
地域のカルチャーセンターやシニアサークルを利用するのも良い方法。
次の準備へ
親や兄弟姉妹と介護の話をするのは勇気がいること。
でも「気まずいから」と避けてしまうと、後で大きな後悔につながります。
少しずつでも話し始めることで、家族の絆が強くなるのを実感できるはずです。
生活と心の準備が整ったら、次に考えておきたいのは「お金や手続き」のこと。
介護には必ず費用や役所の手続きがつきものです。
そこでまた慌てないように、家計面の備えにも目を向けていきましょう。
忘れがちな「お金と手続き」の備え
「介護にどれくらいお金がかかるんだろう…?」
私自身も、親の体調が少し不安定になったときに真っ先に頭に浮かんだのはこの疑問でした。
ネットを調べても数字はバラバラで、正直「現実感のある答え」が見つからなかったんです。
さらに銀行口座や保険の書類がどこにあるのか分からず、頭の中はぐちゃぐちゃ。
多くの方が同じ悩みを抱えているのではないでしょうか。
介護費用の試算と資金準備
介護のお金は「想像以上にかかる」と口にする人が多いです。
でも、これは平均値。
在宅か施設かで金額は大きく変わります。
たとえば——
- 在宅介護なら、ヘルパーやデイサービスを使って月5〜10万円前後。
- 特別養護老人ホームなら、食費や居住費込みで月8〜12万円程度。
- 有料老人ホームになると、20〜30万円以上かかるケースもあります。
私の友人は「母を施設に入れるかどうか」で家族会議を重ねましたが、数字を並べた瞬間にようやく現実的な判断ができたと話していました。
どのくらいなら親が自分で出せるのか、不足分は子どもがどう補うのか——これを家族で共有しておくと、将来の不安はずっと軽くなります。
厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」のサイトには介護サービス概算料金の試算ツールもあります。
実際の数字を「見える化」してみると、漠然とした不安が行動に変わるはずです。
介護費用の目安比較
| 介護スタイル | 月額目安 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 5〜10万円 | ヘルパー、デイサービス |
| 特別養護老人ホーム | 8〜12万円 | 居住費、食費、介護サービス |
| 有料老人ホーム | 20〜30万円以上 | 介護+生活支援+医療サポート |
資産と書類の整理
お金に関する書類は「元気なうちに一緒に整理しておく」ことが肝心です。
実際に、介護が始まってから「口座がどこにあるか分からない」「保険証券が見つからない」と慌てる話は珍しくありません。
- 年金通知書をファイルにまとめて受給額を確認する
- 保険証券を一覧にして、不要な契約は整理する
- 銀行通帳やネットバンキングの情報を把握しておく(セキュリティには注意!)
- 公共料金や固定費は自動引き落としに切り替えておく
私は母と一緒に通帳を見直したとき、「こんなに前の契約が残ってたの?」と驚いたことがあります。
解約手続きを済ませただけで、管理の手間も心の負担も軽くなりました。
最近は「マネーフォワードME」のような家計簿アプリを使えば、複数の口座やカードをまとめて管理できます。
デジタルに慣れていない親世代には少し難しいかもしれませんが、子世代と一緒に設定しておくと心強いです。
面倒に見える作業も、未来の安心につながります。
制度や相談先の確認
介護に関する制度はとにかく複雑。
必要になってから調べると、情報量に圧倒されて結局「もらえるはずの支援」を取りこぼしてしまうこともあります。
だからこそ、元気なうちに情報を持っておくことが大切です。
- 地域包括支援センター:介護や生活支援、相談全般を無料で受けられる
- 高額介護サービス費制度:自己負担が一定額を超えると払い戻しがある
- 医療費控除:介護費用も条件を満たせば対象になる
制度は「知っている人だけが得をする」と言っても過言ではありません。
たとえば、私の知人は制度を知らずに数十万円を自己負担してしまったそうです。
一方、事前に知識を持っていた別の方はスムーズに申請でき、負担を大幅に減らすことができました。
次の準備へ
介護のお金や手続きは、どうしても後回しにしがち。
でも「知っておく・整理しておく」だけで、不安はぐっと小さくなります。
そして最後に考えたいのは、親のことだけでなく「自分自身の未来」です。
介護とキャリアをどう両立するか、自分の暮らしをどう守るか——。
次はそこに目を向けてみましょう。
自分自身の働き方も含めた「未来の準備」
「もし親の介護が急に始まったら、私の仕事はどうなるんだろう…」
これは私自身がふと夜に考えて、眠れなくなったことのある問いです。
キャリアを大切にしたい気持ちと、家族を支えたい思い。その間で揺れるのは、とても自然なことですよね。
特に働く女性にとっては、会社の制度やサポートを知らないまま本番を迎えるのは怖いものです。
自分の働き方を点検する
介護とキャリアを両立させる第一歩は、「会社でどんな制度が使えるか」を知ることです。
でも、多くは制度を知らなかったために「辞めるしかない」と追い込まれてしまったケース。
これは本当にもったいないことです。
具体的には——
- 介護休暇:年5日まで、1日や半日単位で取得可能
- 介護休業:最大93日まで休めて、分割取得もできる
- 時短勤務やフレックス:会社によっては柔軟な働き方が可能
私も以前、自分の会社の就業規則を改めて読み直して「こんなに使える制度があったんだ!」と驚いた経験があります。
知らなければ、選択肢すら持てませんよね。
介護と仕事の両立に使える制度
| 制度 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 介護休暇 | 年5日取得可能 | 半日単位でも利用OK |
| 介護休業 | 最大93日休業可能 | 分割取得ができる |
| 時短勤務・フレックス | 企業独自制度あり | 継続的な働き方を支える |
ITやサービスを先に試す
介護はいつ始まるか分かりません。
だからこそ、見守りカメラやアプリのようなサービスは、親が元気なうちに試しておくのがおすすめです。
たとえば——
- 郵便局:
郵便局員による定期訪問や、訪問中に電話での安否確認を行うサービスがあります。 - セコム・ALSOKなどのセキュリティ会社:
センサーによる見守りや緊急ボタンでのガードマンの駆けつけ、健康相談などが受けられます。 - NTTドコモ・ソフトバンクなどの携帯電話会社:
専用アプリから高齢者の状況を確認したり、センサーと連携して異常を通知したりします。 - 配食サービス事業者:
配達時に高齢者の安否を確認するサービスを提供し、自治体によっては補助制度が利用できる場合があります。
私の知人は「母に突然タブレットを渡したら使えなかった」と嘆いていました。
元気なときから一緒に練習しておけば、親も抵抗なく受け入れてくれるし、いざというときに慌てずに済みます。
ITを保険のように準備しておくと、自分の働き方ももっと柔軟にできますよ。
自分の「もしも」にも備える
介護というと「親のこと」と思いがちですが、実は自分自身にも訪れる可能性があります。
40代の今から準備を始めることは、子どもやパートナーに過度な負担をかけないための「未来への贈り物」になるのです。
具体的には——
- エンディングノートを一冊用意しておく
- 医療保険や介護保険を定期的に見直す
- 資産管理の仕組み(信託や代理人制度など)を検討しておく
実際に親の介護を経験した女性が「自分は子どもに同じ苦労をさせたくない」と言って、早めにノートをつけ始めた話を聞いたことがあります。
その姿勢がとても印象的で、「自分も真似したい」と思ったほどです。
自分の未来に目を向けることは、決して暗い話ではありません。
むしろ「これからも安心して働き続けられる」という自信につながります。
次の準備へ
介護の準備は、親のためだけではなく、自分自身の人生を守るためのものでもあります。
会社の制度を理解し、ITサービスを先に取り入れ、自分の将来にも備えておく。
それはキャリアを諦めないための力になります。
ここまで「生活」「心」「お金」「未来」と段階を踏んで整理してきました。
最後は、これらを行動リストとしてまとめて、今日から一歩を踏み出せるように背中を押していきましょう。
まとめ
介護のことは「まだ先の話」と思いたくなるものです。
私も以前はそうでした。
でも、親が元気なうちだからこそできることが本当にたくさんあります。
今回ご紹介した20項目のチェックリストを使って、まずは「今日できること」から始めてみませんか?
その小さな一歩が、未来の安心へとつながります。
「何から始めればいいのか分からない」という声は、とても多く耳にします。
私自身も最初は同じ気持ちでした。
けれど、先送りにしてしまうと、いざ親が体調を崩したときに慌てることになり、必要以上にストレスを抱えてしまいます。
逆に、たとえ小さなことでも準備しておけば「やるべきことが整理できている」という安心感が生まれるんです。
準備は大きな作業を一気に終わらせる必要はなく、日々の暮らしの中で少しずつ積み重ねていけば十分です。
たとえば——
- チェックリストを印刷して冷蔵庫に貼る。
家族みんなの目に入り、話し合うきっかけになります。 - 今日からできることを一つだけ選ぶ。
たとえば「かかりつけ医の連絡先をスマホに登録する」「実家の冷蔵庫を一緒に整理する」など。 - 公的な便利ツールを活用する。
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、地域の介護サービスを事前に調べられます。 - エンディングノートを手に入れておく。
書店やオンラインで買える「もしもノート」は、親子で一緒に始めやすい一冊です。 - そして、自分の会社の制度も確認しておく。
就業規則を見れば、すぐに分かります。
こうした小さな行動を積み重ねていくうちに、不安の山が「できたことリスト」に変わっていくのを実感できるはずです。
介護準備は、重くのしかかる作業ではありません。
「親のこれからを大切にしたい」「自分の人生も守りたい」という自然な気持ちを、行動に変えていくプロセスです。
ぜひ、20項目のチェックリストをダウンロードして、今日からひとつでいいので実践してみてください。
その一歩が、未来のあなたをきっと救ってくれます。
この記事を読みながら「やってみようかな」と思ったなら、その気持ちが温かいうちに動き出すのがおすすめです。
頭の中で不安を抱え続けるよりも、紙に書き出して一つずつ確認していくことで、心はぐっと軽くなります。
そして何より「準備しておけば大丈夫」という安心感が、これからの日々を前向きに過ごす力になります。
(再掲)親が元気なうちにやっておきたい「介護準備チェックリスト」
| No. | 項目 | 具体例 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 1 | 親の健康状態を確認する | 健康診断やかかりつけ医の診察記録を整理 | ☐ |
| 2 | かかりつけ医の連絡先を共有 | スマホや連絡ノートに記録 | ☐ |
| 3 | 薬や通院の情報を把握 | お薬手帳をコピーして家族で共有 | ☐ |
| 4 | 親の希望を聞いておく | 在宅介護か施設希望かを雑談の中で確認 | ☐ |
| 5 | 延命治療や医療方針を話し合う | 「人生会議」ACPを参考に話す | ☐ |
| 6 | エンディングノートを準備 | 「もしもノート」を親と一緒に記入 | ☐ |
| 7 | 兄弟姉妹と役割分担を話す | 通院担当・買い物担当などを決める | ☐ |
| 8 | 家族で定期的な話し合いの場を設ける | 月1回LINE通話や対面で近況共有 | ☐ |
| 9 | 見守りサービスを試す | 見守りカメラや郵便局の訪問サービス | ☐ |
| 10 | ITツールの使い方を一緒に練習 | LINEビデオ通話や写真共有アプリ | ☐ |
| 11 | 自宅の安全点検をする | 段差解消・手すり設置・転倒防止マット | ☐ |
| 12 | 介護にかかる費用を試算する | 在宅・施設別にシミュレーション | ☐ |
| 13 | 資産や口座の整理を進める | 通帳・保険証券・年金通知書をファイル化 | ☐ |
| 14 | 公共料金や固定費の支払い方法を確認 | 自動引き落としや口座名義を見直す | ☐ |
| 15 | 家計簿アプリを導入 | マネーフォワードMEなどで資産を見える化 | ☐ |
| 16 | 公的支援制度を調べる | 介護保険、高額介護サービス費制度 | ☐ |
| 17 | 相談窓口を把握 | 地域包括支援センターやケアマネ | ☐ |
| 18 | 勤務先の介護制度を確認 | 介護休暇・介護休業・時短勤務制度 | ☐ |
| 19 | 自分の将来の備えも考える | 医療保険・介護保険・信託制度を見直す | ☐ |
| 20 | 家族の思い出を残す | 一緒に旅行・アルバム作成・趣味活動 | ☐ |