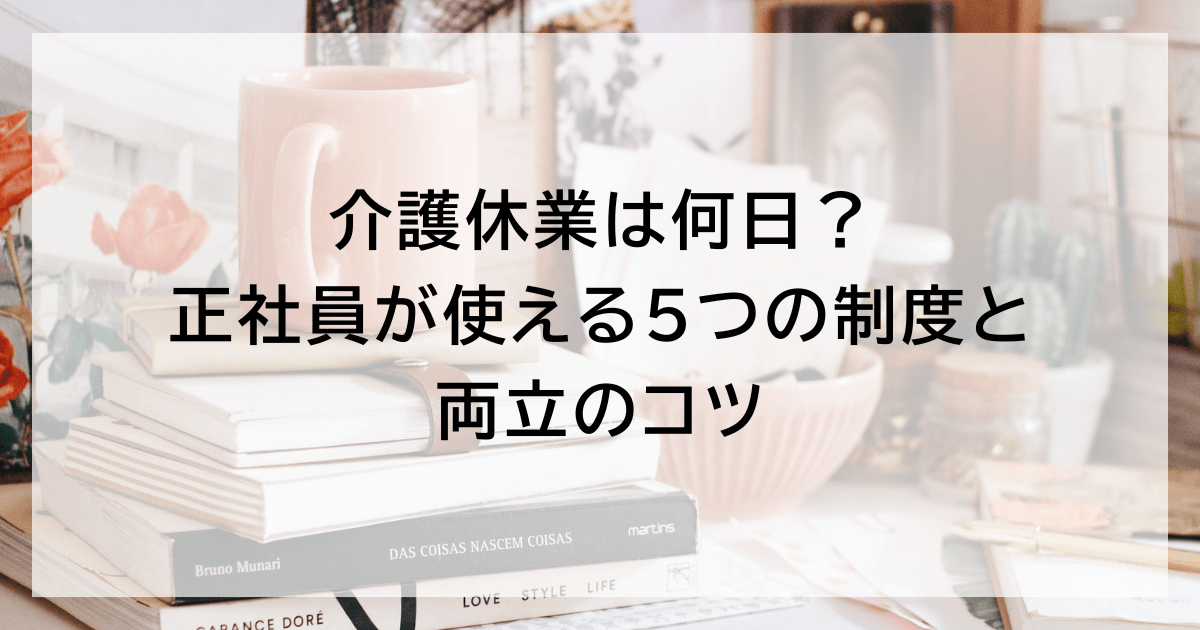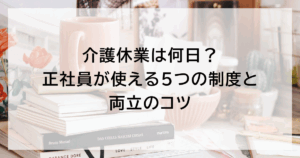親や義父母の介護が現実になったとき、多くの人が最初にぶつかる壁は「仕事、どうしよう…」ではないでしょうか。
私も母の骨折で急に介護が必要になったとき、頭に浮かんだのは「何日休めるの?」「給料は?」という不安ばかりでした。
でも、制度を知ることで状況は一変します。
介護休業だけでなく、介護休暇や時短勤務など、組み合わせて使える制度がいくつもあるんです。
この記事では、正社員が利用できる介護関連制度を整理し、スムーズに取得するコツまでご紹介します。
- 親や義父母の介護が必要になりそうだが、仕事を辞めずに両立できるか不安な方
- 介護休業や休暇の制度があるのは知っているが、実際に何日使えるのか、給料はどうなるのか分からない方
- 介護休業と有給休暇、介護休暇、時短勤務などの違いが整理できていない方
- 制度を使うと職場に迷惑をかけるのではないかと心配な方
介護休業は何日とれる? まずは制度の基本を押さえよう
- 介護休業の法律上の上限日数(通算93日/対象家族1人あたり)を説明
- 分割取得の可否(最大3回に分けられる)
- 「親だけでなく義父母も対象」「同居は不要」など、意外と知らない条件を整理
- 実際に休むときに気になる、有給・無給の仕組みや「介護休業給付金」の概要にも触れる
親の介護が現実味を帯びてくると、仕事中も心のどこかで落ち着かなくなりますよね。
私も母が入院したとき、真っ先に頭に浮かんだのは
「仕事、どうしよう」
「どれくらい休めるんだろう…」
という不安でした。
そんなときにまず知っておきたいのが、介護休業の基本ルールです。
法律では、対象となる家族1人につき、通算で最大93日まで介護休業を取ることができます。
たとえば父と母、二人の介護が必要になった場合は、父93日+母93日で合計186日まで取得可能。
実際に、私の同僚は義父と実母の介護でこの制度を活用し、交互に休みを取りながら無理なく乗り切っていました。
しかも便利なのが分割取得できること。
最大3回に分けられるので、いきなり3か月連続で休む必要はありません。
たとえば最初は10日だけ休んで急場をしのぎ、落ち着いたら一度復帰。
その後、必要に応じて残りの日数を使う――こんな柔軟な使い方ができると、仕事との両立が少し現実的に思えてきますよね。
さらに意外と知られていないのが、対象家族の範囲の広さです。
父母だけでなく、義父母、配偶者、子ども、祖父母、兄弟姉妹まで対象に含まれます。
しかも、同居や扶養の有無は問われません。
遠方に住む義母の介護でも、あなたが申請することが可能です。
そして気になるのがお金のこと。
介護休業中は基本的に無給ですが、雇用保険に入っていれば介護休業給付金がもらえます。
給付額は休業前賃金の約67%。
たとえば日給換算で1万円の方なら、1日あたり約6,700円が目安です。
これがあるだけで、経済的不安がかなりやわらぎますよね。
なお、休業中も健康保険や厚生年金の加入はそのまま維持されます。
保険料の免除はありませんが、万が一の医療や将来の年金に影響が出ないのは安心材料です。
こうして制度の全体像をつかむだけでも、「介護が始まったらもう仕事を辞めるしかない…」という思い込みは少し和らぎます。
次の章では、介護休業以外に正社員が使える便利な制度を5つ紹介します。
制度を組み合わせれば、介護と仕事の両立はもっと現実的になりますよ。
正社員が使える介護関連制度5つと特徴
介護と仕事を両立するために使える公的・社内制度を5つ紹介します。
各制度の利用条件や日数、給与の扱い、運用のコツを整理し、「私にはどの制度が使えるの?」という疑問を解消。
組み合わせれば、キャリアを諦めずに家族を支える道が見えてきます。
親や義父母の介護が必要になったとき、まずぶつかる壁は「どうやって仕事と両立するか」。
私も母が急に入院したとき、会議の合間に病院からの電話を取るたびに胸がざわつきました。
そんな不安を少しでも減らしてくれるのが、法律で整備された介護制度です。
ここでは正社員が利用できる代表的な制度を5つ、整理します。
介護休業(最大93日/対象家族1人あたり)
まずは王道ともいえる介護休業です。
先述のとおり、対象家族1人につき通算93日まで休めます。
父と母を介護するなら、父93日+母93日で最大186日。
数字にすると冷たく感じますが、実際には「3か月×2人分」という具体的な目安になると心強いです。
しかも最大3回まで分割取得OK。
私の同僚は「10日休んで一息つけたことで、気持ちがだいぶ楽になった」と話していました。
お給料は基本的に無給ですが、雇用保険に加入していれば介護休業給付金がもらえます。
休業前賃金の約67%相当で、たとえば日給換算1万円なら1日あたり約6,700円。
満額ではないけれど、精神的な支えになります。
介護休暇(年5日/2人以上なら10日)
短期対応の味方が介護休暇。
対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得可能です。
しかも1日単位だけでなく1時間単位でも使えるので、午前だけ通院付き添い、午後から出社――といった働き方もできます。
給与は法律上は無給ですが、最近は有給扱いにする会社も増加中。
私の勤務先でも、短時間の介護休暇は有給として処理され、同僚は「気兼ねなく使えて助かった」と言っていました
短時間勤務など(事業主選択制)
「毎日は休めないけど、フルタイムは厳しい」というときは短時間勤務などの選択制措置が頼りです。
事業主は以下4つのいずれかを整備する義務があります。
- 1日6時間勤務などの短時間勤務
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 介護サービス利用のための費用助成
ただしどの措置を導入するかは会社次第。
短時間勤務が使えると思っていたら、実際にはフレックスのみだった、というケースもあります。
勤務時間分の給与は支払われますが、収入とのバランスも要確認です。
所定外労働・時間外労働・深夜業の制限
介護は体力も気力も使うもの。
そんなときは残業や深夜勤務の制限の制度が助けになります。
申請すれば、月の残業時間に上限を設けたり、深夜勤務を免除したりしてもらえます。
私の知人は、この制度を利用して「夜の入浴介助がある日は残業免除」にしてもらいました。
給料は働いた分だけ支給されるので、残業代が減る以外の不利益はありません。
社内独自制度(積立有給・特別休暇など)
最後は会社独自の制度です。
たとえば以下のような仕組みがあります。
- 積立有給制度:使いきれなかった有給を積み立てておき、介護時にまとめて取得
- 介護特別休暇:年3~5日程度の有給休暇を追加付与
給与はもちろん100%支給。
大企業や外資系企業に多く、手厚い福利厚生があると介護との両立は一気に現実的になります。
社内イントラや人事部で確認しておくと安心です。
どこにも書いていなくても、人事部に相談したら柔軟に対応してもらえた、という事例もあります。
お困りごとは相談してみてください。
この5つの制度を把握しておくだけで、「仕事を辞めるしかない」という思い込みから少し解放されます。
制度を組み合わせれば、介護とキャリアの両立は楽になっていきます。
次は、実際にスムーズに制度を使うコツをお伝えします。
知っているかどうかで、あなたの心の余裕は大きく変わりますよ。
介護休業の取得をスムーズにする3つのポイント
介護休業をスムーズに取れるかどうかは、事前の準備と職場との調整がカギです。
申請から休業開始、給付金申請までの流れを理解し、次の3つのコツを押さえれば、手続きも気持ちもぐっとラクになります。
介護休業の制度は知っていても、いざ自分が使うとなると、胸がざわつくものです。
「会社にどう説明すればいいんだろう」
「急にお願いしたら迷惑じゃないかな…」
私自身、初めて母の介護で休業を考えたとき、そんな不安でいっぱいでした。
でも、ちょっとした準備と工夫で、申請から取得までをぐっとラクにできます。
ここでは、私や周囲の経験も交えながら、スムーズに休業を進めるための3つのコツをご紹介します。
Point 1:家族の状況を「見える化」してまとめる
まず大事なのは、会社に「なぜ今休む必要があるのか」を伝えることです。
でも、ただ「母の介護が必要なので休みます」と言うだけでは、上司や人事には具体的な状況が伝わりません。
そこで役立つのが、家族の状況をA4用紙1枚にまとめる「見える化」。
私の場合、母が骨折で入院したとき、こんな表を作りました。
- 要介護認定の有無と介護度(例:要介護1)
- 通院やリハビリのスケジュール(例:週2回の通院)
- 1日の介護に必要なおおよその時間(例:朝30分、夜1時間)
- 他に支援できる家族の有無(例:父は高齢で介助は難しい)
この1枚を上司に見せたら、「これならチームの調整もしやすいね」と言われ、承認までが本当にスムーズでした。
最近は、会社によっては状況報告書の提出を求めるケースもあります。
大企業では人事部や産業医にも回ることがあるので、シンプルで具体的な資料は強い味方になります。
Point 2:職場の繁忙期を避け、前倒しで相談を始める
介護関係の制度の利用は、申請が早いほどスムーズです。
就業規則で定められている締め切りはありますが、会社側の準備も必要になるので、早ければ早いほど良い。
特に注意したいのが、繁忙期を避けること。
私が初めて申請を考えたのは年度末でしたが、経理部の友人は「この時期は絶対無理」と断言されていました。
決算期や大型プロジェクトの山場など、職場にとっての「修羅場」で急に長期休業を申し出ると、承認されるまでに時間がかかることもあります。
もちろん家族の状況もあるので、早めに相談をしたくでもできなかった、ということもあるでしょう。
ただできる限り、「修羅場×急×長期休み」のフル装備は避けたほうが無難です。
私は結局、半年ほど前から上司に「母の介護で秋ごろにお休みをお願いするかもしれません」と早めに伝えました。
その後、社内カレンダーで繁忙期を避けた10月に申請することに決め、チームとも事前にスケジュールを共有。
おかげで引き継ぎや後任対応も滞りなく進み、休業前日も落ち着いた気持ちで会社を後にできました。
前倒しで相談するだけで、会社も心構えができるし、承認のハードルもぐっと下がるのです。
Point 3:複数の制度を組み合わせたプランを考えておく
最後のポイントは、介護休業だけに頼らないことです。
先述のように、介護休業以外にも、介護休暇、時短勤務、深夜業や残業の制限など、いくつかの制度があります。
私が実践したプランはこうです。
この段階的な使い方で、仕事への影響を最小限に抑えられました。
さらに、会社によっては積立有給や介護特別休暇といった独自制度もあります。
たとえば私の知人は、社内の「特別休暇」を組み合わせることで、家族の入退院や在宅ケアをうまく乗り切っていました。
複数の制度を組み合わせて活用すれば、介護と仕事の両立はきっと現実的になります。
この3つのポイントを押さえて準備するだけで、申請から休業取得までが驚くほどスムーズになります。
「大変そうだから」と後回しにせず、早めに一歩踏み出すことが、心の余裕にもつながりますよ。
まとめ:制度を知れば、介護と仕事の両立はもっと現実的に
介護休業は「最大93日」と聞くと短く感じるかもしれません。
でも、介護休暇や時短勤務、深夜業制限など、複数の制度を組み合わせれば、現実的な両立が見えてきます。
介護は、ある日突然やってきます。
ニュースでも「働きながら親を支える40代・50代」が増えていると報じられていますが、いざ当事者になると、仕事か介護かの二択に追い込まれたような気持ちになるものです。
でも、制度を知り、早めに準備しておけば、選択肢はもっと広がります。
私自身、母の入院をきっかけに初めて制度を調べ、会社に相談しましたが、「知っているかどうか」で心の余裕が全く違いました。
介護休業はゴールではなく、スタートです。
制度を理解して味方につければ、キャリアを諦めずに家族を支えることは十分に可能です。
あなたらしく安心の準備を整えていってください。