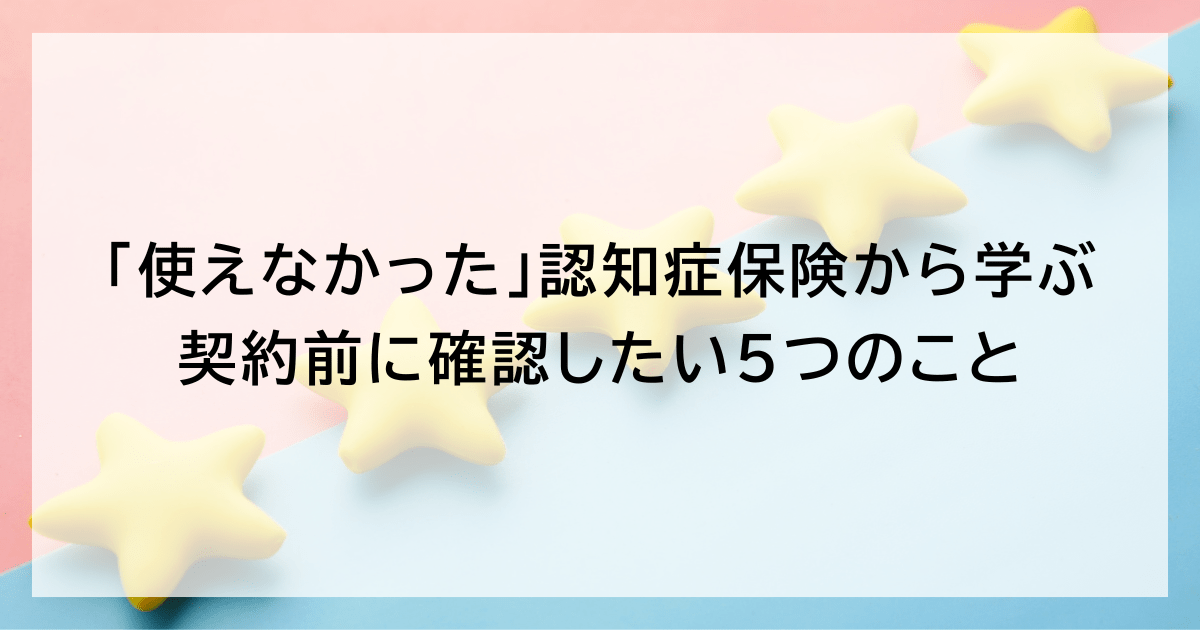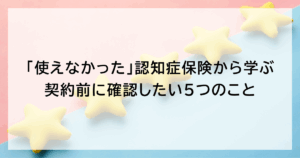「保険に入っておけば安心」——そう思っていたのに、いざというときに「使えなかった」。
そんな声を聞くと、なんとも言えないやるせなさを感じますよね。
特に、認知症に関する保険は、他の医療や生命保険とは少し事情が違います。
診断の基準が複雑だったり、請求のタイミングが難しかったり、本人が手続きをできない状況だったり…。
いざというときに支えになるはずの保険が、思ったように役に立たないこともあるのです。
でも、だからといって「入らない」という選択が正しいとも限りません。
保険そのものを悪者にするのではなく、「どうすればきちんと活用できるのか」を考える視点が大切なのだと思います。
この記事では、認知症保険を検討する際に押さえておきたいポイントや、実際にあった「使えなかった」事例を交えながら、家族でどんな備えをしておくと安心なのかを、一緒に考えていきたいと思います。
大切なのは、「保険に入るかどうか」だけでなく、「わが家にとって必要な備えとは何か?」を見つめ直すこと。
そのヒントになれば幸いです。
- 親が70代後半になり、そろそろ認知症のリスクが気になる方
- 保険の資料を取り寄せたものの、「本当に必要?」「うちの親に合ってる?」と迷っている方
- 保険外交員にすすめられているが、「勢いで入って後悔しないか」心配な方
- 「実際に使えなかった人っているのかな?」という不安を感じている方
「使えなかった」ケースに共通していた落とし穴とは?
「万が一のために入っておけば安心」
そう思って、認知症保険に入っていたのに、いざというときに給付されなかった。
そんな信じられないような話、実はけっして珍しいことではありません。
「うちの親もそうだったら…」と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
この記事では実際にあった事例をもとに、「なぜ保険が使えなかったのか?」という落とし穴と、加入前に確認しておきたい大切なポイントをお伝えします。
発症しても「給付対象外」だったケース
ある方のお話です。
「母がアルツハイマー型認知症と診断されたんです。
でも、保険会社に問い合わせたら、『給付の対象ではありません』って言われて…。
もう、何のために保険料を払ってきたのか分からなくなりました」
こうした「まさか」の事態は、少なからず起こっています。
なぜこんなすれ違いが起きるのでしょうか?
実は、認知症保険には「給付の条件」が思っている以上に細かく設定されているんです。
たとえば…
- 「軽度認知障害(MCI)は対象外」と書かれている
- 「要介護2以上」でないと給付されない
- 「診断名」ではなく「日常生活への支障」が証明されなければならない
など、ハードルの高さに驚くことも少なくありません。
さらに「診断書に書かれた表現が保険会社の基準と一致しない」という理由で、何度も書類の出し直しを求められるケースも。
医療の専門用語と、保険の世界の言葉って、意外とズレているんです。
私も以前、実家の整理中に見つけた保険証券を手に「これ、ちゃんと役に立つのかな…?」と不安になった経験があります。
保険は本来「安心のための備え」のはずなのに、内容を知らなければ、ただの「紙切れ」になってしまう。
そんな悲しい現実があるのです。
次に紹介するのは、さらに複雑な「家族の気持ち」に関わる落とし穴です。
本人が拒否して保険請求できなかったケース
「母に保険の話をすると『私は認知症なんかじゃない!』と怒り出してしまって…。
どうすればよかったのか分かりませんでした」
この言葉、実際に私が聞いたご相談のひとつです。
認知症の初期段階では、本人が症状を自覚していないことが多く、むしろ「自分はしっかりしている」と思い込んでいるケースも珍しくありません。
家族がどれだけ心配しても、保険の請求に協力してもらえないことがあるんです。
さらにやっかいなのが「保険に入っていたこと自体を、本人が忘れてしまっていた」というケース。
保険証券がタンスの奥から見つかって、「え、こんな保険に入ってたの?」と家族が初めて気づく。
そんなエピソードもよく聞きます。
こうしたときに大切なのが、「代理請求制度」の存在です。
保険によっては、家族が代わりに請求できる仕組みがありますが…
- あらかじめ「代理人」を登録しておく必要がある
- 「本人の同意書」が求められる場合もある
など、条件は保険ごとにバラバラです。
加入時に「もしものとき、誰がどうやって請求するのか?」を確認しておかなければ、いざというときに動けなくなってしまいます。
「保険に入っていたのに」給付されなかった共通点
「入っていたのに、使えなかった」。
この言葉の裏には、共通した落とし穴があります。
それは「思い込みによるリスクのズレ」と「条件の見落とし」です。
たとえば…
- 脳血管性認知症を想定していたが、実際はピック病(前頭側頭型認知症)だった
- 「発症前1年以上の加入」が条件だったのに、75歳になってすぐ加入して間に合わなかった
など、わずかな違いが大きな誤算につながってしまうことも。
また「診断された=すぐ請求できる」と思っていたら、「日常生活に支障が出てから一定期間が経っていないと給付対象外」だった、というように、給付のタイミングにも注意が必要です。
さらに厄介なのが、「パンフレットでは簡単そうに見える条件が、実際にはかなり複雑で時間もかかる」ということ。
医師の協力が必要だったり、介護認定の手続きが遅れたりと、思った以上に「根回し」が必要です。
もし今「うちの親も、もしかして…」と少しでも気になった方がいたら、それは大切な第一歩です。
保険は「安心」のためにあります。
その安心が、いざというときにしっかり機能するように。
今のうちから、いっしょに準備していきましょう。
契約前に確認すべき5つのポイント
親の物忘れが増えてきて「そろそろ認知症保険、考えた方がいいのかな」と思ったとき。
多くの方が「念のために入っておこう」と思うものです。
けれど、保険って「入って安心」で終わりではないんですよね。
ここでは、実際に後悔しないために――契約前に必ず押さえておきたい5つのポイントをお伝えします。
私自身、母の介護のことを考え始めたときに、「もっと早く知っておけばよかった…」と感じたことばかりです。
「発症の基準」がどう定められているか
まず最初にチェックしたいのが「発症」の基準。
これが曖昧なままだと「せっかく入っていたのに給付されない」という悲しい事態になりかねません。
実は、多くの認知症保険では「医師の診断=即給付」とはならないことがほとんど。
たとえば「軽度認知障害(MCI)」や「初期のアルツハイマー型認知症」といった、まだ生活に大きな支障がない段階では、給付の対象にならないケースが多いんです。
私の知人にも、親御さんが「認知症」と診断されてすぐに保険会社に問い合わせたところ「まだ条件を満たしていない」と言われてしまった方がいました。
「え? 認知症って診断されたのに?」と戸惑い、結局、給付されないまま月日が流れてしまったそうです。
また「医師の診断だけでOK」という保険もあれば、「要介護認定で2以上」や「生活に具体的な支障が出ている証明が必要」など、複数の条件がセットになっている保険もあります。
これ、まるで「複数の鍵が揃わないと開かない金庫」のようなもの。
さらに、認知症にもさまざまな種類があります。
アルツハイマー型や脳血管性、レビー小体型、ピック病など。それぞれ進行の仕方も症状の出方も違うので、親御さんの健康状態や家族の事情と、保険の内容がきちんと合っているかどうか――
ここはしっかり見極めたいところです。
「何となく心配だから入っておこう」ではなく、「この保険は、いつ・どんなときに助けてくれるのか?」
それを明確にしたうえで契約することが、後悔しない第一歩になります。
代理請求は誰ができる?
次に確認したいのが、「いざというとき、誰が保険を請求できるのか?」ということ。
認知症という病気の性質上、本人がしっかりと手続きをするのが難しいケースはとても多いです。
「うちの父は、保険に入っていたことすら覚えていなかった」という話、実は珍しくありません。
もっと困るのが、本人に症状の自覚がない場合。
「まだ大丈夫だから、そんな話はしないでくれ」と、保険の手続きを拒否されてしまうこともあります。
そうした事態に備えて、多くの認知症保険には「代理請求人制度」があります。
つまり、あらかじめ家族や信頼できる人を「代わりに請求できる人」として登録しておく仕組みです。
ただし注意が必要なのは、これも保険によって条件がバラバラだということ。
たとえば、
- 加入時に家族を代理人として登録しておかないとダメ
- 請求には本人の同意書が必要
- 成年後見人制度を利用しないと請求できないこともある
など、意外にハードルが高い場合もあります。
私の親戚は、保険会社に確認したときに「代理請求には家族の戸籍謄本と診断書と後見人証明が必要」と言われ、「これは今すぐには無理だね…」と諦めてしまったそうです。
「そのときになったらどうにかなるだろう」と思わずに、「そのとき、誰がどう動けるか」を家族で確認しておくことが、保険を生きた備えにするために欠かせないポイントです。
既契約の医療保険・介護保険との重複と違い
ここで、一度立ち止まって考えてみましょう。
「今すでに加入している保険で、カバーできている部分はないか?」
実は認知症保険に入った後で、「あれ? これって介護保険と内容かぶってない?」と気づくことがあるんです。
たとえば、民間の介護保険に「要介護認定されたら一時金が出る」特約が付いていたり、医療保険で認知症による通院や入院もカバーされていたり。
「ちゃんと内容を見直しておけば、無理に新しい保険に入らなくてもよかったのに…」という話は、実はとても多いです。
私も一度、両親の保険証券を片手に家族会議を開いたことがあります。
保険証券って、あれ、すごく分かりにくいですよね(笑)。
でも、どんなときにいくら出るのか、誰のための保険なのかを整理してみると、意外と「あ、この保障で十分かも」と気づけたりします。
新しく保険に加入する前に、ぜひ次の3つを確認してみてください。
- 今持っている保険で、認知症の症状に対してどこまでカバーされているか
- 同じような保障が重複していないか
- それでも不安が残る部分があるかどうか
そのうえで「やっぱりこの保険が必要だ」と納得できたときこそ、本当に意味のある契約になります。
次に確認したいのは、「払っている保険料に見合った価値があるか?」という「費用対効果」の視点です。
このあたりは、家計を守るうえでもかなり重要なポイント。
月々の保険料と「元が取れる可能性」、どう考える?
「保険って、結局いくら払って、いくら返ってくるの?」
これは、私自身も親の保険を検討していたとき、何度も頭をよぎった疑問です。
認知症保険を考えるとき、意外と忘れがちなのが「毎月の保険料が、将来の給付金に見合うのか?」という視点。
たとえば、60歳の女性が月3,000円の保険に加入したとします。
85歳まで払い続けたら、トータルで約90万円。
でも、もらえる給付金は100万円――一見、損はしなさそうに見えますよね。
でも、現実はもう少し複雑です。
保険金を受け取るには「診断が条件に合っている」「必要書類が揃っている」「家族が請求手続きをきちんと行う」など、いくつかの「ハードル」を超える必要があります。
これが意外と高い。
中には「軽度の認知症だったから給付対象外だった」「親が請求に同意しなかった」「そもそも保険に入っていたことを忘れていた」なんて話も耳にします。
つまり、保険料をコツコツ払い続けたのに、使わずじまいだった…というケースも、決して珍しくないのです。
もちろん「一度も使わなかった=よかったこと」でもあるのですが、家計にとっては「払い損」になってしまう可能性もある。
これって、まるで長年通ったスポーツジムの会費を思い出すような…そんな感覚です。
さらに注意したいのは、年齢が上がるほど保険料もアップすること。
70歳を過ぎると、月5,000〜8,000円のプランも出てきます。
高齢の親の介護費用、自分の老後資金、子どもの教育費…と、出費が重なる時期に、毎月数千円の保険料が重荷にならないか?
そこは冷静に見極めたいポイントです。
大切なのは「入っていれば安心」ではなく、「このお金を払って、本当に自分たちの安心につながるか?」という視点。
家族のライフスタイルや、今後の資金計画を見つめ直してみましょう。
さて、ここまで読んで、「そもそも保険って必要なのかな?」と思った方もいるかもしれません。
次は、その「原点」に立ち返ってみましょう。
そもそも「保険で備える必要」があるのか?
保険を検討していると、いつの間にか「入る前提」になってしまっていること、ありませんか?
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいのです。
そもそも、認知症に対して「保険で備える必要があるのか?」
この根本的な問いに向き合うことは、とても大切です。
「なんとなく不安だから」「周りが入っているから」という理由だけで保険に加入してしまうと、本当に必要な備えからズレてしまう可能性もあるからです。
まず押さえておきたいのが、「認知症になったら、どれくらいお金がかかるのか?」という現実的な話。
厚生労働省のデータによると、要介護高齢者の介護費用は、在宅介護で月8〜10万円、施設に入ると15〜20万円くらい。
「そんなにかかるの!?」と思うかもしれませんが、ここで大事なのは「すべてが自己負担ではない」ということ。
介護保険制度を使えば、費用の7〜9割は公的にカバーされるケースも多く、自己負担は意外と抑えられることもあります。
また、認知症は急に進む病気ではなく、少しずつ症状が現れるため、時間をかけて準備できるケースも少なくありません。
家族で話し合ったり、地域の支援を受けたり、貯蓄を見直したり。
つまり、「保険以外の手段でも備えられる可能性がある」ということです。
とはいえ、家族の状況によっては、やっぱり保険が心強い味方になることもあります。
たとえば、
- 親が一人暮らしで、いざというとき頼れる人が近くにいない
- 兄弟姉妹が遠方に住んでいて、サポートが難しい
- 家族全員が忙しく、手続きに時間を割く余裕がない
こうしたケースでは、「万が一のとき、給付金がパッと出る保険」が「安心材料」になるかもしれません。
最近では、予防サポートがついたプランや、アプリ連携で状態の変化を見守れる商品も登場しています。
時代の変化に合わせた選択肢が増えているのも、心強いですね。
結局のところ、「保険に入るべきかどうか」は、その人の暮らし方・考え方・家族の距離感によって異なります。
だからこそ、まずは「なぜ不安を感じているのか?」「どんなサポートがあれば安心か?」を自分の言葉で整理してみてください。
そのうえで「今の自分たちにとって、保険は必要か?」を判断すれば、きっと納得感のある答えが見つかるはずです。
次はここまでのまとめとともに、「今すぐ完璧に備えなくても大丈夫」と思えるような、無理のない準備のステップをご紹介します。
焦らず、自分たちらしく進めていきましょう。
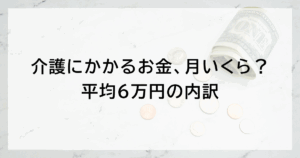
「うちの親には本当に必要?」を考える3つの視点
親の性格とライフスタイル
「認知症保険って、入っておいた方がいいのかな?」
そう考えたとき、つい見落としてしまいがちなのが、親自身の「性格」や「ふだんの暮らし方」です。
たとえば、こんなお父さま・お母さま、思い当たる方はいませんか?
- 病院嫌いで、よほどのことがないと行こうとしない
- 認知症の検査に対して、どこか抵抗感がある
- 手続きや書類が大の苦手。保険の請求なんて考えるだけでイヤそう
- 「私はまだまだ元気だから大丈夫」と、介護サービスをきっぱり拒む
実は、私の母もこのタイプでした。
風邪を引いても「寝てれば治る」が口ぐせで、役所の書類もいつも放置。
保険の話をしたときも、「そんなの要らないわよ」で片づけられたのを覚えています。
こうした傾向がある親御さんの場合、保険に入っていたとしても、いざという時に「診断を受けること」そのものがハードルになる可能性があるんです。
「えっ、診断を受ければお金が出るんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実際はもう少し複雑です。
保険金を受け取るには、
- 医師から認知症の診断を受け、
- その診断書を保険会社に提出し、
- 給付条件に合っているか審査してもらい、
- ようやく給付される
という流れになります。
このどれか一つでも抜けてしまうと、残念ながら保険は機能しません。
逆に、日ごろから「具合が悪かったらすぐ病院に行こうね」「必要な手続きは一緒にやろうね」といった声かけができていたり、公的な制度や診断に対して抵抗がないタイプの親御さんであれば、保険がしっかり役立つ可能性が高まります。
つまり、保険に入るかどうかを考える前に、まずは「うちの親は、現実的に保険を活かせるタイプだろうか?」という視点で、一度イメージしてみることが大切なんです。
「性格的にちょっと難しそう…」と感じる方には、保険以外の選択肢も知っておいてほしい。
次は、公的な支援制度についてお話ししていきます。
すでに受けている公的サービス・制度
認知症保険を検討する際、つい忘れられがちなのが「すでにある支援制度」とのバランスです。
実は、日本には高齢者を支えるための公的サービスがかなり手厚く用意されています。
代表的なものをいくつか挙げると——
- 介護保険制度(要介護認定を受ければ、デイサービスや訪問介護が利用可能)
- 高額療養費制度(医療費が一定額を超えた場合、その分が戻ってくる)
- 医療費控除や障害者控除(確定申告で税負担が軽くなることも)
- 自治体の高齢者向け支援(配食サービス、見守り訪問、通院送迎など)
私の知人のお父さまも、要介護1と認定されたことで、週3回のデイサービスと月2回の訪問リハビリを、数千円の負担で受けられるようになりました。
現金をもらうより「困ったときに手が差し伸べられる安心感」のほうが、本人も家族も助かったそうです。
それに、もし医療保険や民間の介護保険にすでに加入しているなら、認知症による入院や通院の費用がすでにカバーされている場合もあります。
つまり、「保険が重複している」可能性もあるんです。
だからこそ、まずは一度、「今の時点でどんな制度を使えているのか」「すでに入っている保険で、何がカバーされているのか」をざっくり把握してみてください。
そうすることで、「じゃあ本当に足りない部分はどこだろう?」という問いの答えが、だんだん見えてきます。
そして次に見てほしいのが、家族の距離感やサポート体制です。
保険は、誰がどこまで親のケアに関われるかによって、活かされる場面も変わってきます。
その話は、次でじっくりお伝えしていきますね。
家族の距離感とサポート体制
「もし親が認知症になったら、私はどこまで関われるだろう?」
認知症保険を検討するうえで、避けて通れないのが「家族の距離感」と「サポート体制」の話です。
親の老いに気づきはじめたとき、私たちの多くはこう思います。
「何かあったときのために備えておかなくちゃ」と。
でも「何か」が起きたあと、実際にサポートするのは、家族の誰かです。
多くの場合、それはあなただったり、兄弟姉妹だったりします。
たとえば、こんな状況を想像してみてください。
親は地方に住んでいて、自分は都市部でフルタイム勤務。
月に一度の帰省がやっと。
きょうだいはいても、それぞれ子育てや仕事で手一杯。
親と日常的な連絡をとっている人が、自分以外にいない。
こんな場合、「いざというときは保険があるから大丈夫」と思っても、保険を「使う」までには多くの手間と動きが必要です。
病院に連れて行き、診断書をもらい、役所や保険会社とやりとりして…。
正直なところ、それだけのことを一人で担えるかどうか、自信がないという声もよく聞きます。
逆に、実家の近くに住んでいて、親ともよく顔を合わせる距離感の家族がいるなら、いざというときの手続きもスムーズですし、公的サービスも活用しやすくなります。
保険は「お金を受け取って終わり」ではありません。
受け取るまでのプロセスがあり、そしてその後の生活があります。
誰がその手続きを担うのか、どんな頻度で親に関われるのか──
それによって、保険が「使える備え」になるか「ただの安心材料」にとどまるかは大きく変わってきます。
また、現代は「遠距離介護」や「ワンオペ介護」が社会問題になっている時代です。
周囲に頼れる人が少ない場合には、保険に加えて地域包括支援センターや民間サービスなどを視野に入れておくことも必要かもしれません。
「自分が親のために、現実的にできることは何だろう?」
そんな問いを、今のうちに一度、心の中で投げかけてみてください。
備えとは、モノやお金だけではなく、「関わり方」を決めておくことも含まれているのです。
まとめ:保険を「入る/入らない」で終わらせないために
実際、保険に入っていても「いざというときに使えなかった」という声、意外とよく耳にします。
診断書の文言が足りなかった、家族が請求手続きを知らなかった、本人が請求できる状態じゃなかった…。
ほんの些細なことで、受け取れるはずのお金が宙に浮いてしまうこともあるのです。
だからこそ、大事なのは「入るかどうか」ではなく、「ちゃんと使えるかどうか」を意識しておくこと。
たとえば、診断書にどんな記載が必要か、代理請求の方法はどうなっているか、そもそも発症の基準は何なのか…。
今のうちに確認しておくだけでも、いざというときの行動がずいぶん変わります。
それと同時に、保険だけに頼りすぎない視点も持っていたいですね。
介護保険や高額療養費制度といった公的な支援も含めて、家族の生活や収支とのバランスを見ながら、「どこに、どれくらい備えるか?」を話し合っておく。
たとえば、「保険料が家計に負担になっていないか」「請求手続きが親にとって現実的か」など、ちょっとした違和感にも丁寧に向き合うことが大切です。
とはいえ、ネットやCMを見ていると「今のうちに入らなきゃ損!」というような広告が目につくことも。
つい焦ってしまいそうになりますよね。
特に、親の老後を思うと責任感を感じて「何かしなきゃ」と行動したくなるのが、私たち子世代の特徴かもしれません。
でも、だからこそ一度立ち止まって、情報を冷静に見極める時間も必要です。
周りの人が入っているから、という理由だけで決めるのは避けたいところです。
たとえば「手続きが複雑そうで、親一人では対応できなさそう」「うちの家計ではこの保険料は厳しい」といった、わが家ならではの現実的な事情を、判断の軸にしてみてください。
最初は面倒に感じるかもしれませんが、それが結果的に、安心につながる近道だったりします。
最後に、どうか忘れないでください。
備えるというのは、保険に入ることだけを意味するわけではありません。
認知症というテーマは、医療だけでなく、生活全体、そして家族の関係性にも深く関わってきます。
だからこそ、「わが家らしい備え方」は、人それぞれ違って当然なんです。
一人で悩まず、家族や信頼できる専門家と一緒に「もしものとき、どうする?」を話してみてください。
たとえすぐに答えが出なくても、その対話こそが、一番の備えになるはずです。
保険に入って終わりではなく、「本当に必要なとき、ちゃんと使えるか?」まで考えておくこと。
それが、あなたとあなたの大切な人たちにとって、心からの安心につながりますように。