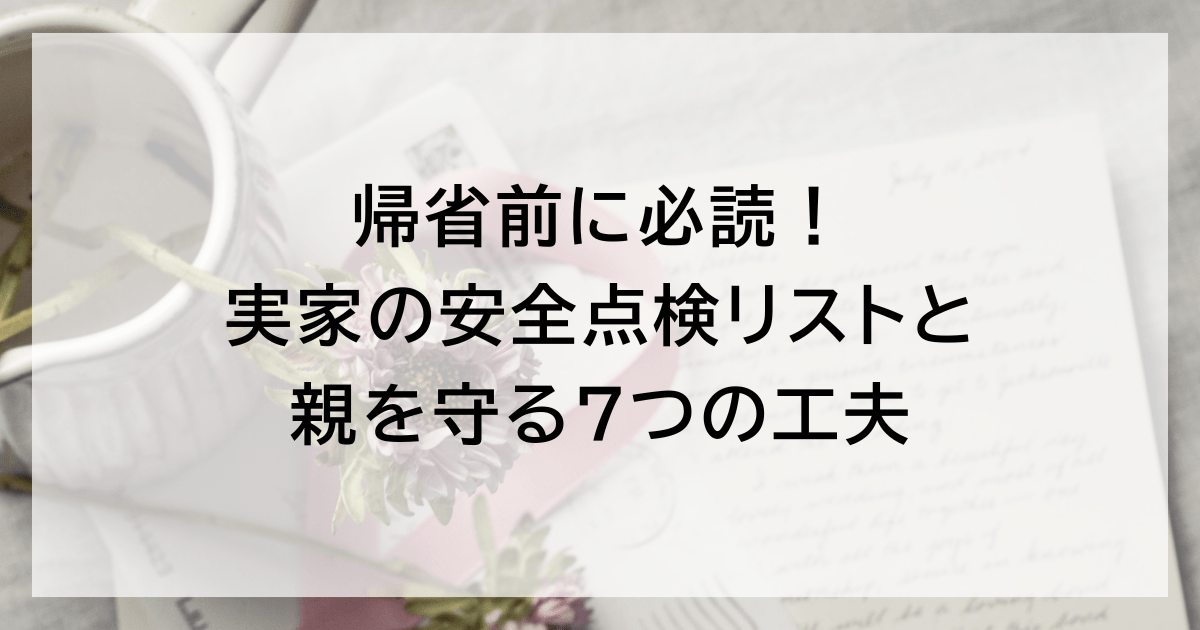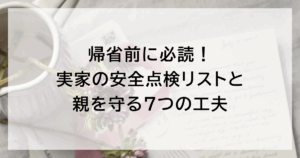実家に帰ると「やっぱり落ち着く」と感じる一方で、ふとした瞬間に「ここ、少し危ないかも」と気づくことはありませんか。
玄関の小さな段差、浴室の濡れた床、廊下の暗がり…。
若い頃なら気にも留めなかった場所が、年齢を重ねた親にとっては転倒や骨折の原因になり得ます。
一度のケガで生活が一変し、本人だけでなく家族全体の暮らしに影響を及ぼすことも少なくありません。
とはいえ、「大がかりなリフォームまでは難しい」と感じる方も多いでしょう。
実は数千円からできる手軽な工夫で、実家の安全性は大きく高まります。
本記事では、転倒や事故を防ぐためにチェックしておきたい7つの危険ポイントと、その改善方法をご紹介します。
次の帰省時に「すぐできること」を見つけ、安心できる実家づくりを始めましょう。
- 離れて暮らす親の安全が心配な方
- 実家に帰省したときに「危ないな」と感じたことがある方
- リフォームまでは考えていないけれど、簡単な対策を知りたい方
- 介護を始める前に、できる限り事故を予防したい方
- 家族と一緒に実家の安全を点検するきっかけを作りたい方
なぜ「実家の安全点検」が今すぐ必要なのか
「うちの親はまだ元気だから大丈夫」
私自身もついそう思って安心してしまったことがあります。
でも実際には、高齢の方にとって「ちょっとしたつまずき」が、その後の生活を大きく変えてしまう引き金になることが少なくありません。
今のうちから小さな備えを積み重ねておくことが、親の健康と、離れて暮らす私たち家族の安心を守る一番の近道だと感じています。
要介護となる主な原因(厚生労働省データより)
| 原因 | 割合(%) |
|---|---|
| 認知症 | 24.3% |
| 脳血管疾患 | 18.5% |
| 高齢による衰弱 | 12.8% |
| 転倒・骨折 | 12.5% |
| 関節疾患 | 10.2% |
| 心疾患 | 4.7% |
| その他 | 17.0% |
特に75歳を過ぎると骨がもろくなったり、足腰の筋力が弱まったりして、ほんの数センチの段差や濡れた床でも転んでしまうことがあるのです。
一度骨折すると入院・リハビリが必要になり、そこから寝たきりにつながるケースも少なくありません。
そして、それは本人だけの問題ではありません。
要介護の状態になれば、家族、とくに働き盛りの子世代にも大きな影響が及びます。
仕事と介護を両立させようとすると、生活のリズムが大きく崩れ、精神的にも経済的にも負担がかかってきます。
「もっと早く安全対策をしておけばよかった」と悔やむ声を耳にするたびに、予防の大切さを痛感します。
私の知人の母親も、まさにその一例でした。
70代前半で畑仕事もこなし、元気そのものだったのに、冬に帰省したときに廊下の段差でつまずき骨折。
たった数センチの段差が命運を分けることになるなんて、本人も家族も思っていなかったそうです。
そこから入院とリハビリが始まり、結果的に介護サービスを使うようになりました。
「もっと早く廊下に手すりをつけておけば」「照明を明るくしておけば」と後悔を口にしていたのが、とても印象に残っています。
こうした話は決して珍しくありません。
だからこそ、親がまだ元気な今のうちに「安全点検リスト」を活用して、家庭内の危険をひとつずつ減らしていくことが大切です。
親世代は「そんなに大げさなことを」と感じるかもしれません。
でも、「自分たちが安心できるから、やらせてね」と伝えれば、意外とすんなり受け入れてくれることも多いものです。
しかも、転倒防止や事故予防の工夫は必ずしも大規模リフォームが必要なわけではありません。
たとえば、自治体によっては「住宅改修助成制度」を利用でき、手すりの設置などにかかる費用を一部補助してもらえるケースもあります。
こうした制度をうまく活用すれば、負担を抑えながら対策を始められます。
親の家を点検するというと、ちょっと大げさに感じるかもしれません。
でも、次に帰省するときに「まず玄関から」「次は浴室」とひとつずつ見直していけば十分。
ここまでで「なぜ今すぐ点検が必要なのか」をお伝えしました。
では具体的にどんな場所を重点的に見直せばよいのでしょうか。
次の章では、実家の中で特に事故が起こりやすい「7つの危険ポイント」を、場所ごとに詳しく見ていきます。
実家でチェックすべき7つの危険ポイント
親が暮らす実家に帰ると、「やっぱり落ち着くな」とホッとすることが多いですよね。
けれどその安心感の裏側に、思いがけない危険が潜んでいることもあります。
長年住み慣れた家だからこそ、「ここは安全」と思い込んでしまい、小さな段差やちょっとした物の置き方が大きな事故につながってしまうのです。
実際、私自身も帰省したときに「このマット、滑りそう…」とハッとしたことがありました。
ここでは特に注意したい7つのポイントを取り上げ、それぞれの工夫についてご紹介します。
実家の7つの危険ポイント一覧
| 場所 | 危険要因例 | 改善策の例 |
|---|---|---|
| 玄関・廊下 | 段差、暗い照明、靴の散乱 | 手すり設置、センサーライト、靴収納整理 |
| 浴室・トイレ | 濡れた床、急な立ち座り | 滑り止めマット、浴室用手すり、便座調整 |
| 階段・段差 | 急な勾配、踏み外し | すべり止めシート、段差スロープ、足元ライト |
| リビング・寝室 | カーペットのめくれ、コード類 | カーペット固定、配線整理、ベッド高さ調整 |
| キッチン | 高い収納、火の扱い、床マット | 安全装置付きコンロ、収納改善、滑りにくいマット |
| ベランダ・庭 | 濡れた床、植木鉢の配置 | 滑り止めタイル、手すり設置、鉢の整理 |
| 電気コード等 | 延長コード、古い家電 | コードカバー、家電点検・買い替え |
玄関・廊下まわり
玄関は「家の顔」と言われますが、同時に毎日必ず通る場所。
だからこそ危険も潜んでいます。
段差や散らかった靴、暗い照明…これらが高齢の親にとって転倒の引き金になりかねません。
高齢になると筋力やバランス感覚が少しずつ衰えていき、若い頃なら気にもしなかった数センチの段差でつまずくことも珍しくありません。
さらに冬の玄関は外との温度差が大きく、血圧が急に上下してふらつくことも。
私の母も「廊下が暗いと夜はちょっと怖い」と口にしていましたが、意外と多くの家庭で廊下の照明は十分ではないのです。
対策としては、玄関に手すりをつけたり、センサー付きライトを置いたりするだけでも安心感が違います。
実際、たとえば東京都では、手すりの設置や段差の解消などのバリアフリー改修に対して、補助金制度を設けています。
お住いの市区町村により異なりますので、ぜひ調べてみてくださいね。
Amazonやニトリで買える滑り止めマットも数千円程度から揃っています。
「たったこれだけ?」と思える工夫が、大きな事故を防いでくれるのです。
浴室・トイレ
実は家の中で最も事故が多いのが浴室とトイレ。
濡れた床や急な立ち座り動作は、思った以上に危険です。
特に冬の浴室はヒートショックと呼ばれる急激な血圧変化が起きやすく、失神や転倒、場合によっては命に関わることもあります。
夜間にトイレへ行くときも要注意。
眠気やふらつきで転倒するケースは少なくありません。
私の父も「夜中に立ち上がると、ちょっと目が回る」と言っていたことがあり、そのとき初めて危険性を実感しました。
対策としては、浴室用の滑り止めマット(ニトリやカインズで2,000円前後〜)や、TOTOなどのL字型手すりが人気です。
便座の高さを少し上げるだけでも、腰や膝の負担がぐっと減ります。
意識すべきは「滑らない・つかまれる・立ちやすい」の3つ。
この3点が整えば、水回りでの事故は大きく減らせます。
階段・段差
階段や小さな段差は、骨折につながる大きなリスクです。
実際に「たった一段で足を踏み外しただけで大腿骨を骨折」という話は珍しくありません。
骨折をきっかけに寝たきりになるケースも多く、「命に直結する場所」と言っても大げさではないのです。
特に古い家は階段が急で段差も大きく、若い頃の感覚で上り下りするのは危険です。
私の祖母も、ほんの一瞬の油断で階段から滑り落ち、数か月の入院を余儀なくされました。
改善策としては、ニトリやアイリスオーヤマで買える段差スロープや滑り止めシートが手軽。
夜間には階段脇にLEDライトをつけるだけでも安心感が違います。
リビング・寝室
一番安心できるはずのリビングや寝室も、実は転倒事故が多い場所です。
カーペットのめくれ、床に伸びた電気コード…。
これらは「小さなつまずき」の代表格です。
寝室では、夜中にトイレへ行こうとしたとき、暗さや寝ぼけで転んでしまうことも。
私も帰省したとき、コードに足を引っかけそうになりヒヤリとした経験があります。
見慣れている家だからこそ、危険に気づきにくいのです。
IKEAや無印良品のコード整理グッズで配線をすっきりまとめたり、カーペットを滑り止めシートで固定したり。
ベッドの高さも調整できるタイプなら、立ち上がりやすく転倒予防になります。
安心できる空間だからこそ、見直す価値があります。
キッチン
キッチンは「火」と「転倒」、二つの危険が同居する場所です。
高い棚から無理に物を取ろうとして踏み台から落ちる。
床のマットでつまずく。
こうした事故は想像以上に多く報告されています。
さらに、火の消し忘れや不完全燃焼などは大きな火災につながるリスクがあります。
リンナイの安全装置付きガスコンロや、IHクッキングヒーターへの切り替えは有効な選択肢です。
また、無印やニトリの「低い位置に設置できる収納」を使えば、踏み台に頼らずに済みます。
料理を楽しむ場を「安全に楽しめる場」へと変えることが大切です。
ベランダ・庭
「外だから大丈夫」と油断しがちなのがベランダや庭。
ですが、濡れた床や植木鉢、段差が思わぬ事故につながります。
雨の日に植木の手入れをしようとして転んだ、雪の日に滑って骨折した――そんな話も実際にあります。
LIXILの滑り止め加工タイルや、ベランダに手すりを設置する工夫は有効です。
植木鉢は床一面に置くのではなく、まとめて配置するだけでも安心度は高まります。
電気コード・家電まわり
最後に忘れてはいけないのが電気コードと家電です。
床を這うコードに足を引っかけたり、古い家電から発火したり。
これは「転倒」と「火災」、二重のリスクを抱えています。
コードカバーや配線整理ボックス(Amazonやヨドバシで1,000円前後〜)を使えば、床がすっきりして転倒リスクは大幅に減ります。
実際、私の親戚も古い電気ストーブから発火しかけ、慌てて買い替えたことがありました。
「まだ使えるから」と油断していたのが危なかったのです。
こうして7つの危険ポイントを振り返ると、「うちは大丈夫」と思っていた実家にも、意外と多くのリスクが潜んでいることに気づかされます。
次の章では、こうした危険を「低コストで解決できる方法」をさらに掘り下げてご紹介します。
低コストでできる安全対策アイデア
実家の安全対策というと、「大がかりなリフォームをしないと意味がない」と思われがちです。
私も最初はそう考えていました。
でも実際は、数千円から1万円程度で始められる工夫がたくさんあるんです。
ホームセンターやネット通販をのぞいてみると、思った以上に簡単に取り入れられて、しかも効果の高いアイテムが並んでいます。
「やれることから少しずつ」が合言葉。
小さな工夫が、親の大きな安心につながります。
高齢の親世代は「まだ大丈夫」とつい言いがちです。
大掛かりなリフォームなんて話を持ち出すと、「そんなに心配しなくても」と笑ってしまうことも。
でも、実はちょっとした工夫だけでも事故を減らせることがわかっています。
東京都福祉局の「住宅改善事業」でも、手すりや段差解消といった小さな改修が重視されているのはその証拠です。
ホームセンターやネットで買える安全グッズ
たとえば、ホームセンターやネットで買えるグッズはすぐに役立ちます。
転倒防止の滑り止めマットや段差解消スロープは、カインズやニトリ、Amazonで2,000〜5,000円程度。
浴室やトイレには工事不要で取り付けられる「吸盤付き手すり」が便利です。
廊下や階段にはセンサーライトを置けば、夜中にトイレへ行くときも安心。
IKEAや無印良品にもおしゃれで実用的な商品が揃っています。
数千円〜1万円以内でできる改善例
数千円〜1万円以内で取り入れられるアイテムも豊富です。
家具の角に貼るコーナークッションは1,000円以下から買えますし、幅広の段差スロープでも1万円前後。
突っ張り棒や固定金具といった家具転倒防止グッズも、地震対策として自治体が推奨しています。
DIYでできる簡単な工夫
DIYでできる工夫もあります。
延長コードを床に這わせず壁沿いにコードカバーでまとめるだけで、つまずきリスクは大幅に減ります。
ベッドや椅子の高さは市販の継ぎ脚やブロックで変えられ、立ち上がりがぐっと楽に。
冷蔵庫や大きな家具も耐震マットで固定でき、女性でも一人で設置可能な商品がたくさん出ています。
私自身、実家の冷蔵庫に耐震マットを敷いたとき、「これだけでこんなに安心できるんだ」と実感しました。
低コストでできる安全対策の価格感
| 対策アイテム | 目安価格帯 | 購入場所例 |
|---|---|---|
| 滑り止めマット | 2,000〜5,000円 | ニトリ、カインズ、Amazon |
| 吸盤付き手すり | 3,000〜7,000円 | TOTO、ホームセンター |
| センサーライト | 1,500〜3,000円 | IKEA、無印良品、Amazon |
| 家具転倒防止グッズ | 1,000〜5,000円 | ホームセンター、通販 |
| 段差解消スロープ | 5,000〜10,000円 | ニトリ、アイリスオーヤマ |
こうしてみると、どれも工事不要で「買ってすぐに使えるもの」ばかり。
数千円の出費で転倒リスクを減らせるなら、その安心感は何倍もの価値があります。
おしゃれなデザインの商品も増えているので、「介護っぽく見えるのは嫌」という親世代の気持ちにも寄り添いやすくなっています。
つまり、安全対策は必ずしも大掛かりなリフォームを意味しません。
むしろ、思いついたところから少しずつ整えていく方が現実的で、親も抵抗なく受け入れてくれます。
最初の一歩は「玄関にセンサーライトを置く」「廊下に手すりを一本つける」。
その程度でも十分です。
ここまでで、低コストでもできる具体的な対策を紹介してきました。
次に大事なのは、これらの工夫をどうやって親に受け入れてもらうか。
次の章では、会話の工夫を通じて「安心を一緒に見える化」する方法について考えていきましょう。
親との会話から始める「安心の見える化」
実家の安全点検を進めたいと思っても、親から「そんなに危なくないよ」「大げさだね」と笑って受け流されること、ありませんか。
私も以前、父に廊下の段差のことを指摘したときに、軽くあしらわれてしまった経験があります。
こちらとしては心配だから伝えているのに、強く言えば反発される。
けれど黙っていれば不安は募るばかり。
そんなジレンマに悩む方も多いと思います。
親世代は「自分はまだ若い」「昔から慣れた家だから大丈夫」と考えがちです。
実際、長年住み慣れた家は身体に染みついていて安心できる場所ですから、その気持ちも理解できます。
ただ、体力や反応速度の衰えは本人には自覚しづらいもの。
事故はいつも突然起きるからこそ、押しつけではなく「納得してもらえる形」で話を進めることが大切になります。
私は「安心の見える化」という言葉が好きです。
言葉だけで説得するのではなく、一緒に「見える形」にしていく工夫があると、親も前向きになってくれるんです。
押しつけにならない声のかけ方
たとえば、声かけ一つでも工夫できます。
「お父さんのために手すりをつけたい」と言うと身構えられますが、「孫が遊びに来るときに危なくないようにしたいな」と第三者を理由にすれば、案外すんなり受け入れてくれます。
私自身も「夜中にトイレへ行くとき、廊下が暗いと怖いな」と自分の体験を話したら、母が「そうね、私もそう感じてた」と共感してくれたことがありました。
共同作業としての点検
また、点検を「共同作業」として取り組むのもおすすめです。
「実家の7つの危険ポイント一覧」を一緒に見ながら「ここ危なくない?」と話し合う。
記録して「見える化」する工夫
さらに、点検した結果を写真で残してアルバムにしておくと効果的です。
「この前ここを直したよね」「次はここに手を入れようか」と進捗が目に見えると、親も「一緒に整えている」という気持ちになれます。
こうした工夫を積み重ねていくと、親も「守られている」ではなく「一緒に作っている」と感じられるようになります。
それはプライドを守りつつ、安全を整えていく一番自然な形なのだと思います。
結局のところ、安全点検は押しつけではなく、親との共同作業です。
小さな声かけや写真一枚でも、安心を「見える化」していくことで、親が自然と受け入れてくれる環境が整っていきます。
ここまでで、親との関わり方と「安心の見える化」のヒントをいくつかご紹介しました。
次は最後に、なぜ今、安全点検に取り組むことが家族にとって大切なのかをもう一度振り返ってみたいと思います。
まとめ
ここまで読んでいただいた方に一番お伝えしたいのは、「大きな工事をしなくても、日々のちょっとした工夫で親の安全は守れる」ということです。
転倒や事故は特別な出来事ではなく、ほんの小さな油断や段差がきっかけになることが多いもの。
だからこそ「まだ大丈夫」と思える今のうちに、できることから始めることが、ご両親の暮らしと、そしてあなた自身の安心につながります。
骨折から寝たきりになるケースは少なくなく、生活が一気に変わってしまうこともあります。
でも、玄関に手すりを一本つける、浴室に滑り止めマットを敷く、廊下に小さなセンサーライトを置く――そうした数千円でできる工夫が事故を防ぐ現実的な方法なのです。
今回ご紹介した「実家の7つの危険ポイント」を思い出してみてください。
玄関や廊下、浴室やトイレ、階段や段差、リビングや寝室、そしてキッチンやベランダ。
どれも、普段見慣れているからこそ「危険」とは気づきにくい場所ばかりです。
けれど少し視点を変えるだけで、改善の余地が見えてきます。
しかも、それは大がかりなことではなく、ホームセンターやネットで買える身近なグッズや、ちょっとしたDIYでできる工夫なのです。
親も「守られる存在」ではなく「一緒に整える仲間」だと感じられることで、安全対策はずっと進めやすくなります。
私自身、母と一緒に廊下を見直して「ここに明かりを足そうか」と話し合ったとき、ただの点検が家族のコミュニケーションの時間になったことを覚えています。
最後に、次回の帰省時にすぐ役立つ「簡単チェックリスト」を用意しました。
次回の帰省時にすぐ役立つ「簡単チェックリスト」
| チェック | 内容 |
|---|---|
| □ | 玄関や廊下に段差や暗がりがないか確認する |
| □ | 浴室に滑り止めマットや手すりを設置できるか見る |
| □ | 階段や段差にすべり止めや足元ライトを追加する |
| □ | リビングや寝室のカーペットやコード類を整理する |
| □ | キッチンの収納や火の元の安全性をチェックする |
| □ | ベランダや庭の段差や植木鉢の配置を見直す |
| □ | 古い家電や延長コードを点検・更新する |
このリストを片手に実家を一巡するだけでも、「今できること」が見えてくるはずです。
親の安全を守ることは、未来の自分や家族の生活を守ることでもあります。
「次の帰省で一つだけでもやってみよう」と心に決めるだけで、行動は変わります。
小さな一歩が、親の暮らしに大きな安心をもたらすのです。
そして、どの部分を優先するか迷ったときや、より具体的なアドバイスが欲しいときには、地域の高齢者支援窓口や自治体の住宅改修助成制度を活用してみましょう。
制度や専門家の力を借りれば、さらに確実で安心な暮らしに近づけます。
- 転倒や事故は「小さな段差や暗がり」など身近な場所から起こる
- 数千円〜1万円程度の工夫で、大きな事故を防げる
- 押しつけではなく「一緒に見直す」ことが親世代に受け入れられる秘訣