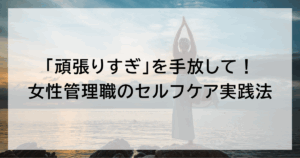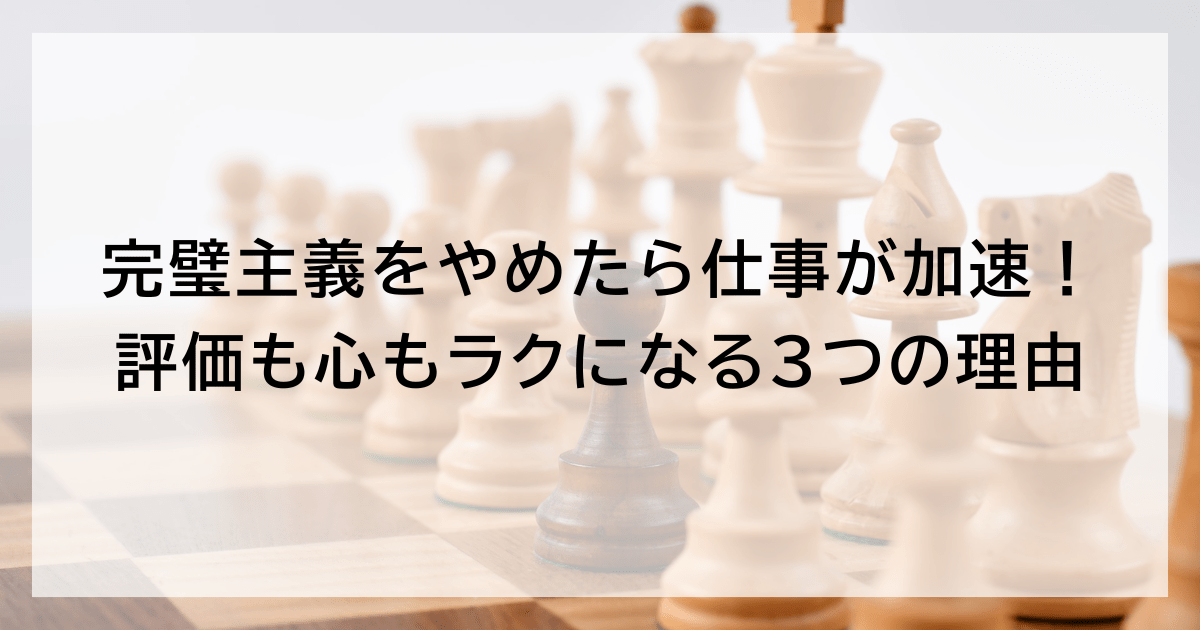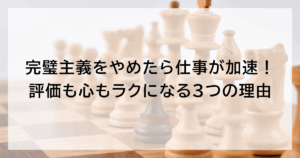「もっと頑張らなきゃ」
「完璧に仕上げないと認めてもらえない」
そんな気持ちで夜遅くまで働いた経験はありませんか?
私自身、かつては資料の1枚1枚に執拗にこだわり、上司に提出する直前まで修正を繰り返すタイプでした。
でも、その努力の割に評価は伸びず、心身ともに疲れ果てるばかり。
正直、「もう限界だ」と思った瞬間が何度もありました。
ところがある日、仕事の進め方を少し変えて「完璧主義を手放す」という選択をしただけで、驚くほど毎日がラクになり、逆に成果まで上がりはじめたのです。
時間もストレスも減り、「なんで今まであんなに頑張りすぎていたんだろう」と拍子抜けしたほどでした。
この記事では、なぜ完璧主義が仕事を苦しくさせるのか、そして手放したときにどんな変化が訪れるのかを、私の実体験を交えて紹介します。
「頑張っているのに評価されない」
「気づけばいつも疲れている」
そんなあなたにこそ読んでほしい内容です。
なぜ完璧主義は危険なのか?
「もっと丁寧にやらなきゃ」
「これじゃダメ、まだ足りない」
そんなふうに自分を追い込んだ経験はありませんか?
私もかつて、企画書ひとつに徹夜で向き合い、翌朝ふらふらのまま出社したことがあります。
でも、その資料を見た上司の反応はひと言。
「ありがとう、ちゃんと内容は伝わってるね」
あれだけ必死になったのに、評価されたのは「完璧さ」ではなく「伝わるかどうか」だけだったのです。
実は、完璧主義は成果を高めるどころか、あなたの時間と心をじわじわと削り取ります。
なぜなら、「絶対にミスできない」という思いが強すぎると、作業時間が膨れ上がり、ちょっとした指摘にも過敏に反応してしまうからです。
結果、「まだ終わらない」「もっとやらなきゃ」と自分を追い込み、気づけば深夜でも頭が休まらない状態に。
たとえば、社内資料のスライド1枚に3時間もかけてしまう――
そんなときの頭の中には、「誰にも指摘されたくない」「100点じゃなきゃ意味がない」という声が響いています。
でも、現実に上司や同僚が求めているのは「アート作品のような完璧さ」ではなく、「伝わる内容」です。
この認識のズレが、無駄な時間とストレスを生んでいるのです。
たとえば、小さなミスを全体の失敗と捉え、「私はダメだ」と一気に自己否定へ走ってしまう傾向です。
これが積み重なると自己肯定感が下がり、新しい挑戦をする気力すら奪われます。
背景には、リモートワークの広がりや、成果主義の加速があります。
自分の仕事ぶりが見えにくくなる分、「もっとちゃんとしなきゃ」と不安が膨らみやすいのです。
では、どうすればこの悪循環から抜け出せるのでしょうか?
ここからは、私自身が実践して効果を感じた習慣や、心理学の知見を取り入れた考え方の切り替え方を紹介します。
次で、すぐに取り入れられる具体的なステップを見ていきましょう。
完璧主義と自己肯定感の悪循環
ミスを恐れる
過度な時間投入
疲労・ストレス
成果が伸びない
自己否定が強まる
さらにミスを恐れる
完璧主義を手放すための実践法3つ
「もう少しだけ整えたい」
「ここに影を入れたら見やすいかも」
仕上げの「もう一手」が、気づけば深夜まで続いてしまう。
私も長いあいだ、その無限ループの住人でした。
完璧主義をやめようと決めても、
「どこで止めればいいの?」
「手を抜いてると思われない?」
と心がざわつくんですよね。
ここでは、私自身や周りの女性管理職が実際に試して効いた、等身大の3ステップをまとめました。
どれも小さく始められて、続けるほど「頑張りすぎの悪循環」に歯止めがかかります。
まずはできそうなものから、一緒に肩の力を抜いていきましょう。
「80点で提出」を意識する
最初の一歩は、勇気を出して「未完成のまま」世に出すこと。
言い換えると、「80点でもまず出す」を自分の新ルールにする、です。
なぜ効くのか。
完璧を狙うと提出が遅れ、その間に不安が雪だるま式に大きくなります。
「まだ甘い」
「指摘が怖い」
と手直しを重ねるほど、視野は狭まり、判断も鈍る——
私が何度も体験した流れです。
一方、80点で早めに出すと、上司や同僚から具体的なフィードバックが戻り、修正の方向が一気にクリアになります。
実際、同僚は2週間かけて作り込んだ社内プレゼンに「ここ、もっとシンプルでOK」とひと言をもらい、次回からは「早め提出→対話で仕上げる」スタイルに切り替えました。
仕上がりはむしろ良くなり、工数は半分に。
怖さがチクッとする時は、ひとこと添え書きを。
「粗い版ですが、方向性の確認をお願いします」
この一文で、受け手の期待値が整い、返ってくる言葉もやわらかくなります。
実務のコツは区切りを決めること。
Trello や Asana のチェックリストで「骨子→主要スライド→注釈」の3段階に分け、「骨子ができたら提出」の基準を可視化。
Slack や Teams に「初稿です。目的・結論・未確定事項はこの3点です」と短い要約を貼ると、レビューの速度も質も上がります。
「提出のハードル」が下がったら、次は「どこに力を配るか」。
ここからが、効果をさらに底上げする鍵です。
タスクの優先順位を決める習慣
すべてを100点で仕上げようとすると、時間も体力もあっという間に底をつきます。
だからこそ、「大事な3つに集中する」。
私は毎朝ノートに MIT(Most Important Tasks)を3つだけ書き、残りは「あとで良い」扱いにします。
この「選ぶ」行為そのものが、心の余白を取り戻してくれます。
なぜ3つなのか。
人の注意力は有限だから。
小さな用事(チャット返信、細かな体裁直し)が行列をつくるリモート時代こそ、優先順位の習慣はお守りになります。
やり方はシンプルで、
- 目的(何のための一日?)を一行
- MITを3つ
- それ以外は Todoist や Google カレンダーで翌日以降に送る
これだけ。
先に大事な3つを終えると、残りにかける時間も気持ちも自然に生まれます。
「後回しの不安が消えない…」という声もよく届きます。
対処法は「見える化」。
Notion で「今週やらないリスト」を作り、意図的に「置いておく」項目をひとまとまりに。
家事やケアと仕事が並走する日も多い私たちだからこそ、「選ぶ勇気」は自己防衛。
優先順位が定まると、最後の壁——「失敗が怖い」——にも、向き合えるようになります。
ここで、恐れを学びに変える仕組みを用意しましょう。
失敗事例を共有して安全に学ぶ方法
失敗は隠すもの、ではなく「共通の教材」に。
そう思える場があると、完璧の呪いは驚くほど弱まります。
根っこにある思い込みは「ミス=評価が落ちる」。
私の前部署では、月1回「今月のしくじり」を5分ずつ持ち寄る時間を設けていました。
ルールは3つだけ——責めない/名指しにしない/次の一手を一緒に出す。
たとえば
- 「見積もりの桁を誤って送信→テンプレートに自動フォーマット追加」
- 「リリース文の表現が伝わりにくかった→冒頭に1行要約を固定」
最初は手が震えるほど恥ずかしかったのに、3回目には「言ってしまった方がラク」へ。
もし職場で場づくりが難しければ、外のコミュニティを借りるのも現実的な選択です。
女性向けキャリア支援の SHElikes や、メンター探しのできる MENTA では、学びや失敗談を気軽に共有できます。
匿名のフォーム(Google フォームなど)で「しくじり投稿→月次メモにまとめる」だけでも、心理的なハードルはぐっと下がります。
投稿の書き出しテンプレはこれでOK。
- 何が起きた?(事実)
- なぜ起きた?(推測で良い)
- 次はどうする?(再発防止の一手)
こうして失敗を「恥」から「資源」に変えると、挑戦の回数が増え、体験の母数が結果を押し上げます。
小さく始めるなら今日から
- 80点でもまず提出。
添え書きは「方向性の確認をお願いします」。 - MITを3つ。
残りはアプリに送り、「今週やらない」箱へ。 - 月1回の「しくじりタイム」。
外部コミュニティでも可。
ここまで読んで「やれそう」と思えた一つが、あなたの脱・完璧主義のスタートラインです。
完璧をやめたら起きた変化
作業スピードが一気に上がった話
以前の私は、資料づくりに何時間もかけていました。
1枚のスライドを仕上げるのに丸一日。
レイアウトを直しては「これで本当に大丈夫?」と自問し、言葉尻まで何度も修正。
気づけば時計の針が締切に迫っていて、夜遅くにパソコンの前で焦る――
そんな日々でした。
思い切って「完璧を目指さない」と決めたのは、ちょうど社内プロジェクトのプレゼン資料を作っていたときです。
それまで丸一日かかっていた作業が半日で完成。
しかも、早めに上司や同僚に見せられるので、その場でフィードバックをもらいながら改善できる。
結果として、最終的な資料の出来はむしろ良くなったのです。
なぜこんな変化が起きるのか?
理由はシンプルです。
完璧主義だと、すべてのタスクに均等にエネルギーを注いでしまい、「重要な部分」と「それほど重要でない部分」の線引きができなくなる。
でも、あえて80点を目指すと、「まず終わらせる」というゴールが明確になり、本当に注力すべきところにだけ力を集中できます。
たとえば、ビジネススキルを学べるオンラインサービス「グロービス学び放題」でも、すべての講座を隅々まで理解しようとするより、今の課題に直結する部分だけをピンポイントで学ぶほうが効率的だと言われます。
この考え方は、そのまま仕事の進め方にも応用できますね。
こうして「まずは完成」を合言葉にすると、仕事のスピードが上がるだけでなく、時間の余裕も生まれます。
心の軽さは想像以上だった
完璧主義をやめて一番驚いたのは、気持ちがこんなにも楽になることです。
理想の自分と現実の自分を常に比較して、「まだ足りない」という感覚が強まってしまうのです。
逆に、
「今できるベストを出す」
「必要ならあとで修正すればいい」
と考えるだけで、心がふっと軽くなり、結果としてパフォーマンスも向上します。
同僚や部下と話すときに、
「完璧じゃなくていいよ」
「まずやってみよう」
と自然に声をかけられるようになったのです。
その一言でチームの空気が柔らかくなり、心理的な安全性が高まるのを実感しました。
人は安心できる環境では思い切って挑戦できます。
結果として組織全体のスピードも上がる――ちょっと不思議ですが、本当にそうなんです。
実際、経営者コミュニティで「失敗談をシェアする会」に参加したときも、「あ、自分だけじゃないんだ」と心からホッとしました。
完璧じゃなくても成果は出せる。
それを生で聞けたことで、自分の考えがさらに確信に変わりました。
完璧主義を手放したBefore/After
| 項目 | Before(完璧主義) | After(手放した状態) |
|---|---|---|
| 仕事の進み方 | 1つのタスクに過剰な時間 | 優先度をつけて効率的 |
| メンタル | 常に緊張・疲労 | 余裕が生まれる |
| 評価 | 「丁寧だが遅い」 | 「スピーディで助かる」 |
完璧を手放すと、仕事の効率が上がるだけでなく、心の余裕まで取り戻せます。
まとめ
完璧主義は、一見「真面目さ」や「責任感の強さ」の証に見えます。
ですが、その裏側には「失敗したくない」「誰にも欠点を見せたくない」という恐れが潜んでいます。
それでも上司からの評価は「細かいけど進みが遅いね」という一言。
心が折れそうになりました。
しかし、思い切って「8割で提出してみよう」と方針を変えたとき、意外なことに上司から返ってきたのは「仕事が早くなったね」「要点がわかりやすい」という言葉。
私が勝手に背負っていた「完璧の呪縛」は、誰からも求められていなかったのです。
この経験から学んだのは、仕事は「100点」ではなく「伝わること」「進むこと」が価値ということ。
細部にこだわるのは悪いことではありませんが、それが目的になってしまうと生産性もメンタルも削られてしまいます。
一方で、完璧主義を手放すと視野が広がり、人に頼ることができるようになります。
「ここはアドバイスをもらおう」
「これは早めに共有しよう」
と柔軟な進め方ができるため、仕事が進みやすくなります。
完璧を目指さないことで得られるのは「手抜き」ではなく、「余裕」です。
その余裕がクリエイティブな発想や、人との良好な関係を生み出します。
私が実感した最大の変化は「毎日が少し楽しい」と思えるようになったこと。
これこそが、成果と幸福感を同時に引き寄せる最大のポイントです。
- 完璧主義は時間を奪い、評価を上げるどころか逆効果になることがある
- 8割の完成度で進める方がスピードと成果が両立しやすい
- 「余裕」が新しい挑戦や発想力を生み、結果として評価につながる